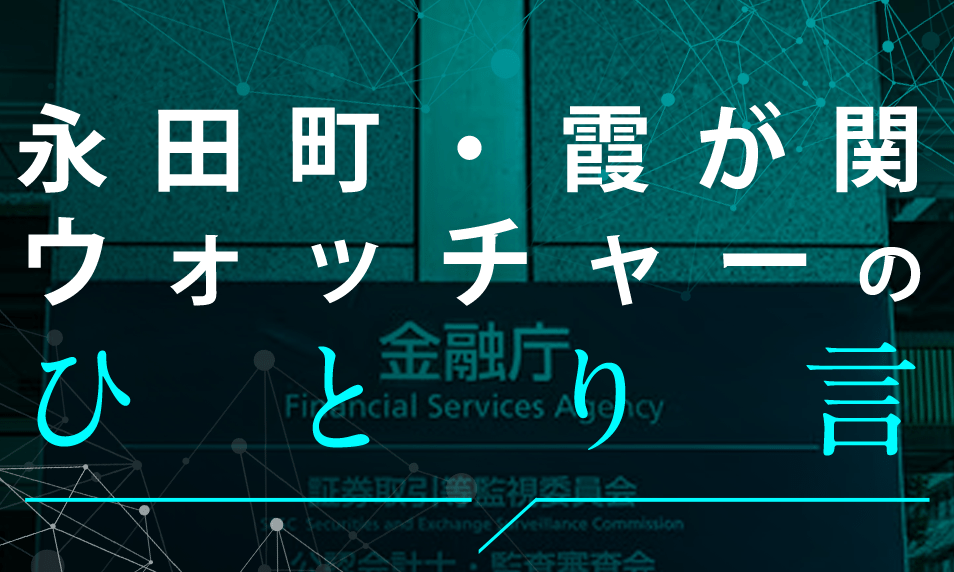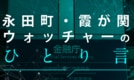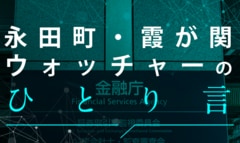金融庁は8月29日に公表した令和8年度(2026年度)税制改正要望において、少額投資非課税制度(NISA)の拡充策として以下の3項目を求めている。以下、筆者なりに論点を整理してみた。
1.こども支援の一環としての、つみたて投資枠における対象年齢の見直し
本施策は、こども家庭庁との共同要望である。現在18歳以上に限定されているNISA制度のつみたて投資枠を未成年にも拡大することにより、若年層における早期からの資産形成習慣の定着と、親世代から子世代への計画的な資産移転の促進を図るものである。
「ジュニアNISA」の時にもあったが、本施策には「金持ち優遇」との批判が付きまとう。未成年者のNISA口座を開設し、資金を拠出できるのは、主にその親や祖父母など、ある程度の資産や所得を持つ層であり、経済的に余裕のない家庭では、そもそも投資に回す資金がなく、制度の恩恵を受けることができない。結果として、富裕層や高所得者層が、非課税メリットを享受しながら、より早期から子や孫の資産形成を有利に進めることができるため、資産格差が拡大するのではないか、という懸念がある。
こうした批判をする方々には、本施策は、若年層の金融資産形成への意識を高め、日本の「貯蓄から投資へ」の流れを加速させるほか、高齢者から若年層への資産移転を進め、日本経済全体の活性化に繋げるという政策目標を叶えるためのツールであり、投資促進策の性質上、ある程度の余裕資金が前提となるのは避けられないことを納得してもらう必要がある。経済的に困窮している家庭に対しては、所得再分配策として、生活保護や児童手当、教育費支援など、直接的な所得支援や福祉政策の充実を図るべきであり、こうした異なる政策目標を持つ投資促進策と所得再分配策をうまく組み合わせることが政府には求められるのではないだろうか。
他方、政府は、家庭の経済状況に関わらず、全ての国民が金融リテラシーを向上できるように、学校における金融教育のさらなる充実を図るほか、J-FLEC(金融経済教育推進機構)など公共機関による親向けのNISA活用セミナーや金融基礎講座の充実を図るべきだ。金融知識の習得機会は、全ての国民に公平に与えられなければならないと思う。
2.さまざまな資産運用ニーズに応えるための、対象商品の拡充
NISA対象商品の拡充については、金融庁が設置した「NISAに関する有識者会議」が8月29日に公表した「中間とりまとめ」に具体的な方向性が示されており、投資初心者や高齢者層のニーズに応えるべく、(債券など)株式に比べてリスクが低く、より安定的なキャッシュフローが望めるアセットクラスを投資対象とした投資信託など、比較的低リスクの商品を新たに対象に加えるほか、つみたて投資枠の投資対象となる株式指数について、「マーケット全体を広くカバーし、すでに市場関係者に広く浸透している」という基準を明確化し、欧州やアジアなどの地域別株式指数を単体で扱う商品についても「検討する余地がある」と言及している。
なお、今年4月に、自民党の資産運用立国議員連盟が「プラチナNISA」の導入を提言した際、業界関係者間では「対象商品に毎月分配型投資信託が追加されるかも」と期待されていたが、今回の「中間とりまとめ」には言及がなく、税制改正要望も「さまざまな資産運用ニーズに応えるための、対象商品の拡充等」というざっくりとした記載に留まっている。
そうした中、先日、筆者は金融庁幹部と面談する機会があり、毎月分配型投信をNISA対象商品に加えることを検討しているか質問したところ、「(以前より問題視されている)コストが高く、タコ配が頻発するような毎月分配型投信を対象とするのはいかがかと思う」と言いつつも、きっぱりと否定することはなかった。おそらく、より低コストで元本払戻金も限定的な設計にした毎月分配型投信であれば、対象に加えていくのではないかと思われる。なお、同幹部は、「それよりも、一部の証券会社で既に提供されている定期売却サービスの利用が広がれば良いのだが…」と付け加えていたことをお伝えしておきたい。
3.投資商品の入替をしやすくするための、非課税保有限度額の当年中の復活
現行のNISA制度では、保有商品を売却した場合、その非課税投資枠が復活するのは翌年1月1日となっている。今回、枠復活を当年中に可能とする制度改正を要望し、ライフステージの変化や市場環境の変動に応じて、投資家が機動的に資産配分を調整できることを目指している。
投資商品の入れ替え(スイッチング)については、枠を簿価ベースで復活させるのか、時価ベースで復活させるのかが議論になる。
商品を売却した場合、その商品の「買付時の簿価」分の非課税保有限度額が当年中に復活し、その復活した枠で新たな商品を購入できるとした場合、売却時の時価(実際に手元に戻る金額)と、復活する枠の金額(簿価)が異なってくる。例えば、利益が出た商品を売却した場合、売った金額よりも少額の枠しか復活しない一方、投資で損失が出た場合は、時価で復活するよりも多くの枠が復活することになる。ちなみに、大きく利益が出た商品を売却した場合、簿価分の枠しか復活しないため、それ以外の資金を再投資する時は課税口座での運用となる。
他方、時価ベースでの入れ替えでは、商品を売却した場合、その商品の「売却時の時価(約定金額)」分の非課税保有限度額が当年中に復活し、その復活した枠で新たな商品を購入できる。「売って手元に戻ってきた金額=再投資できる枠」という考え方になるため、顧客にとっては非常に直感的で分かりやすい。
利益が出た商品を売却した場合、その利益分も含めて枠が復活するため、より多くの資金を非課税枠内で再投資することが可能になり、複利効果を最大限に享受しやすい。ただし、損失が出た商品を売却した場合、時価(売却価格)分の枠しか復活しないため、簿価ベースの場合よりも少ない枠しか再利用できない。なお、こうした「利益が出たらより多くの枠で再投資できるが、損失が出たら再投資できる枠は減る」という概念は、投資の「リターン」と「リスク」の両面を理解してもらうには有益ではないかと思う。
一方、難点は、現行の生涯投資枠(1800万円)が簿価ベースで管理されているため、売却時の枠復活だけ時価ベースにすると、制度全体の整合性が失われてしまうことだろう。この解決策としては、生涯投資枠の管理方法も「時価ベース」に移行することが考えられるが、これはNISA制度の根幹に関わる大きな変更であり、システム改修なども含め実現のハードルはかなり高い。次善策としては、NISA口座における簿価ベースの買付額と時価ベースの評価額を顧客に提供し、差分を常に認識しつつ枠管理してもらうことだろうが、システム対応に加え、顧客において、ある程度の金融リテラシーを必要とする作業であり、こちらもハードルは低くないように思う。
なお、業界関係者の話によると、現時点では、簿価ベースで枠を復活させることを前提に検討が進んでおり、時価ベースでの復活は見送られる公算が高いようだが、それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、中長期目線で深い議論が行われることを期待したい。
いずれにせよ、顧客の金融リテラシーの向上がさらなるNISA活用に向けた要の施策であることは間違いない。金融広報中央委員会が実施している金融リテラシー調査などで、「金融経済教育を受けた経験がある人の方が、投資における損益がプラスとなる割合が相対的に高い」という調査結果が出ていることも申し添えておきたい。