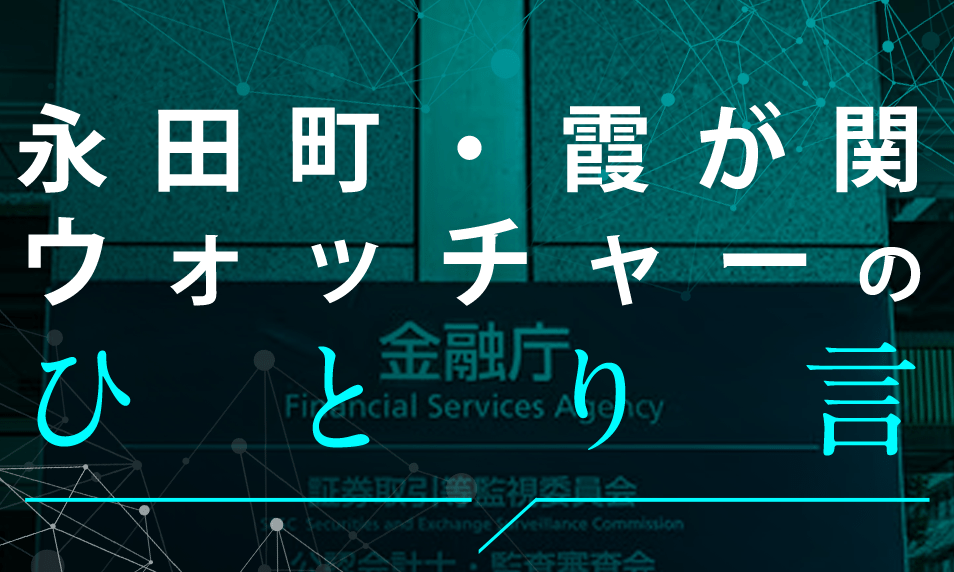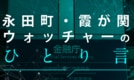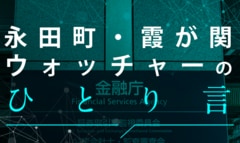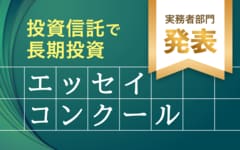個人の資産形成を後押しする税制優遇策としてはNISAとともにiDeCoがあるが、iDeCoの加入者数は 371万人(令和7年7月時点)に留まっており、NISA(2,647万口座。令和7年3月末)に大きく水をあけられている。
こうした中、2025年6月に成立した年金制度改正法では、さらなるiDeCo活用策として、掛金拠出限度額の引上げ(第1号被保険者(自営業者など)が月7.5万円、第2号被保険者(会社員・公務員など)が月6.2万円に引き上げられる予定)や加入可能年齢の引上げ(70歳未満の老齢基礎年金やiDeCo老齢給付金を受給していない人はiDeCoの加入・継続拠出が可能となる予定)が盛り込まれた。
こうした拠出限度額や加入可能年齢の改定により、ある程度の加入者増が見込まれるだろうが、NISA並みに、多くの国民にiDeCoを活用してもらうには、より多角的な視点で施策を考える必要があるように思う。
以下、現行制度の課題を踏まえつつ、筆者なりにいくつか施策案を提示してみたい。
提言1:加入対象者の拡大と柔軟な拠出制度の導入
現状、iDeCoへの加入は任意となっている。また、加入を希望しても、企業型確定拠出年金(DC)を導入している会社において、マッチング拠出を行っている場合はiDeCoへ加入できないといった制約がある。そのほか、拠出金額の変更が年1回など、制度が柔軟性に欠けている。
【具体策】
① 原則、全勤労者のiDeCo加入
・企業年金(確定給付企業年金、確定拠出年金)の有無にかかわらず、新規採用者を対象に「雇用時自動加入(opt-out方式)」を導入する(従業員は自ら明示的に辞退しない限り加入)。
・中小企業に対するiDeCo導入支援を強化し、企業型DCの導入が難しい企業でもiDeCoを従業員に推奨・支援するインセンティブを付与する。
②拠出金額の「月次変更」の容認
・家計の状況に応じて、毎月の拠出金額を柔軟に変更できるようにする。これにより、急な出費や収入減にも対応しやすくし、拠出継続のハードルを下げる。
③最低拠出額の撤廃または大幅な引き下げ
・現状の月額5,000円という最低拠出額を撤廃する、もしくは、月額1,000円程度に引き下げることにより、少額からでも始めやすくし、若年層や低所得者層の参入を促進する。
提言2:税制優遇措置の抜本的強化と簡素化
現状、所得控除のメリットが所得税・住民税に限定され、恩恵が分かりにくい。また、拠出時、運用時、受取時の税制優遇があり、複雑化している。
【具体策】
①拠出額に対する「所得控除」から「税額控除」への移行
・所得控除では所得が高い人ほどメリットが大きくなるところ、税額控除(拠出額の一定割合(例:20%)を所得税額から直接控除するなど)にすることで、所得の多寡にかかわらず一定の税制優遇を享受できるようにする。
②受取時の課税優遇のさらなる拡充
・退職所得控除や公的年金等控除の枠をさらに拡充し、受取時の税負担を実質的にゼロに近づける。特に、年金形式での受取を推奨するための優遇措置を強化する。
提言3:iDeCo運用の選択肢の拡充と情報提供の強化
現状、投資初心者が商品選択に迷わないように運用商品の提供数が35本に制限されているが、それでも商品選定に悩む投資初心者が少なくない。他方で、iDeCo加入者の属性(年齢、投資経験、リスク許容度、資産形成目標など)が多様化しており、現状の35本という上限では、全てのニーズをカバーしきれない可能性がある。
【具体策】
①「iDeCo推奨ファンド」の選定と提供義務付け
・金融庁が、長期・積立・分散投資に適した低コストのインデックスファンド等を「iDeCo推奨ファンド」として選定し、全てのiDeCo取扱金融機関にその提供を義務付ける。これにより、どの金融機関を選んでも一定水準以上の商品にアクセスできるようにし、商品選択のハードルを下げる。
②「デフォルト・ポートフォリオ」の導入と自動運用プランの提供
・投資経験のない加入者向けに、年齢やリスク許容度に応じた「デフォルト・ポートフォリオ」を設定し、加入時に自動的にそのポートフォリオで運用が開始される選択肢を提供する。これにより、商品の選び方が分からないという理由でiDeCo加入を躊躇する層を減らす。
③運用商品の提供数の大幅増(もしくは撤廃)
・商品提供数を増やし、国内外の新しい投資手法や資産クラスを踏まえた商品を対象に加えることにより、各加入者が自身の投資目標やリスク許容度により合致したポートフォリオを構築しやすくする。
④ iDeCo専用ポータルサイトの構築と情報提供の強化
・国民年金基金連合会が主導し、iDeCoに関するあらゆる情報を集約したポータルサイトを構築し、加入方法、金融機関比較、商品情報、運用シミュレーション、税制メリットの具体的な計算例などを分かりやすく提供する。
・専門家によるオンラインセミナーやQ&Aセッションを定期的に開催し、国民のリテラシー向上を支援する。
提言4:手続きのデジタル化
現状、口座開設時や加入者情報変更時、給付金受取時などは、各管理機関に対し書面による届け出が必要であり、手続きも煩雑となっている。
【具体策】
①マイナンバー・マイポータル連携によるオンライン申請の促進
・オンライン化することで、自宅や外出先から手軽に手続きできるようし、加入へのハードルを下げ、継続しやすくする。
・特に、住所変更や転職時の企業型DCからの移換など、手続きが煩雑に感じられる部分を簡素化することで、手続き漏れや遅延のリスクを減らす。
提言5:制度の簡素化とコスト軽減
現状、iDeCoは、制度主体である国民年金基金連合会(国基連)のほか、運営管理機関、資産管理機関、レコードキーパー、商品提供機関など多くの組織体が関わる複雑な制度となっている。その複雑さゆえに事務コストやシステムコストが大きくなり、結果として利用者が支払う手数料が高くなりがちである。
【具体策】
① 役割分担の見直し
・各機関に共通のプラットフォームを導入するほか、一部の事務作業の一元化・集約化などを促進する。
・特に、国民年金基金連合会が担う役割と、運営管理機関が担う役割について、重複や非効率な部分がないか見直し、効率化・簡素化を図る。
②デジタル技術の活用
・AIを導入し、事務手続きの自動化を進めることで、人件費などのコスト削減を図る。
・ブロックチェーン技術などを活用した、よりセキュアで効率的なデータ管理システムの構築を検討する。
③手数料体系の透明化・簡素化
・各機関が徴収する手数料の妥当性を検証し、よりシンプルな手数料体系へ見直すとともに、情報開示を進める。
提言6:企業によるiDeCo導入・活用支援の促進
現状、企業型DCの導入が進まない中小企業が多く、また、従業員へのiDeCoに関する情報提供や教育が不足している。
【具体策】
①中小企業向け「iDeCo導入支援補助金」の創設
・中小企業が従業員のiDeCo加入を支援するための福利厚生制度を導入する際にかかる費用(事務手数料、従業員向け説明会費用など)に対して、国が補助金を支給する。
②企業内研修への「iDeCo講座」設置の義務付け
・一定規模以上の企業に対し、従業員向けにiDeCoに関する基礎知識や活用方法を学ぶ機会(社内研修、外部講師招聘など)を設けることを義務付ける。
提言7:iDeCoと他の資産形成制度との連携強化
現状、NISAとiDeCoが併存しており、制度が複雑なうえに、制度間の連携が不十分となっている。
【具体策】
① iDeCoとNISAの連携を強化
・例えば、iDeCoに一定額以上拠出した場合、NISAの非課税投資枠を上乗せするなど、双方の活用を促すインセンティブを導入する。
これらを実現するには、各種法改正や税制改正、予算手当、システム対応、事務フローの大幅な変更などが必要となるため、国会や業界において長い時間をかけて議論を重ね、合意形成に努めることが求められる。現状の衆参ともに少数与党という不安定な政権下では、国会内で議論を始めることすら難しいのかもしれない。また、業界においても関係者が多岐に渡ることより、方向性を定めるのは容易ではないだろう。
だが、一つでも二つでも実現すれば、若年層や低所得者層の加入が促進し、国民全体の資産形成意識が高まることにより、個人の自助努力による資産形成が加速、公的年金制度の持続可能性への不安が軽減されるのではないかと期待している。