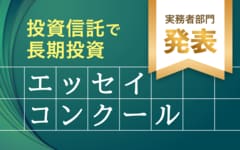金融庁の調べでは、同信組は遅くとも1992年ごろから、反社から度重なる不当な要求を受けて資金提供を行い、歴代理事長やコンプライアンス担当理事、監査部長らが直接的に主導して、繰り返し不正融資を実施していたといいます。この他に、実績稼ぎを狙って本来不要な金利負担を顧客に課す期またぎ融資、常務会議事録の改ざんなども発覚したとして、金融庁は同信組に対し業務改善命令と、1ヶ月間の一部業務停止命令を発出しました。
1990年代に反社への資金提供が始まり、2000年代に迂回融資、無断借名融資といった不正融資に手を染め、その不正融資の手法が反社への資金提供にも使われていたと金融庁はみています。同庁幹部は「不正行為の数々を長期間にわたり経営陣主導で実行し、かつ隠蔽してきたことは金融機関としてあるまじき事態だ。報告徴求命令に対する虚偽報告に関する告発も検討している」と話しています。
資本参加制度の申請期限「26年3月」迫る
一連の事案は、個別金融機関のスキャンダルにとどまらず、地域金融機関の経営を支援する法制度に関する議論にも影を落としています。
金融機関の経営基盤の強化を目的として公的資金を注入する資本参加制度は、来年3月に申請期限を迎えることになっています。期限を延長するには法改正の必要があり、足元、金融審議会の作業部会(地域金融力の強化に関するワーキンググループ)で具体策の議論が進められているところです。
ただ、いわき信組は資本参加制度の震災特例によって公的資金の注入を受けた金融機関のひとつ。このことが、制度延長論そのものに暗い影を落としているのです。
作業部会の会合である有識者は、「現在、地域金融サービスを担う既存の組織全てが(制度延長という)施策の対象に値するのか、大変気になる」と発言。「いわき信用組合の事例は例外であると思いたいが、ガバナンスはもちろん、経営手腕等にも大いに疑問がある事業者が存在する状況で、企業経営の品質を考慮せず制度の延長策の具体を議論するのは適当かどうかは考えるところがある」と述べました。
資本参加制度については、公的資金の注入前に、有識者で構成される専門審査会(金融機能強化審査会)の意見を聞くことになっていますが、この審査会の機能の強化を求める声も上がりました。
一連の不祥事をめぐっては、金融庁の限られたリソースで小規模の地域金融機関に監督・検査の目を光らせることの難しさも浮き彫りになりました。金融庁は一連の問題を受け、今事務年度から「協働組織金融モニタリング室」を設置。同時に新設した地域金融モニタリング参事官の指揮の下で、全国の信金信組などの財務データやリスク状況を調査・分析する体制を整えています。
金融庁幹部は「事案の発生を重く受け止め、組合自身の改善を指導し検証していくだけでなく、(金融庁の)体制強化を通じ、信用組合を含む協働組織金融機関に対する的確なモニタリングに取り組んでいきたい」と力をこめます。金融機関経営を支援する資本参加制度の延長は、政府が年内策定を目指す「地域金融力強化プラン」の根幹的な施策の一つとなるだけに、いわき信組の不祥事によって制度改正の議論に遅れが出ることを避けたいとの考えがうかがえます。