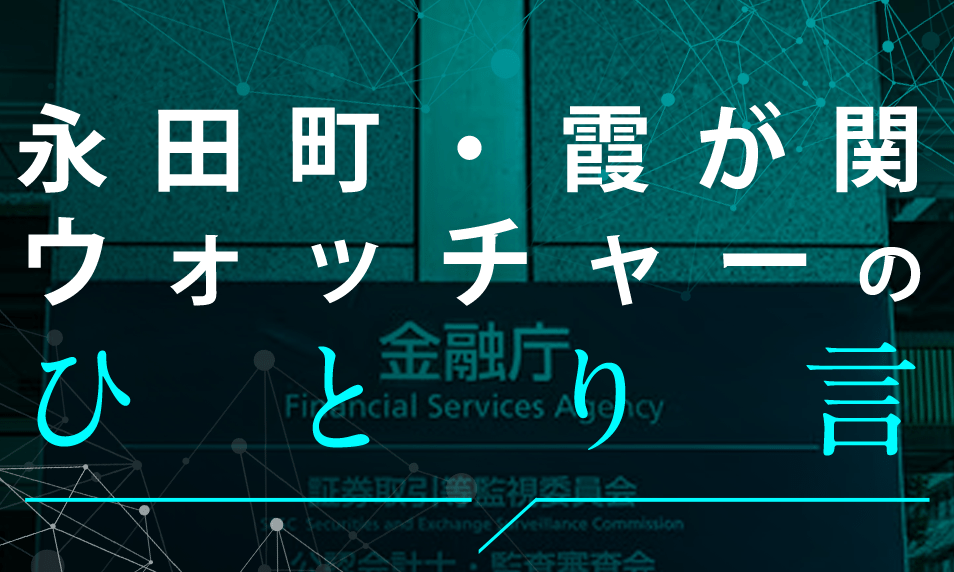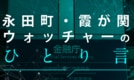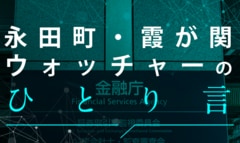2月12日、日本証券業協会が「新NISA開始1年後の利用動向に関する調査結果(速報版)」を公表した。2024年中に新NISAで金融商品を購入した人(7,610名)を対象に、購入・売却に係る金額や銘柄数、商品のほか、その理由及び損益などを調査した結果となっている。
調査対象者の属性を見ると、男女比率は6対4、平均年収は454万円(男性548万円、女性316万円)で、全体の4割が年収300万円未満となっている。また、金融資産保有額(現金・預貯金とリスク性金融商品の合計額)のウェイト平均は1,446万円(男性1,562万円、女性1,259万円)で、同保有額が300万円未満の割合は27.4%(男女でほぼ同じ)となる中、20代でもウェイト平均で男性が524万円、女性が450万円とまずまずの金融資産を保有している。また、「金融経済教育の経験あり」は23.0%となっており、2022年の金融広報中央委員会による金融リテラシー調査(18~79歳の個人3万人を対象)の「学校等において金融教育を受けた者」の割合7.1%の3倍強に達する。
これらより(今回の調査対象となった)新NISA利用者は、比較的金融リテラシーが高く、既に資産形成に取り組んでいる方々が多いことがうかがわれる。
いくつかの調査結果を踏まえ、筆者の感想を述べてみたい。
① つみたて投資枠の平均購入金額は47.3万円(男性52.0万円、女性40.7万円)で、投資上限額(120万円)をフル活用した者は15.3%。また、成長投資枠の平均購入金額は103.3万円(男性109.7万円、女性91.2万円)で、投資上限額(240万円)をフル活用した者は16.6%
両枠とも平均4割の利用率で、枠をフル活用した方が15%程度となっている。また、(枠併用のケースを考慮せず)単純計算すると、男女とも、つみたて投資枠は平均年収の10%前後、成長投資枠は平均的な金融資産保有額の7%程度を投資に回していることとなる。よって、枠の設定額としては大きすぎず、小さすぎず、良い水準だと思われるほか、利用者もあまり無理のない範囲で投資している様子が見て取れる。
② つみたて投資枠では、購入銘柄数は1銘柄が32.5%と最多(平均購入銘柄数は2.5 銘柄)で、売却銘柄数は売却していない者が83.2%と最多(平均売却銘柄数は0.3銘柄)。一方、成長投資枠では、購入銘柄数は1銘柄が31.9%と最多(平均購入銘柄数は3.1 銘柄)で、売却銘柄数は売却していない者が75.3%と最多(平均売却銘柄数は0.6銘柄)
売却していない者が8割前後というのは、長期投資の観点から好ましい結果と言えよう。一方、詳細なデータを見て気になったのは、5銘柄以上購入している者がつみたて投資枠で約1割に及んでいる点だ。分散投資の観点から複数銘柄を保有することは悪い話ではないが、既に分散投資が図られている投資信託やETFを5銘柄以上保有するというのは効果的に見てどうだろうか。
そもそも銘柄が増えれば、それだけ購入後のモニタリングの手間が多くなる。また、例えば「オルカン(全世界株式)」と「S&P500(米国株式)」など、一見投資先が異なるように見えて、実は投資先の多くが重なる銘柄を保有する場合は、銘柄分散のメリットは限定的だろう。地域や原資産(株式、債券、不動産、オルタナティブなど)が異なる銘柄に分散投資する場合でも、相関度合いを確認しながら配分を適宜調整しないと分散効果を十分得られない可能性がある。
投資経験の浅い方は、シンプルな形から入ったほうが投資が長続きするように思われる。まずは1~3銘柄にて基本的な知識や経験を習得し、投資額が相応の水準になってきたら、適切なポートフォリオ構築に向けて、銘柄数を増やす、あるいは銘柄の入れ替えを行う等といったことを検討していけば良いのではないか。
③ 新NISAを始めた動機・目的は、両枠とも「将来・老後の生活資金」が50%台でトップ、次いで「資産形成自体が目的」(40%台)が続く。「特に動機・目的はない」も10%台の回答。
気になるのは「資産形成自体が目的」や「特に動機・目的はない」との回答が目立つ点だ。常にゴールベースアプローチであるべきと主張するつもりはないが、「どのような性質の資金を、いつまでに、どの程度の額を目指すか」といったゴールが見えないと戦略の立てようがないし、心の構え方もわからないだろう。投資家がゲーム感覚でやみくもに、時に荒れ狂う市場に臨むとすれば、損失を被る局面に出会うと簡単にギブアップするのではないか。もし、顧客に長期投資を望むのであれば、「ゴールを持ちましょう」とアドバイスするのが我々業界人の務めかと思う。
このほか、調査結果では所々に「金融経済教育の経験別」のデータを示し、経験者の方が投資に対するスタンスが優れており、良い成果(損益)を得ているといった旨のコメントがなされている。例えば、つみたて投資枠での購入銘柄の理由として、「金融経済教育の経験ありの者は、『ポートフォリオ(保有銘柄)の多様化のため』が25.5%と、経験なしの者の17.7%を大きく上回っており、金融経済教育を受けた経験が分散投資の促進に寄与している可能性があると考えられる。
また、経験ありの者は、購入理由の多くの項目において、経験なしの者よりも購入理由を回答した割合が高い傾向にあるため、金融経済教育を受けた経験に基づき投資判断を行っている可能性があると考えられる」などと分析し、結果として「金融経済教育の経験ありの者は、経験なしの者よりも、新NISAの損益がプラスである者の割合が高く(つみたて投資枠で88.5%対81.1%、成長投資枠で78.1%対67.5%)、金融経済教育を受けた経験の有無が損益に寄与している可能性があると考えられる」としている。
日証協としては、「可能性がある」と慎重な言い回しをしつつも金融経済教育の必要性・有益性を強調したいのだろう。想いは良くわかるが、「過去1年間の損益だけを示して、『ほらっ、経験ありと無しとではこんなに結果が違うでしょ!』と言われてもねえ…」と感じる読者もいらっしゃるのではないだろうか。こうした懸念を払しょくするためにも、より長期のデータを踏まえて、改めて評価するべきかと思う。