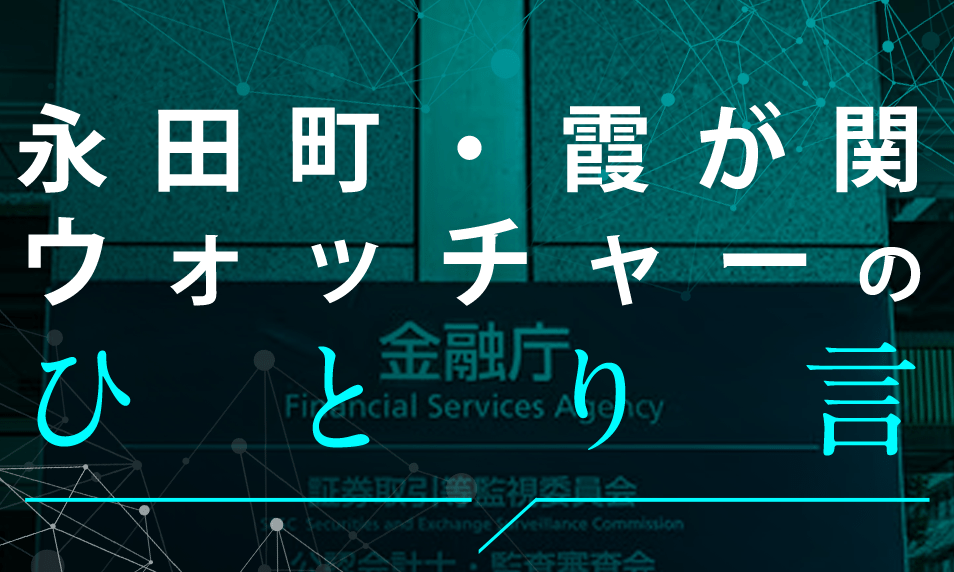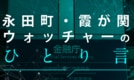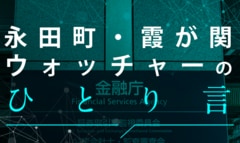テレビ番組は「労働」と「節約」しか念頭にない?
先日、平日夜のゴールデンタイムのテレビ番組で、老後資金の必要額について複数の専門家が最新データを使って試算した結果を紹介していた。2019年に金融審議会の「市場ワーキング・グループ」が公表した報告書をきっかけとした「老後2000万円問題」について、足元の社会情勢を踏まえて再検証するものであった。
同番組では「平均的な高齢夫婦が約30年間で必要な老後資金」は専門家の間で0円から4500万円まで分かれた。これには前提条件がある。0円というのは、「年金生活開始時点では0円でも構わない。なぜなら、高齢者が健康を維持し、年金を受給しながら仕事を続ければ、年金受給開始時点からその後の必要な資金を十分貯めることが出来るから」との意見だ。また、4500万円というのは、「完全リタイア層が年に数回国内旅行や海外旅行をするといったゆとりある老後生活を送る場合」を想定している。
なお、金融審議会の報告書では、2017年の総務省家計調査年報をベースに算出した場合に2000万円必要であるとされたが、同番組によると、2023年の最新データを使って同様の方法で計算すると、必要額は1400万円前後になるそうだ。ちなみにコロナ禍の2020年には外出制限などにより支出が抑えられたこともあり、必要額が55万円程度まで縮小したとのこと。要は、生活環境に大きく左右される数字であり、少なくとも単年度で議論すべき数値ではないということだろう。こうした中、番組では、「老後どのような生活を送るかで必要額は大きく変動する」と結論付けていた。
予想通りの結論であるが、番組で筆者が気になったのは、高齢者が必要な老後資金を確保するための方策として、健康維持を兼ね隙間時間を使ってアルバイトする、あるいは、手狭ながら割安な賃貸物件に住み替えるといった事例を紹介する中、NISA制度等を使った資産形成・資産運用の提案などが無かった点だ。昨年来、これだけ新NISA制度が話題となっても、番組制作者には、高齢者が投資による資産形成や資産運用を行うというイメージが無かったのだろうか。金融業界関係者としては残念に思う。
「運用の必要性を感じない」という人には、人生設計の話をしてみる
QUICK資産運用研究所が昨年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」では、「資産形成・資産運用の必要性を感じない」と答えた方々は12.6%、「どちらとも言えない」が26.5%となった。「必要性を感じない」との回答者にその理由を尋ねたところ、「そもそも資産形成について考えたことがない」との回答がトップ(31.1%)を占めている。これは、資産形成・資産運用の概念すら、いまだに国民の多くに浸透・定着していないことを示唆しており、番組制作者がこの話題をスルーしたとしても不思議ではないのかもしれない。
必要性を感じない理由の上位には、「節約すればいいと思うから」、「預貯金と公的年金で暮らしていけるから」といった回答も並んでいるのだが、資産形成に関心のない層も含め、もしも彼らが「これまで何とか平穏に暮らせてきた。これからもなんとかなるだろう」といった、あまり根拠のない自信を持っているとすれば危険だ。
なお、資産形成・資産運用の必要性を感じない理由として、「リスクを取りたくないから」、「面倒だから」といった回答も上位を占めている。こうした回答者に対しては、リスク分散の手法をわかりやすく説明する、取引手順を簡素化するといった対策を打てるだろうが、さて、「なんとかなるだろう」派に資産形成・資産運用に関心を持ってもらうにはどうすべきであろうか。
冒頭のテレビ番組では、専門家が老後の医療・介護費や住み家のリフォーム費用をどの程度見込むべきか示しつつ必要な老後資金を見積もっていたが、現役層であれば、さらに、住宅建設・購入資金や子供の教育資金、自家用車購入資金なども加えて支出額を見込んだうえで、給与や年金等の収入見込み額を予測し、それらがバランスするか確認作業を行って初めて「なんとかなりそうor足りなさそう」といった判断が下せるはずだ。
やはり、こうしたライフプランニングの必要性を唱えることから顧客にアプローチするのが王道だろう。まずは「あなたの夢は何ですか」、「あなたはどんな生活を望んでいますか」と問いかけ、「その実現のためにはどの程度資金が必要か、見込まれる収入額で賄えそうか、見てみましょう」と促す。この結果、「それでは、この程度は手元資金にも働いてもらいましょう」ということになれば、初めて具体的な資産形成・資産運用の提案を行う。人生100年時代と言われる中、例えば60代~70代の方々にも同様のアプローチは可能だろう。
このようなライフフプランニングが顧客にとって有益なものとなるか否かは、顧客情報をどこまで深掘りして聞き出せるかにかかっており、そのためには顧客との信頼関係の構築が要となる。先日ある会合で、「貯蓄から投資」の流れをさらに浸透させるためには何が必要か、金融庁幹部諸氏と意見を交わす機会があった。幹部の一人は、「新NISA制度により加速している流れが止まってしまうと、次はもう(ブームは)来ないとの思いでいる。金融機関の不祥事をきっかけに顧客が不信に陥りこの流れが止まってしまうことだけは絶対に避けたい」と強調していた。本人は当局やJPXのインサイダー取引疑惑も念頭にあったものと思う。そのうえで、「顧客の信頼を保ち続けるには顧客本位の徹底が必要だ」と結んでいた。あらためて、この言葉を肝に銘じた次第だ。