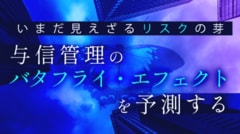議論を積み重ね
サービスやプロダクトで連携
―― 2022年10月7日に資本業務提携を締結しました。以後、どのような布石を打ってきたのでしょうか。
楠 当初の19.99%の出資受け入れの段階から、私たちは毎月、必ず集まって提携モデルに向けた議論を重ねて、オンラインの部分でのサービス連携をやっていくことになったし、プロダクト連携という路線も決めた。また、投資情報という面では、当社は情報提供能力に限界があったため、投資情報を提供してもらうことにもなった。プロダクトの領域は最初からかみ合いが良い。社債のディストリビューションや、TOBの復代理人を楽天証券に任せてもらっている。これらはリテール専業証券の当社ではこれまでできなかったが、みずほの全面的な協力を得て実現できるようになった。
プロダクト連携は、具体的な成果が早くから上がってきている。IPO、POも具体的な成果が出ている。2024年末までにECM(エクイティ・キャピタル・マーケッツ)関係で37件、DCM(デット・キャピタル・マーケッツ)関連で27件、TOB連携で6件という実績があがっている。
浜本 コンシューマーに近いウェルスマネジメントや資産運用の領域では、オンライン、リモート、対面という3つのチャネルのビジネスモデルは似ているようで全く違う。従って、カンパニーを分けたほうが良いのではないかと感じている。提携作業を通じて、チャネルの発想を変えなければいけないことをいよいよ確信できたが、それだけではない。
例えば、投資銀行ビジネスでは楽天証券の幅広いお客さまから資金を調達できるのは魅力的だ。また、発行体企業は個人株主を増やすことに関心が高く、個人投資家向けのIR活動に熱心だ。その点、リモートで数百人~数千人の個人投資家が参加する楽天主催のIRイベントは人気が高く、IRサポート連携は増加している。
2024年4月に合弁で事業開始したIFA法人「MiRaIウェルス・パートナーズ」は相談件数が1000件弱、預かり資産は50億円を超えた程度にすぎないが、確実に成果は上がっている。同社のアドバイザーは5人と実証実験レベルの態勢だが、しっかりとKPIを達成してくれば人員を投入していく。時間軸は言えないが、将来的には預かり資産1兆円は実現できる。
役割分担と協力分野を明確化
両社の相違がプラスに
楠 システムが絡む部分になると、お互いの標準というか、考え方の違いが如実に表れやすく、その調整に時間を要することもあり、当初のスケジュールより多少後ずれしているが、周辺的な分野はかなり整ってきたと考えている。
浜本 両社の考え方の違いが端的に表れたのがシステムに対する哲学で、価値観が激しくぶつかり合った。なにしろ、楽天証券はお客さまへのUI/UXの発想が前面に出るシステム様式である一方で、当社グループでは堅牢性を最大価値として、オンプレミス方式でウォーターフォール型のシステムを構築してきた。誤解を恐れずに言えば、この違いは水と油のようなものであり、リテール領域において、とりわけ際立っている。しかし、今後の展開を考えれば、マスに関しては、そこは共存よりも、むしろ楽天側のシステム発想に寄っていかなければならないと思う。当社も価値観を変えていかないと生き残れないという意識が着実に芽生えてきている。
楠 とはいえ、両社が非常に相違していることはプラスに働いている。なにしろ、ビジネス上のコンフリクトがない。お客さま層、チャネル、サービスの内容等々でも重複感がほとんどない。楽天証券は完全なリテール専業のオンライン証券だ。IFAビジネスをやっているが、このスタイルは総合証券とは全く異なり、当社はみずほ側にない部分を持っている。一方で、みずほは巨大であり、浜本さんが言ったように事業領域は広く、多様なファンクションがそろっている。
浜本 この3年ほど、私は「Right Channel,Right Access」という言葉を唱えて、役割をきちんと分担して、楽天証券側に担ってもらう部分は楽天証券側に任せるようにしている。当社にとって、それが経営資源の正しい配分にもなるし、顧客へのきちんとしたサービス提供につながっている。
顧客セグメント上、若手世代や預かり資産がまだ一定レベルに達していないような方々は、楽天側で対応してもらおうとしている。楽天証券側の方がUI/UXが優れているし、顧客は夜中でも土・日曜日でも利用できるからだ。それとは異なる顧客層、例えば、本当に対面方式でのアドバイスを求めている方々は当社が対応する。単なる運用ではなくて資産・事業の承継や不動産関連の相談や、投資銀行的な要素も含めた全てのコンサルティングのようなケースだ。属性的には富裕層や、企業オーナーなどであり、これらは対面方式でしっかりと関係を築く必要がある。
楠 従来、そうしたお客さまのすみ分け論のなかで抜け落ちていた資産階層がマスアフルエント層だ。金融資産数千万円という資産階層は、大手金融機関にとって大して儲からない層であり、せいぜいロングテールの態勢で対応するという感じにとどまっている一方で、オンライン証券はこの階層をサポートする機能が乏しい。従って、この資産階層は空白状態的になってきた。
しかし、これから成長が見込めるのはこの領域にほかならない。それなりの所得があって、おカネの蓄えもできて、しかもNISAで資産が積み上がってきている。そのような階層に対して、われわれはきちんと対応しなければいけないし、お互いに機能やアイデアを持ち寄って、新たなモデルを構築していくことができるはずだ。
―― 一方、連携における最大級の注目点は、両社間で顧客資金がどれだけスムーズに行き来できるのかという点でしょう。万全なセキュリティー体制の下でパスワード等の手続をどこまでなくしてシームレスにできるのかが問われています。
浜本 証券会社同士はそれほど資金の行き来は想定されないかもしれない。やはり、本丸は楽天証券とみずほ銀行との接続だ。そこで、われわれ2社の議論のなかにみずほ銀行も加わって、いまや、どちらかといえば、銀行連携がアジェンダの半分ほどを占めるようになっている。そこでの最大級の課題が接続方式にほかならない。
当初、時間軸が全く合わずに、その溝をいかに埋めるのかに労力を要したし、UI/UXについても、銀行はどうしても銀行発想に陥りがちになってしまう。今、みずほ銀行のインターネットバンキング「みずほダイレクト」も随分と仕様が変わってきたし、スピードも速くなっている。顧客のアプリ評価も改善している中で、楽天証券方式の発想を埋め込んでいくことでさらにその流れを加速させていきたいと考えている。
25年7月からはみずほダイレクトで楽天証券の預かり残高や損益を確認できるようになったし、楽天証券への入出金はすでに始まっている。いずれ、楽天証券が楽天銀行とやっているマネーブリッジのようなオートスイープをやれるようにする。これは必達の挑戦テーマだ。