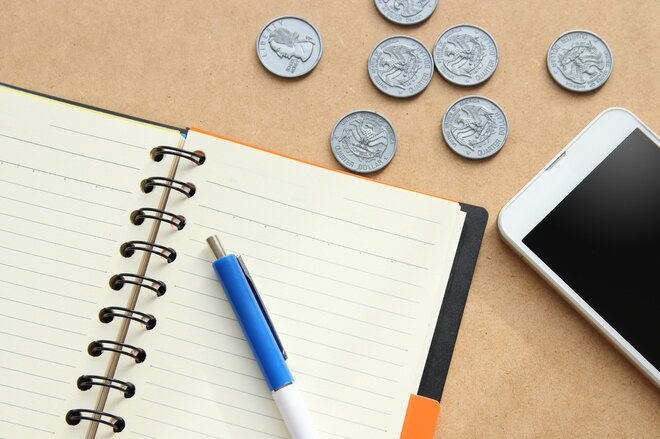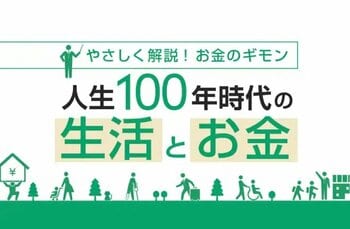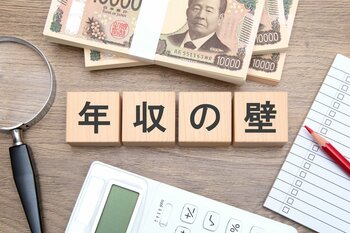これまで、日本におけるファイナンシャル・ウェルビーイング(Financial Well-being、以下FWB)を高める考え方や具体的な取り組みについて解説してきました。今回は海外の金融経済教育の取り組みとFWBの動向に目を向けてみます。
OECDの金融教育の取り組み
21世紀における金融経済教育の変遷を振り返ると、2008年のリーマン・ショックにより「個人家計の脆弱性」が明らかになったことが大きな転換点でした。リーマン・ショックを機に各国で個人家計のレジリエンス(頑丈さ、抵抗力)を高める観点で「金融リテラシーの重要性」が改めて認識されました。また、経済協力開発機構(OECD)において、2008年5月に金融経済教育に関する情報共有・分析を目的として「金融経済教育に関する国際ネットワーク(OECD/INFE)」が設立され、現在、約130ヵ国が加盟しています。OECD/INFEは、2012年4月に「個人のFWBを向上させるために必要な知識、態度、行動の総体が『金融リテラシー』である」と定義し、金融経済教育の指針として「金融教育のための国家戦略に関するハイレベル原則」を作成しました。同原則は同年6月のG20ロスカボス・サミットにて承認されています。
さらに新型コロナウイルス拡大によって、「個人家計の脆弱性」が再び強く認識されたことを受け、OECD/INFEは2022年6月に「Policy handbook on financial education in the workplace」(職場における金融教育の実施手引き)を公表しました。この中で、個人家計の「短期・長期の予期せぬ収入減への抵抗力」と「経済的な満足度(FWB)」を向上させる取り組みにおいて「職場は、家計の意思決定者を含む成人人口の大部分に金融教育を届けることができるうってつけのチャネルでもある」として、職場での金融教育の重要性が指摘されています。