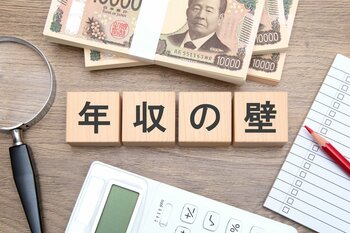2025年5月22日、米系の大手運用会社ティー・ロウ・プライス・ジャパンは、新ファンドに関するメディア向け勉強会を開催した。勉強会では今年の米国経済・株式市場の動向が説明された後、「S&P500 Pro」の新規設定に関する発表が行われた。
2025年米国経済・株式市場動向
米国経済・株式市場については、同社のポートフォリオ・スペシャリスト 永井基志氏がファンダメンタルズ分析調査に基づいた見通しを披露した。

政治と政策面では、「関税政策における直近の中国との直接交渉は、スコット・ベッセント財務長官が存在感を出して話を進めている。ベッセント氏の発言は非常にロジカルで現実目線なので比較的安心感を持って見ていける」「トランプ大統領については、年明け以降の一連の政策発動もあり、金融市場への関心という点が非常に懸念されていた。しかし、今回の関税発動を巡る一連の言動を見るにつけ、彼は金融市場のパフォーマンス動向に非常に注意を払っていることが改めて確認できた」と評価した。
米国企業の業績は直近の1-3月期決算がおおむね良好であったと説明。セクター別では、個人消費関連は好調、資本財・サービスセクターも「底打ちか回復局面に入っている」とした。例外として、トラックの運輸や鉄道などの物流セクターを挙げ、「コロナ禍で特殊な事態が発生した影響でキャパシティが追加された。その消化に時間がかかっている印象があり、少し回復が遅れ気味」との見解を示した。
AI需要に関連する設備投資は「今後減速すると予想されるが、関連銘柄の新規受注は依然として底堅い印象」と説明。米国経済全体を見通す上で注目するのはハードデータとソフトデータの乖離で、「売上や利益などのハードデータは健全に推移しているが、経営者の見通しや消費者心理などのソフトデータは下向きが続いている。今後数カ月でこれらの乖離がどう解消されるかに注視していく」と述べた。
米国株式市場の弱点と言われるバリュエーションの高さについては、「マグニフィセントセブンは確かに高いものの、収益性の高さと合わせて考えると納得できる」とした。さらに「S&P500構成銘柄の単純平均PER(株価収益率)は16.4倍と、欧州企業等と大差はない」とも強調した。
最後にAIと米国企業の労働生産性の関係について触れ、「2022年11月末にChatGPTが登場したことも一つの大きな契機となり、米国企業の労働生産性が再び加速し始めている。今年の下半期以降、AIを活用した事例やアプリケーションが続々と登場する。新しい技術は全世界に等しく普及するが、米国企業には新しいものをいち早く取り入れるカルチャーがある。米国企業の生産性改善は今後も続いていく可能性があり、ひいては米国の名目GDP成長、さらには米国企業のEPS(1株当たり純利益)の拡大につながっていくと考えている」と期待感を示した。
初のオンライン証券での取り扱いとなる「S&P500 Pro」
またこの日、同社から新たな公募投資信託「ティー・ロウ・プライス 米国株式リサーチファンド 愛称:S&P500 Pro」の設定も発表された。これは米国ティー・ロウ・プライスで1999年に運用開始した運用戦略「米国ストラクチャード・リサーチ株式戦略」を採用したファンドで、ポートフォリオ全体を30の業種セグメントに分け、専門のアナリストがS&P500の構成比率を参考に個別銘柄を選定する。保有銘柄数は約300で、S&P500と同程度のリスク特性とリターンパターンを示す。
指数をベースにしながら超過リターンを狙う投資手法は、「エンハンスト・インデックス運用」とも呼ばれている。インデックス運用とアクティブ運用のスタイルを組み合わせた手法で、欧米の年金基金や機関投資家の間では広く浸透している。
同ファンドは楽天証券での取り扱いが決まっている。投信営業部ヴァイスプレジデントの髙松浩二氏は「ティー・ロウ・プライスのファンドが初めてオンライン証券で買えること」「ファンドが用いる運用戦略について25年間に及ぶ実際の運用実績を示せること」が採用の背景にあったと語った。

投資に向いている人・向かない人
個人投資家の間では、アクティブファンドの手数料の高さに対するネガティブな意見が散見される。それに対し髙松氏は、「S&P500 Pro」では、プロによる綿密な銘柄分析・選択が当ファンドに付加価値を与えていると補足した。「既にS&P500を保有している投資家にとって、このファンドは、通常のスマートフォンと “Proモデル”のスマートフォンの関係に近い」と説明し、S&P500のコア戦略を補完する選択肢であることを示した。
徹底して低コストを追求する投資家にとっては、引き続きS&P500連動のインデックス投資が主流となるだろう。しかし、多少コストをかけてもよりパフォーマンスの良い運用を求める投資家にとっては、新たな選択肢となるかもしれない。ただし、アクティブファンドは必ずしも常に市場平均を上回るわけではない。短期間では、市場の変動やファンドの戦略が裏目に出る可能性もゼロではないため、短期的な上下動を重視する投資家にとっては注意が必要だ。
「パッシブとアクティブの二刀流」は投資家の選択肢となるか
勉強会終盤の質疑応答で、新商品の販路拡大について尋ねられると、髙松氏は「当面は楽天証券でしっかりプロモーションしていきたい」とした。また、経験の浅い投資家への訴求に関して、「個人投資家はメディア、あるいはインフルエンサーからの情報発信を見て投資判断をする方が多いため、今後、両方にアプローチしていく」と説明。ファンド名に「S&P500 Pro」と冠したことも、インデックスにプロの目利きを加えた運用商品として認知度向上の狙いがあるという。
楽天証券での取り扱い開始により、これまで対面販売を中心としていたティー・ロウ・プライスの商品が、初めてオンライン証券を通じて個人投資家に提供される。SNSや知名度の高い投資家を中心にインデックス投資の人気が高まる中、安定した超過収益の追求を目指す運用アプローチが、日本市場でどのように受け入れられるか注目される。