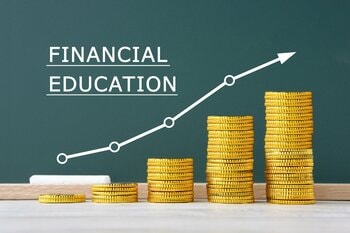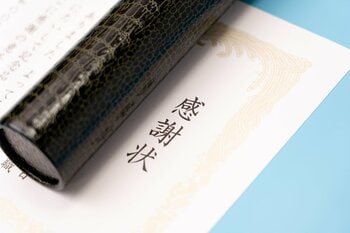「投信のパレット」の開発へ 鍵を握る存在となった新会社
では、FFGが目指した投信ビジネスの姿とはどのようなものだったのか。「長期投資を前提にすると、やはり『株式』というエンジンは欠かせないものの、それだけでは相場の上げ下げに耐えられず、離脱するお客さまも多くなってしまいます」と古澤氏は指摘する。商品面で顧客の離脱を防ぎ、長期投資を実現するためには、顧客の投資の目的やリスク許容度に応じて株式に債券をはじめとする他の資産を組み合わせて保有してもらう必要がある。
その手段となるのが投信で、分散投資を手軽に実現してくれる投信本来のメリットを活かしたうえで、さらに複数の商品の組み合わせで保有してもらう。もっとも、投信の数は多く、良しあしがあるので、それらを公平・中立的な視点で評価し、優れた投信で最適なポートフォリオを組むことさえできれば、顧客が望む長期の目標リターンを達成できるのではないか。それが新たなビジネスモデルの確立に向けて、FFGが立てた仮説だったという。
また、営業スタイルにおいて目指す新たなビジネスモデルは、「余裕資金による短期売買ではなく、お客さまのコアの資金にアプローチし、コア資産全体を長期で安定的に増やしてもらうことです」と古澤氏。「それにより、お客さまの生涯を通して関わることができるので、これこそが私たち地域金融機関にふさわしいビジネスだと考えていました」
もともと銀行の柱となってきた貸出業務は、長期にわたって利ざやを積み重ねていくため、いわばストックビジネス(継続的に売り上げが積み上がるビジネスモデル)だと言ってもいいだろう。投信ビジネスにおいても、入り口の販売手数料ではなく、顧客に寄り添いながら長期で得られる信託報酬を中心とするストックビジネスこそが、本来は銀行との親和性が高いはずだ。
この目指すべき姿を実現するには、まずは投資の考え方を社内で統一し浸透することが重要となるが、当時の米国ではすでにライフプランニングに基づくゴールベースアプローチが根付きつつあり、資産運用ビジネスの理想形の一つと言われていた。「もちろん、一気にそこを目指したいという気持ちもありましたが、短期目線の提案スタイルから一足飛びにビジネス転換するのはかなり難しいと考え、まずは多くの方に必要である長期の資産形成ニーズに真に貢献できるような投信ビジネスの確立を目指すことから始めました」(古澤氏)。
そして、いよいよ「投信のパレット」の開発がスタートするわけだが、目指す投信ビジネスの実現のためには、提案手法の確立が必要であり、提案のためのツールの開発が不可欠であった。「投信のパレット」の開発に当たって、鍵を握る存在となったのが新会社だ。それがR&Dビジネスファクトリー(R&D)であり、2018年8月の設立。古澤氏は同社の研究開発部長を兼務することとなり、現在も代表取締役を務めている。
とくに新たなシステムの開発では、外部パートナーとの協業に加え、行内の既存ビジネスを支える関係者との連携も必須となる。とはいえ、それを内部でこなそうとすると、「従来のやり方を変えたくないという意識も働くため、やはり外部の組織が必要でした」と古澤氏は説明する。しかも、スピード感を持って試行しながら改善する開発を目指していたため、それが従来の銀行組織では難しい面もあったわけだ。
投信調査センターとTACが新たなビジネスモデルを牽引
このR&Dによって開発された基幹システムが「F-navi+」であり、これをベースにした投信提案ナビゲーションシステムにより生み出されたものこそが「投信のパレット」である。さらに同社では調査専門組織の「投信調査センター」を新設。いわば自前の投信評価機関であり、対象となる約5000本の公募投信を中立、公平に診断する。「投信のパレット」ではこの投信調査センターが福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行にF-navi+を提供し、商品や人材に関するコンサルティングも行うスキームになっていて、そのためにR&Dは投資助言業のライセンスも取得している。
また、どんなに優れたツールであっても、実際の営業現場で使われなければ意味がない。使われるためには、営業店をサポートする人材も必要になるため、福岡銀行でもTAC(トップアセットコーディネーター)と呼ばれる本部所属の専門部隊を新たに立ち上げた。投信調査センターはこのTACの育成も担い、TACも同センターと連携しながら情報や知識、ツール利用スキルを含む営業スキルをアップデートし、自らも営業の最前線に立ちながら、そのノウハウを生かして営業店をサポートする。投信調査センターとTACは、まさに新たなビジネスモデルの牽引役であり、両輪となって「投信のパレット」を販売現場に浸透させていった。
ここで「投信のパレット」についてもう少し詳しく説明しておくと、まず基本となるのは、F-navi+の活用により、顧客の意向に沿った目標収益を目指すための最適な投信の組み合わせを提案できる機能。しかも資産形成だけではなく、「定額換金受取りサービス」による取り崩しも提案できる。
「投信のパレット」で提示するプランは、目標リターンごとの最適な資産配分の6コース。定量的な評価データとFFG独自の45分類に振り分けられた実在する投信をベースとしたオリジナルの指数を用いる。それは投信調査センターの評価を軸に選定された投信の組み合わせでもある。
さらにF-navi+には、ポートフォリオ提案にとどまらず、「FFG積立プラン」と呼ばれる顧客のリスク許容度やニーズに応じた積立のコースを提示できる機能もある。加えて、長期の国際分散投資がFFGとしての理想ではあるものの、タイミングに応じた短期売買を楽しみたいという顧客がいるのも事実であり、実績の高い投信を単一でも提案できる仕組みも備えている。
こうした顧客のニーズに応じたF-navi+による多彩な提案機能は、TACが実際に使用しながら改善を重ねることでさらに使い勝手が良くなっていく。投信調査センターによる集合研修、TACによるOJTなどを通して販売現場の提案レベルも向上していった。実際に、「成約率と単価の上昇、解約率の低下、さらには新規開拓の増加など、その効果は数字にも表れています」と古澤氏は強調する。