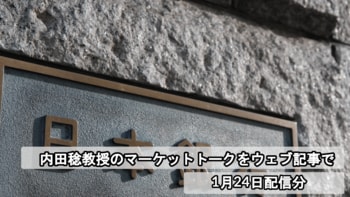家計部門が機関投資家に並ぶ存在に?
ちなみに本書執筆時点では4月分までの数字が明らかになっており、投信経由の対外証券投資は1〜4月期合計で+4兆2670億円に達している。これを商品別に見ると4兆665億円が株式・投資ファンド持分なので、やはり殆ど全てが海外株に流れていることが分かる。
通年統計で見た場合、2014年から2023年の10年平均が+3兆6111億円、パンデミック直前となる2015年から2019年の5年平均が+3兆6456億円という実績だった。つまり、2024年1〜4月期に記録した+4兆2670億円という数字はそれまでの年間買い越し額に匹敵するほどの大きさということである。仮にこのペースが続くと年間で約+13兆円程度という凄まじい仕上がりになる。
もちろん、2024年1〜4月期は新制度稼働直後ということもあり、ご祝儀的に成長投資枠の設定なども膨らんだ可能性がある。同じペースが続くと考えるのも、合理的ではないだろう。
とはいえ、これほどの動きを前提とすれば、投信経由の対外証券投資の水準が切り上がった可能性は十分考えられる。その上で、伝統的に為替市場で注目される機関投資家である年金(≒信託銀行における信託勘定)や証券会社(≒金融商品取引業社)そして生命保険会社などの取引も考慮する必要がある。
仮に「投信の買い」が年間10兆円以上のペースを維持し、年金や証券会社の買いも重なった場合、日本から海外への対外証券投資は極めて大きな規模に至る。
もちろん、新NISA稼働を受けた「投信の買い」については今後のデータを見ながら逐一評価を詰めていく必要があるため、本書で確たることを言うのはまだ早い。しかし、将来的に歴史を振り返った時、国策の追い風を受けて、機関投資家級の存在として個人投資家の存在が注目され始めたのが2024年だったという年になるのかもしれない。
元来、日本の個人投資家は為替市場で「ミセス・ワタナベ」と呼ばれ海外でもその存在感が認知されていたが、新NISAはそれを強化する装置になる可能性がある。
さらに言えば、新NISAを通じて買い付けされた外貨は長期投資を基本としているため、「戻って来ない円」として塩漬けされることが予見される。だとすれば、2011年頃から加速した日本企業の対外直接投資(≒製造拠点の海外移管)が円高抑止効果を持ったように、家計部門の運用行動が円の方向感を中長期的に縛る可能性は出てきている。
弱い円の正体 仮面の黒字国・日本
著者名 唐鎌 大輔
発行元 日経BP 日本経済新聞出版
価格 1,100円(税込)