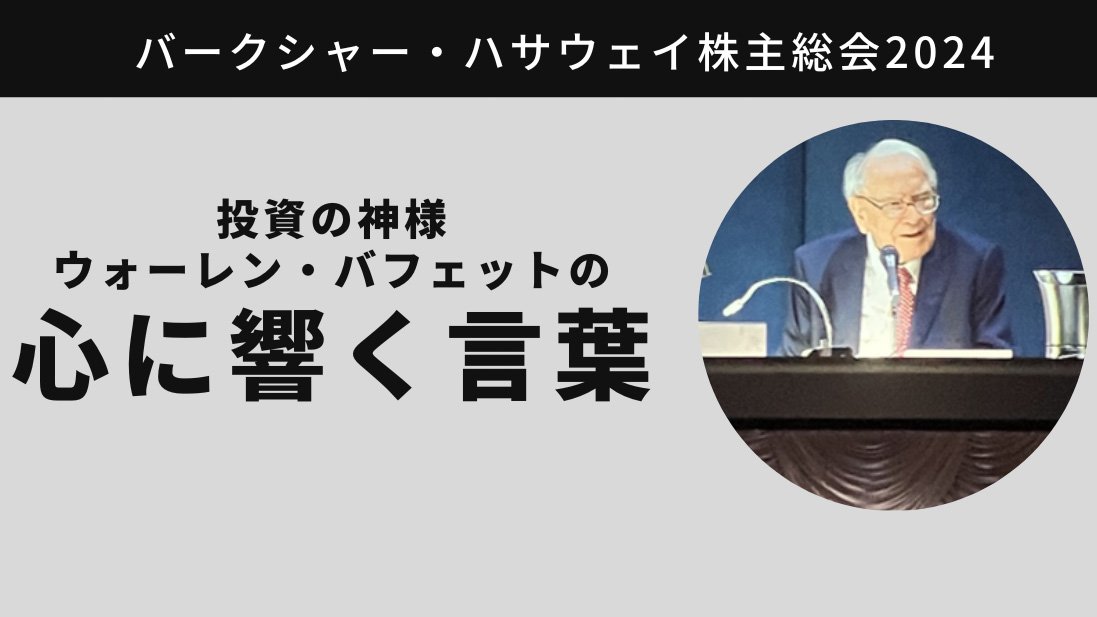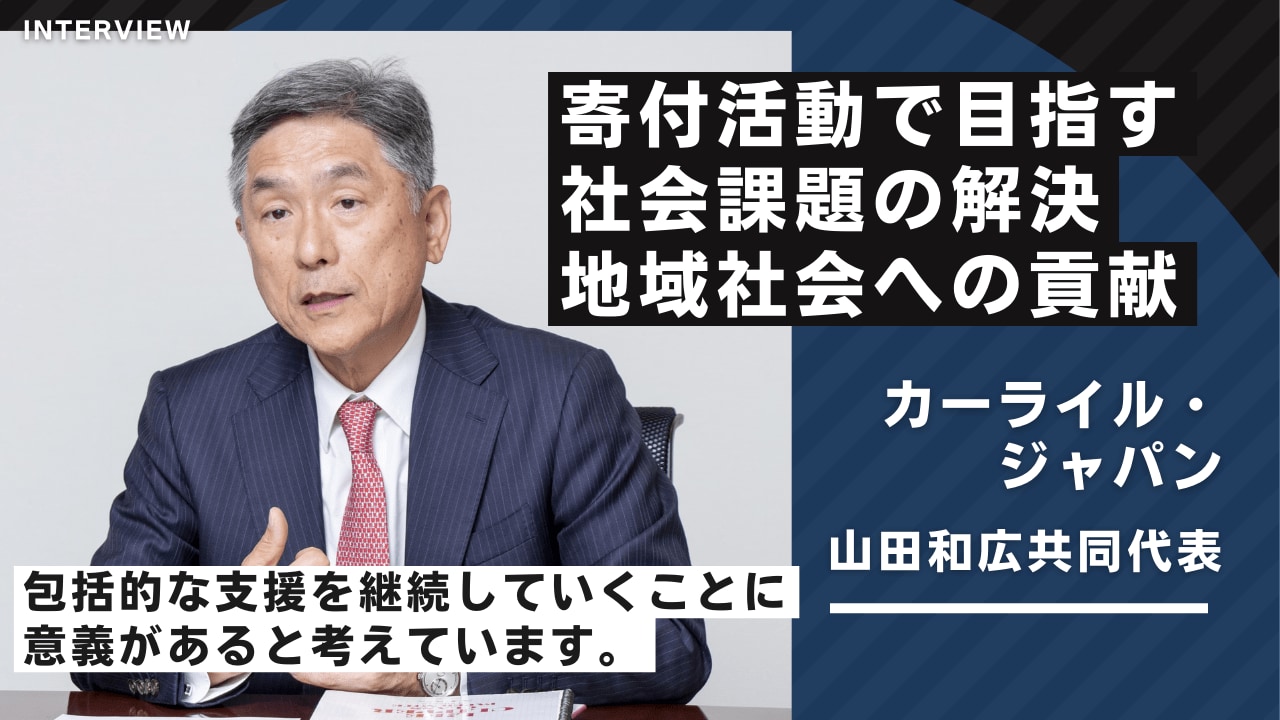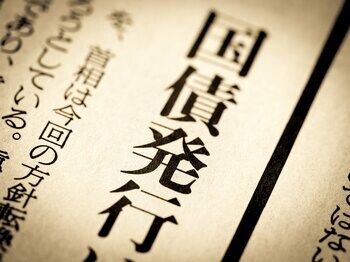返済義務の有無によって、取れるリスクが決定的に違う
返済義務がない資金と、40年という長期借入とはいえ2042年度以降、順次返済していく資金とでは、投資対象にも大きな違いが生じると思われます。つまり、返済が義務付けられているJSTの大学ファンドに比べ、寄付金を中心に運用する海外のエンダウメント・ファンドの方が、より高いリスクを取れるのではないかという点です。
実際、ポートフォリオの中身について見てみましょう。
まずJSTの大学ファンドですが、2022年度末時点のポートフォリオは以下のようになります。
・グローバル債券・・・54.6%
・グローバル株式・・・17.2%
・オルタナティブ・・・0.6%
・短期資産(預金等)・・・27.6%
一方、ハーバード大学の2021年6月末時点におけるポートフォリオは、
・未公開株式・・・34%
・ヘッジファンド・・・33%
・上場株式・・・14%
・短期資産・・・8%
・不動産・・・5%
・債券・・・4%
・天然資源・・・1%
・その他資産・・・1%
ついでにイェール大学の2020年6月期におけるポートフォリオは、
・ヘッジファンド・・・23.5%
・ベンチャーキャピタル・・・23.5%
・バイアウト・・・17.5%
・外国株式・・・11.75%
・不動産・・・9.5%
・債券/現金・・・7.5%
・エネルギー・・・4.5%
・米国国内株式・・・2.25%
となっています。
JSTの大学ファンドのポートフォリオが保守的であるのに対し、米国の2大学のポートフォリオは、かなり攻めているように見えます。
それはリターンの違いにも現れており、米国の2大学のリターンは概ね年10%台であるのに対し、JSTの大学ファンドが目指すリターンは、年4.38%としています。
各大学のポートフォリオは私たちの資産形成の参考にもなる!?
大学ファンドやエンダウメント・ファンドのポートフォリオを、個人がそのままマネるのは困難ですが、運用期間とリスクの取り方を考えるうえで、上記のポートフォリオは非常に示唆的です。40年でも十分に長期ですが、運用期間が切られると、どうしてもポートフォリオは保守的にならざるを得ませんし、その分だけ期待リターンは下がります。
資産運用は若いうちから始めた方が良いと言われるのは、運用期間を長く取れる分、リスクも積極的に取れ、かつ、より高いリターンの実現が期待できるからなのです。