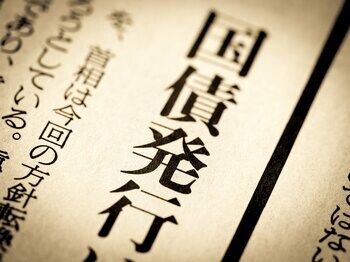日本にも「エウダウメント」はあるが、欧米とは“桁違い”の実態
JSTの大学ファンドは、前述したように政府出資ならびに財政投融資資金を原資にして運用されますが、他の大学も各々、卒業生などから集められた寄付金を運用して得た運用益を、学生の奨学金、研究資金などに充てています。
この寄付金を「エンダウメント」といい、米国や英国など海外の有名大学は相当程度の運用規模を持っています。寄付金は返済義務がありませんが、JSTの大学ファンドは大半が返済義務を負う資金であり、ここが大きな違いといっても良いでしょう。
具体的な運用資産の規模は、第一生命経済研究所のレポート「10兆円の大学ファンドが直面する課題と展望」にある数字で示してみましょう。
やや古い数字で、ハーバード、イェール、スタンフォードの各大学は2021会計年度末、オックスフォード大学は2022年12月末、慶應義塾大学、東京大学、京都大学は2021年度末の数字ですが、運用資産の規模は以下のようになります。
ハーバード大学・・・532億ドル(7兆9800億円)
イェール大学・・・423億ドル(6兆3450億円)
スタンフォード大学・・・378億ドル(5兆6700億円)
オックスフォード大学・・・58億ポンド(1兆1542億円)
慶應義塾大学・・・925億円
京都大学・・・527億円
東京大学・・・180億円
海外大学は外貨建てなので、日本との規模感を比較しやすいように、米ドルは1ドル=150円、英ポンドは1ポンド=199円で換算したものをカッコ内に入れておきます。
まるで桁違いです。
JSTの大学ファンドは、10兆円の運用資産から得られる運用益を複数の国際卓越研究大学で分け合うことになりますが、ハーバード大学などはJSTの10兆円とほぼ比肩する約8兆円の運用資産を持ち、そこからの運用益はすべてハーバード大学の経営基盤強化や学生支援、教育研究の充実などに使うことができます。しかも、ベースは卒業生からの寄付金ですから、返済義務がありません。