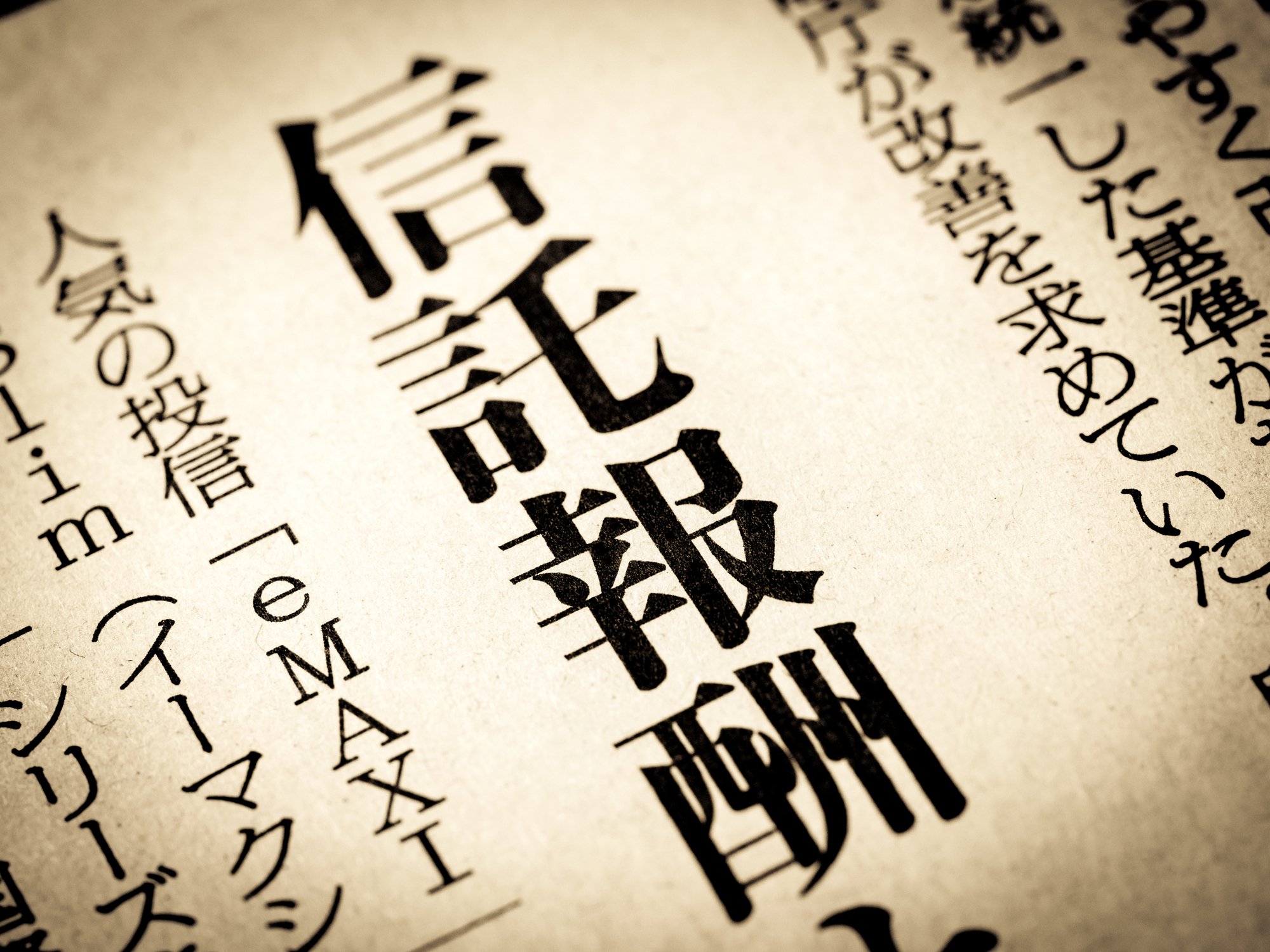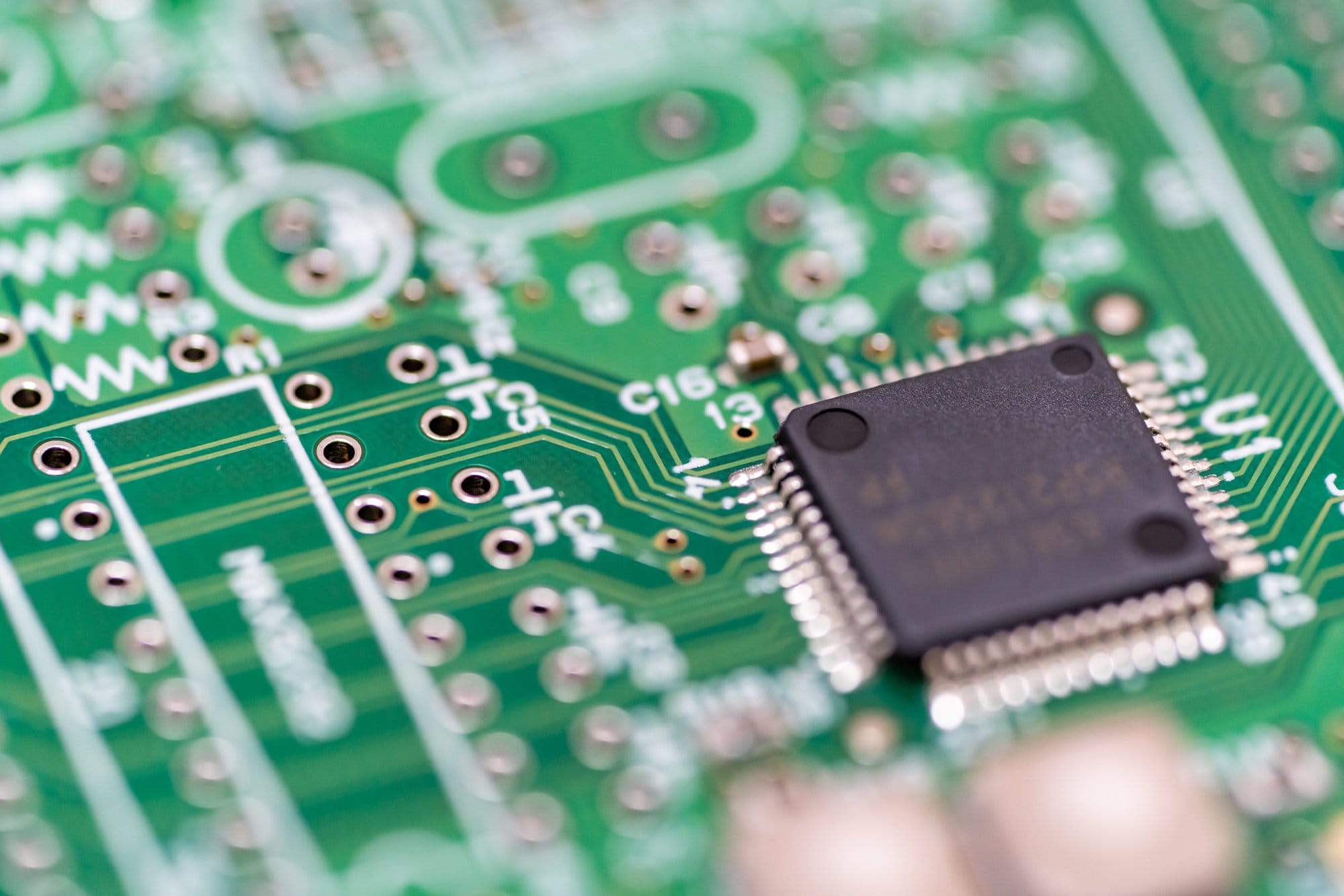“Slim”のありなしで何が変わる? 「eMAXIS」と「eMAXIS Slim」の成績比較から見えること
インデックスファンドの商品的な付加価値がどこにあるのかというと、それは連動目標とする指数に対して、どれだけ高い連動率を維持できるのか、という点です。
具体的な事例を挙げてみましょう。三菱UFJアセットマネジメントが設定・運用しているeMAXISシリーズです。最近では「オール・カントリー」が人気を集めていることで知られています。何しろ「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の信託報酬率は年0.05775%で(2024年5月17日時点)、業界最低水準です。ちなみに、同ファンドの運用がスタートした時点の信託報酬率は年0.120%で、純資産総額が増えるのに伴って、段階的に料率の引き下げが行われてきました。
ところでeMAXISシリーズには、他のタイプの「オール・カントリー」もあります。正式名称は「eMAXIS 全世界株式インデックス」です。
Slimが付いているのと、付いていないのとで、何が違うのでしょうか。
まず信託報酬率が違います。「eMAXIS Slim(オール・カントリー)」が年0.120%から段階的に引き下げられて、現在は年0.05775%であるのに対し、「eMAXIS(オール・カントリー)」のそれは年0.66%です(2024年5月17日時点)。
なぜ、このような差が生じるのかというと、販売形態が異なるからです。eMAXIS Slimがこれだけの低コストを実現できているのは、販売をオンライン取引に限定し、目論見書等の交付を店頭での手渡しや郵送ではなく、電子交付に限定するなどコスト削減を行っているからです。対してeMAXISはオンライン取引以外に、対面型の金融機関でも扱っています。つまり管理コストがかかる分だけ、「eMAXIS(オール・カントリー)」の方が、高めの信託報酬を徴収しているわけです。
かたや信託報酬が年0.66%、もう一方が年0.120%から段階的に引き下げられて年0.05775%。これだけ信託報酬が異なれば、運用成績にも差が生じるだろうと考えるのが普通です。
ところが、eMAXISとeMAXIS Slimのオール・カントリーで成績を比べるとどうなるでしょうか。eMAXIS Slimのオール・カントリーが設定された2018年10月31日時点の基準価額の推移を比較すると、信託報酬率が圧倒的に低いeMAXIS Slimと、eMAXISのオール・カントリーの成績差は、ほぼないに等しい結果となりました。
同日の基準価額を100として計算すると、eMAXISが2024年3月末時点で237.65。対してeMAXIS Slimは240.97でした。5年と5カ月の運用期間でわずか3.32の差は、あってないようなものでしょう。
これはある意味、正しいことです。両ファンドにとって大事なことは、連動目標である指数に対して高い連動率を保つことなので、両者の運用成績に差が開かないのは、インデックスファンドとして正しい付加価値を提供していることになります。
だとしたら、わざわざ低コストを全面に打ち出したマーケティングは無意味であると解釈できます。繰り返しになりますが、インデックスファンドにとって最大の付加価値は、連動目標である指数に対して高い連動率を保つことなのです。それが達成されているのであれば、極端な話、年率2%の信託報酬率でも問題ないはずです。
思うのですが、そもそも信託報酬率の低さが運用成績にとってプラスの効果をもたらすのは、インデックスファンドではなく、アクティブファンドで問われるべきなのではないでしょうか。
運用者の銘柄選択眼、トレーディング能力で多少劣後したとしても、運用コストが低ければ、その不利をある程度カバーできる。その意味において、運用コストの低さがメリットになると考えることはできます。
しかし、それをインデックスファンドにも当てはめてマーケティングを行っているところに、今の投資信託市場の不健全さがあるように思えます。