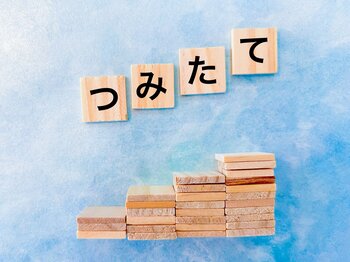ターゲットイヤーファンドは「60歳を迎える年」で選ぶ
運営管理機関として投資教育をするにあたって、運用商品の推奨はできませんが、ターゲットイヤーファンドであれば目標年が分かれば、自動的に買うべき投資信託が決まってきます。
たとえば、2030年に60歳を迎える人(1970年前後生まれ)は、2030年をターゲットイヤーとした投資信託が当てはまります。多くの場合、投資信託の名称の末尾に「2030」などと数字が付いているので、ご自身のターゲット年と合致するものを選ぶといった具合です。
企業型DCでは、ターゲットイヤーを10年刻みで組み入れているプランもあります。その場合は、保守的に考えるのであればターゲットイヤーが早い方を選び、逆にリスク性資産を多めに考えるのであればターゲットイヤーが遅い方を選ぶということになります。たとえば1985年生まれの人が保守的に考えるのであれば2040、リスク性資産を多めにするのであれば2050となります。
iDeCoでこそターゲットイヤーファンドの真価が発揮される?
ターゲットイヤーファンドはNISAのつみたて投資枠ではあまり見かけない投資信託です。
DCとNISAの大きな違いは、「途中で換金して使えるかどうか」です。
DCは原則として60歳までは引き出せないため、いったん加入したら運用が続きます。長期の運用であるという点がターゲットイヤーファンドを安心して保有し続けられることの素地ともいえます。
一方、企業型DCの場合、中途退職とともに資格喪失して投資信託をいったん売却ということも考えられます。
そのため、ターゲットイヤーファンドを活用するのであればiDeCoで使い、企業型DCではよりリスクの高い外国株式型やREITを選ぶ(逆にリスクを抑えるために元本確保型にする)といった利用方法もあるかもしれません。
企業型DCとiDeCoを併用しやすい環境が整いつつあります。iDeCoを選ぶ際に、ターゲットイヤーファンドの特徴から見てみるというのも一つの考え方かもしれません。