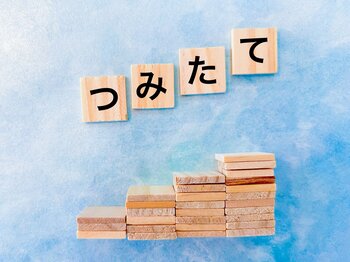米国401(k)加入者の68%が保有するほど普及
米国の確定拠出年金では、ターゲットデートファンド(=ターゲットイヤーファンドと同義)が普及しています。
米国では年金保護法が2006年に発効され、翌年には401(k)プランの「自動化」が可能になりました。自動化は従業員が「非加入」の意思表示をしない限り、加入者とする仕組みです。自動化以前は、401(k)を活用したい人だけが加入者だったため、運用商品の選択ができる人が中心でした。しかし「自動化」によって自ら運用商品を選べない人が増えることが想定されました。そのため多くのプランが、運用商品を選ばなかった場合に購入する運用商品(デフォルトファンド)として、ターゲットデートファンドを設定しました。
その結果、米国401(k)加入者の68%がターゲットデートファンドを保有し、401(k)全体の資産の38%がターゲットデートファンドとなっています(2022年末)(※2)。
また、英国では2008年の年金法により決まり、2012年より導入されたNEST(National Employment Savings Trust)でもターゲットイヤー型がデフォルトファンドに設定されています。
日本でも、2018年5月から「指定運用方法」が法定されました。最初の掛金拠出から一定期間経過した後に運用商品を選んでいなければ、規約で定めた運用商品を加入者本人が指定したとみなすことができる仕組みです。
企業型DCの指定運用方法は49%の規約で設定されており、そのうちの64%は元本確保型商品、残りの36%が投資信託になっています。しかし、近年、指定運用方法を投資信託に変更する規約も徐々に増えてきています(※3)。
なお、個人型DC(iDeCo)では、指定運用方法を選定しているプランの約8割において投資信託が指定運用方法として選定されており、うち6割はターゲットイヤーファンドとなっています。
※2 ICI米国投資信託協会「2025 INVESTMENT COMPANY FACT BOOK」
※3 金融庁「プログレスレポート2025」金融庁