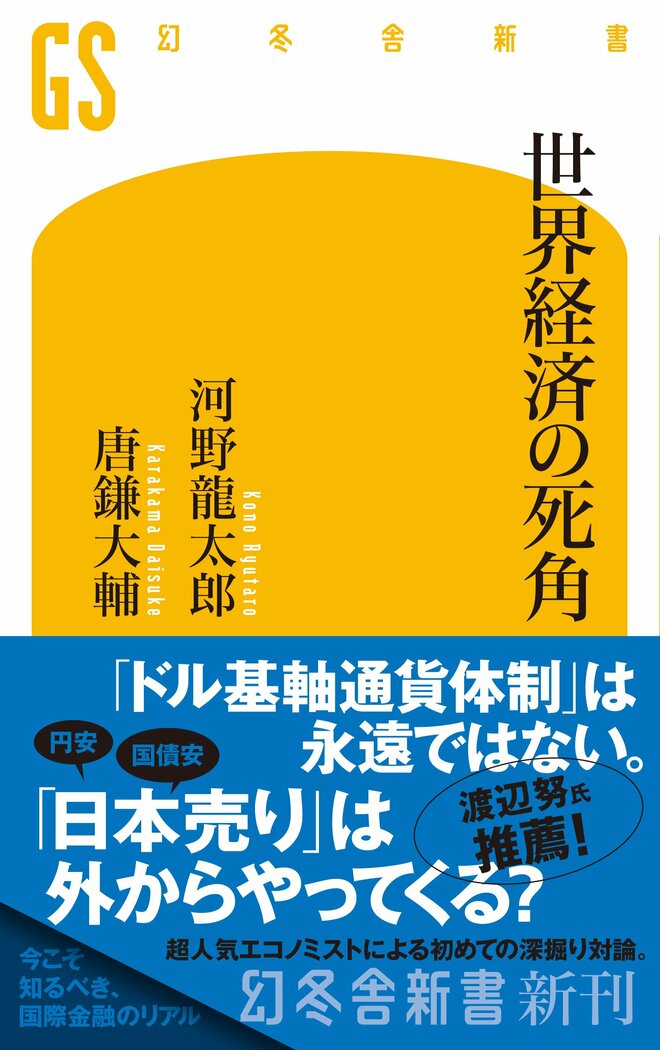唐鎌 なるほど。定昇の存在が危機感の醸成をある程度抑制していたわけですね。たしかに、定昇で「自分はそこそこ給料増えているし」ということで、問題意識を持たなくなっている人は多いかもしれませんね。
河野 このように、企業全体の賃金の総額が変わらなくても、社員一人ひとりの目線では新入社員のときに比べると賃金が上がっているので、「自分の生産性が上がり、それが賃金の増加に反映されている」と錯覚しやすくなります。
そのため、大企業経営者に「日本の実質賃金はまったく上がっていない」と話すと、多くは「あ、それはうちの話じゃありませんね」といった反応を見せます。特に、日本の場合は、経営者自身、叩き上げが多く、長期雇用制の下で定期昇給を経験しているので、「実質賃金が上がらないのは、生産性の低い中小企業の問題」という思い込みを抱きやすいのだと思います。
唐鎌 それはあるでしょうね。なんせ自分は「25年間で1・7倍」になっているわけですから、「自分は違う」と思うでしょう。
河野 あるいは近年、企業統治改革(コーポレートガバナンス改革)の効果もあって、経営陣には株価連動型報酬が導入されているので、大企業経営者自身の報酬はかなり上がっています。そのことも、賃金がしっかり上がっているという思い込みに影響しているかもしれませんね。
企業が蓄えている「利益剰余金(いわゆる内部留保)」は、1998年には約130兆円でしたが、アベノミクスが始まった2013年には300兆円に達して、我々エコノミストは当時大騒ぎしていました。そして2023年には、ついに600兆円まで積み上がっています(図表1-3)。
人件費はほとんど横ばいのままなのに、利益剰余金は四半世紀で、なんと5倍弱です。
1990年代末から2022年頃までの間、ベアがほとんど行われなかったことを考えると、企業が基本給を抑えることで利益を蓄え、自己資本の強化に回していたということです。
これにより日本企業は経営の安定性を高め、メインバンクが不在でも、長期雇用制度の維持を可能にしていたのです。ただ、それにしてもため込みすぎだとは思いますが。
世界経済の死角
著者名 河野龍太郎/唐鎌大輔
発行元 幻冬舎新書
価格 1320円(税込)