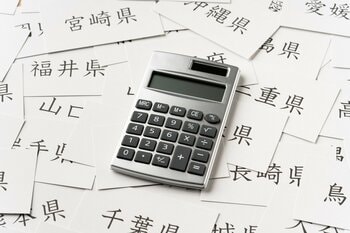――フォーラムの活動内容について伺います。2025年度に実施されている4つの分科会(オルタナティブ投資、企業価値向上、DX・デジタル化、サステナブルファイナンス)では、どのような議論をしていますか。
4つの分科会こそが資産運用フォーラムの中心的な活動の場であり、2カ月ごとに定期的に会合が開催され、テーマごとに深掘りした議論が活発に行われています。
例えばDX・デジタル化の分科会では、「生成AI」などの新しいテクノロジー分野がホットなテーマです。資産運用の現場にこうした技術をどう取り入れるかが、非常に大きな関心事となっています。
中でも重要な論点の一つが「データ」です。生成AIの活用には、質の高い、正確で多様なデータが不可欠です。業界としても、こうした認識を共有しながら、具体的にどのようにデータを運用に生かしていくかが議論されています。
これまでアナリストが行っていた企業の決算資料の読み込みや要約といった作業も、今ではAIによって自動化されつつあり、テクノロジーによってどのように生産性を高めていくかが、大きなテーマです。
また、電子取引も進化しています。かつては音声でやりとりしていた取引が、今ではほとんど自動化され、画面上で完結するようになった金融資産も多くみられるようになりました。電子取引には人為的なミスの削減、取引のスピード向上、コンプライアンス強化など、さまざまなメリットあり、それらをより多くの皆さまが享受できるための議論が活発に行われています。
こうしたデジタル化の進展は、発行体の企業価値向上にもつながります。配当や持ち合い株の管理の透明性が高まるなど、資産運用の信頼性や効率性を高める取り組みとして重要です。特に日本では労働人口が減少する中で、テクノロジーの活用は不可避の課題となっています。
――サステナブルファイナンスについては、トランプ米政権の方針を受けて後退の動きも見られます。そうした中でも、日本の資産運用フォーラムとしては、分科会のテーマとして取り組まれていくということでしょうか。
そのとおりです。確かに、世界ではさまざまな政治的な動きがありますが、そうしたことに左右されることなく、持続可能な金融の枠組みを着実に提供し続けていくべきだと考えています。
脱炭素や持続可能な社会の実現に向けて、日本政府も高い目標を掲げており、日本がリーダーシップを発揮できる分野でもあると思います。分科会では、参加者の皆さまが、目標達成に向けてどのようなステップを踏んでいくべきか、市場関係者とともに議論を重ねています。
――オルタナティブ投資の分科会もありますね。過去20年で日本のアセットオーナーが海外のオルタナティブ資産に投資する流れは進んできましたが、日本国内での外資系PEファンドの活動は、欧米と比べると成熟途上です。分科会では、主にどのような方向性に注目が集まっているのでしょうか?
日本のプライベートマーケットやオルタナティブ投資の市場については、ご指摘の通りだと思います。ただし、それは裏を返せば、日本にはこれから成長できる余地や、新たに発掘されるべき投資機会が多く残されているということでもあります。
そうしたポジティブな視点で、日本市場に新たな可能性を見出そうという雰囲気が、今、着実に広がっています。PE以外にも、多様なオルタナティブ資産の分野で、より深みのある議論が始まっています。
日本はGDP規模でも世界トップクラスであり、投資対象としての潜在力は非常に高いと見られています。分科会では、海外からの資金誘致、日本のアセットオーナーによる国内投資・海外投資のバランス、その両面について活発な議論が行われています。
重要なのは、それが一方通行ではなく、双方向の相互作用としてマーケットが発展していくという点です。オルタナティブ投資の分野も含めて、総合的かつ持続的に成長していけるようなエコシステムを築いていくことが、フォーラムと分科会の目指すところです。
分科会の4つのテーマはいずれも、現在の資産運用業界が直面している重要な変革と深く結びついています。各分科会の議論の成果は、ステートメント(声明文)という形で発表する予定です。
日本の資産運用市場は非常に成熟しており、何かが一夜にして変わるというような性質のものではありません。ただし、参加企業が増え、建設的な議論が行われるようになってきた今の流れは、非常にポジティブな兆候だと捉えています。歴史ある大きな市場であるからこそ、さまざまな分野の変革は慎重かつ段階的に進めていくべきだと考えています。