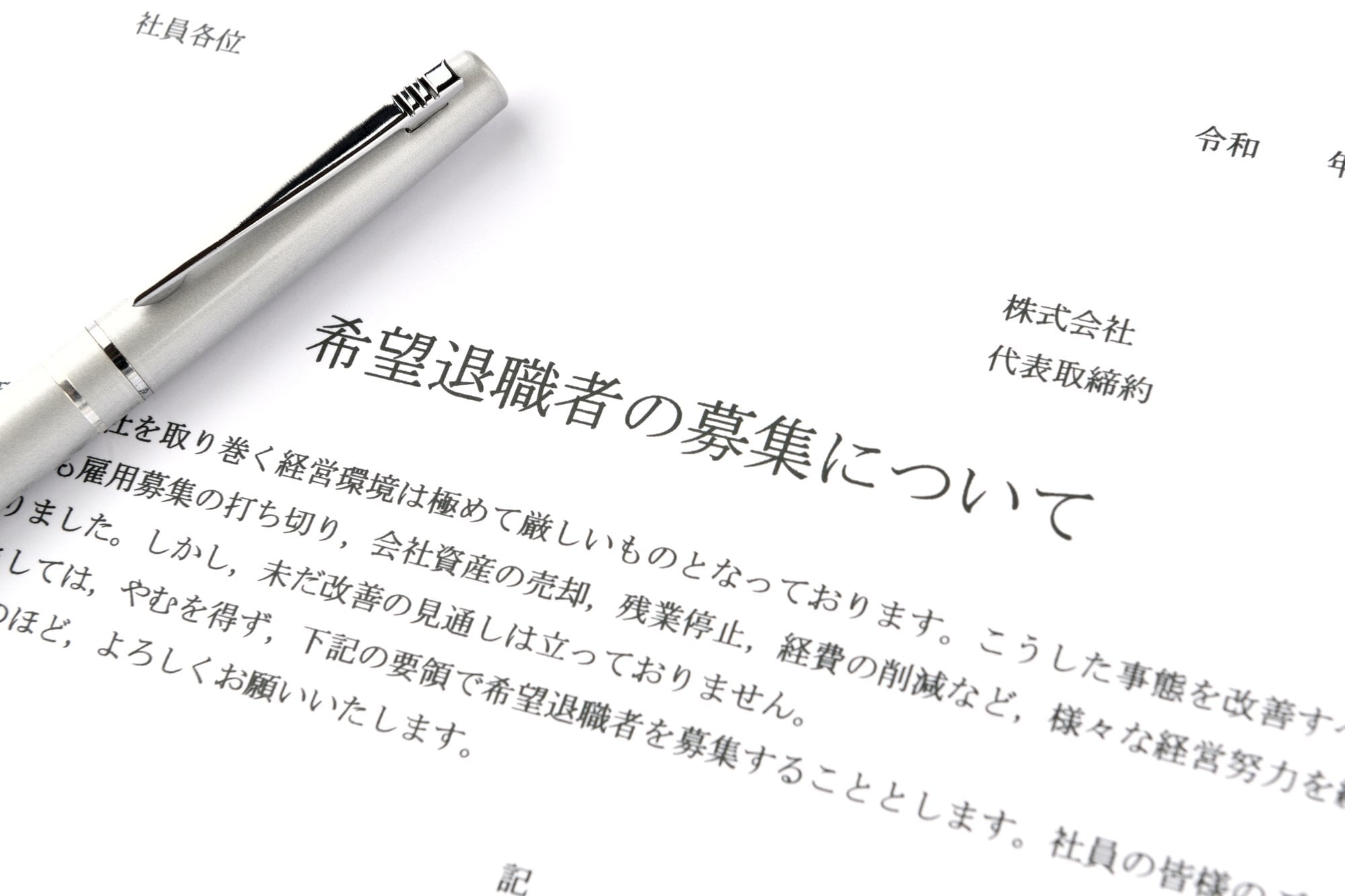取締役、監査役、監査法人のいずれもが、その機能を全く果たしていなかった…
それにしても、上場企業でありながら、なぜガバナンスが効かなかったのでしょうか。
この絵図を描いた首謀者は創業者ですが、創業者が社長だった時代のCFOはモルガン・スタンレー出身者です。2022年に取締役CFOに就任した時点で、すでにオルツは架空取引を行っている真最中でした。何も知らずにCFOを勤め続けたとはとても思えません。
オルツの出資者であるベンチャーキャピタル、ジャフコ出身の社外取締役は、報告書によると、「事業執行面への関わりはなく、専ら取締役会の場において社外の立場から助言や監督を行っていたことが窺われる。そのため、AI GIJIROKUに関する個別具体的な取引やスキーム等の策定や意思決定に関与しておらず」、したがって何も悪いことはしていませんよ、ということなのでしょうが、これでは社外取締役としての役割を果たしていないのも同然です。
監査役も「AI GIJIROKUに関する個別具体的な取引やスキーム等の策定や意思決定に関与しておらず」ということで、循環取引には関与していないとしていますが、前監査法人から循環取引の疑義があることを指摘されたにもかかわらず、それについて自ら詳しく調べることなく、後任の監査法人であるシドーからの監査報告を受けて、循環取引の疑義は解消されたものと認識していたというのですから、何をか言わんや、としか言いようがありません。
そして、2022年9月から監査法人を前任の監査法人より引き継いだシドーは、引き継ぎの際に循環取引という不正の疑いがあることを認識していたにもかかわらず、決算数字に疑念を抱くことなく監査を通していました。
つまり経営者の監視役になるべき取締役、監査役、監査法人のいずれもが、その機能を全く果たしていなかったことになります。
一個人が不正を見抜くのは難しいものの、まずは「監査法人」に注目!?
おそらく、この手の不正を一個人が見抜くのは、非常に難しいでしょう。
ただ、監査法人は大手と称される4社が、監査業務収入の約8割を占めると言われています。
ある会計士によると、「上場企業クラスで大手、準大手以外の監査法人を使っているところは要注意」だそうで、これはひとつヒントになるように思えます。