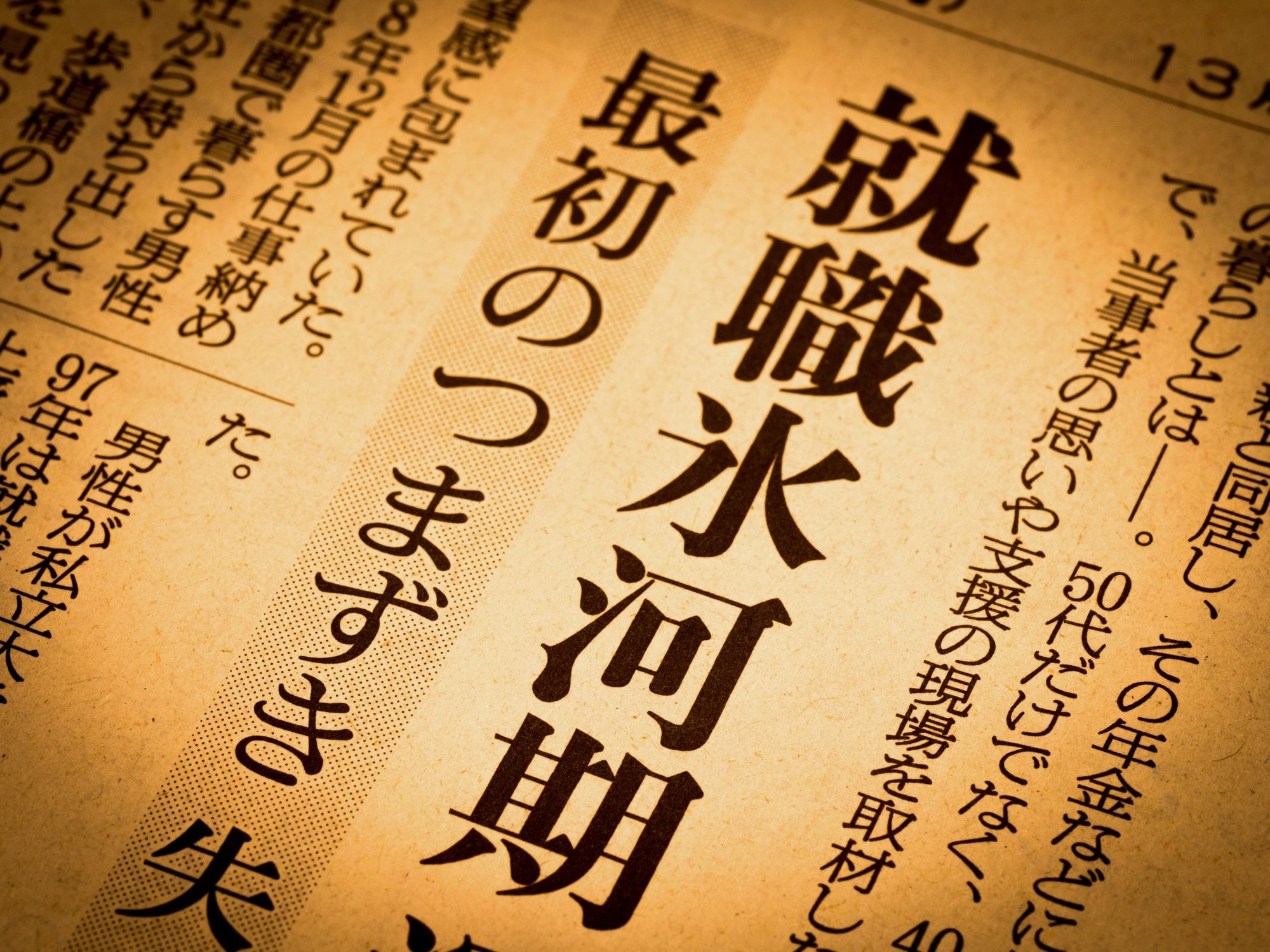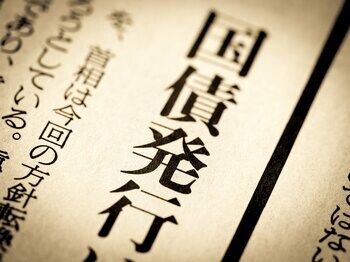日々の暮らしに関わる喫緊の争点は「物価高対策、コメ価格高騰、消費税」
前出の17にわたる争点のうち、私たちの生活に直接関わってくる喫緊のものとしては、物価高対策、コメ価格高騰、消費税でしょう。
以下、NHKがまとめた各党の政策を見ていきたいと思います。
まず、現時点で与党を形成している自民党・公明党の政策を紹介すると、自民党が「賃上げ環境の整備」であり、公明党が「全世帯への支援」でした。
しかし、もし参議院選挙で与党が過半数割れになると、これらの政策よりも野党の言い分が通りやすくなる可能性が出てきます。その野党が、物価高対策で何を主張しているのかというと「減税」です。
目下、野党で減税を物価対策として主張しているのは、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、れいわ新選組、参政党、日本保守党、社民党、みんなでつくる党、NHK党の8党です。なかでも消費税については、「食料品の消費税をゼロ%にする」という政策を掲げているのが立憲民主党、日本維新の会、社民党であり、消費税廃止を唱えているのがれいわ新選組、消費税の恒久的な5%引き下げを唱えているのがNHK党です。
次にコメ対策です。コメの価格高騰が昨今の社会問題化したこともあり、当然のことながら今回の参議院選挙でも、争点のひとつになるわけですが、「農家の所得を補償する制度の導入」と答えたのが国民民主党、共産党、れいわ新選組、参政党、社民党の5党でした。正直、この手の所得補償の類は、コメ問題の根本的な解決にはつながらないと考えられます。
その点では、「流通経路の改善」と答えた日本維新の会、日本保守党、みんなでつくる党、NHK党、再生の道、チームみらいは、JAの在り方を再考するという意味合いが含まれるのであれば、所得補償よりははるかにマシです。
これは以前、ある若い生産者に聞いた話ですが、そら豆を作ってJAに出荷したところ、買取価格が安いうえに、手数料として20%を差し引かれたということです。20%の手数料率が高いかどうかはともかくとして、この手数料がJA職員などの給料に反映されているのは事実でしょう。JA全中の調べでは、2023年度時点のJA職員数は14万人とされており、2018年度に比べて約1割減少しているということですが、上場されておらず、ガバナンスも効きにくい組織だけに、14万人という職員数が適正なのかどうか、生産性向上の努力がどこまで行われているのか、といったことが外部からは全く見えません。
流通経路の中心となるJA組織の抜本的な見直しによって、農家が儲かる商売になるのかどうかは、今後、若手生産者を増やすうえでも重要であり、安易な所得補償よりも評価できます。
ちなみに、自民党は「生産・流通・備蓄の各段階で在庫と流通量を検証し、需給動向を把握して機動的に対応する」ということですが、JA改革に踏み込まないあたり、自民党とJAとの関係による忖度が感じられます。
日米関税交渉の結果によっては日本経済への悪影響も…?
少しマクロな争点についても見ておきましょう。先日、日本からの輸入品に対して25%の関税を課すと、一方的に通告してきた米国との間で、これから大きな争点になる「日米関税交渉」ですが、与党である自民党、公明党ともにこれまでの政府の対応を評価しており、なかでも共通するのは「中小企業に対する支援体制を整えている」という点でした。
しかし25%という数字は、4月に発表された日本への相互関税の24%を上回る水準であり、その影響は実施される予定の8月1日以降にならないと見えてきません。一応、8月1日までは交渉の余地があるということで、日本の政府関係者は粘り強く交渉を続けていく方針を打ち出していますが、石破首相の強硬的な姿勢では話し合いが平行線をたどる可能性が高く、今年度後半にかけての日本経済への悪影響が懸念されるところです。