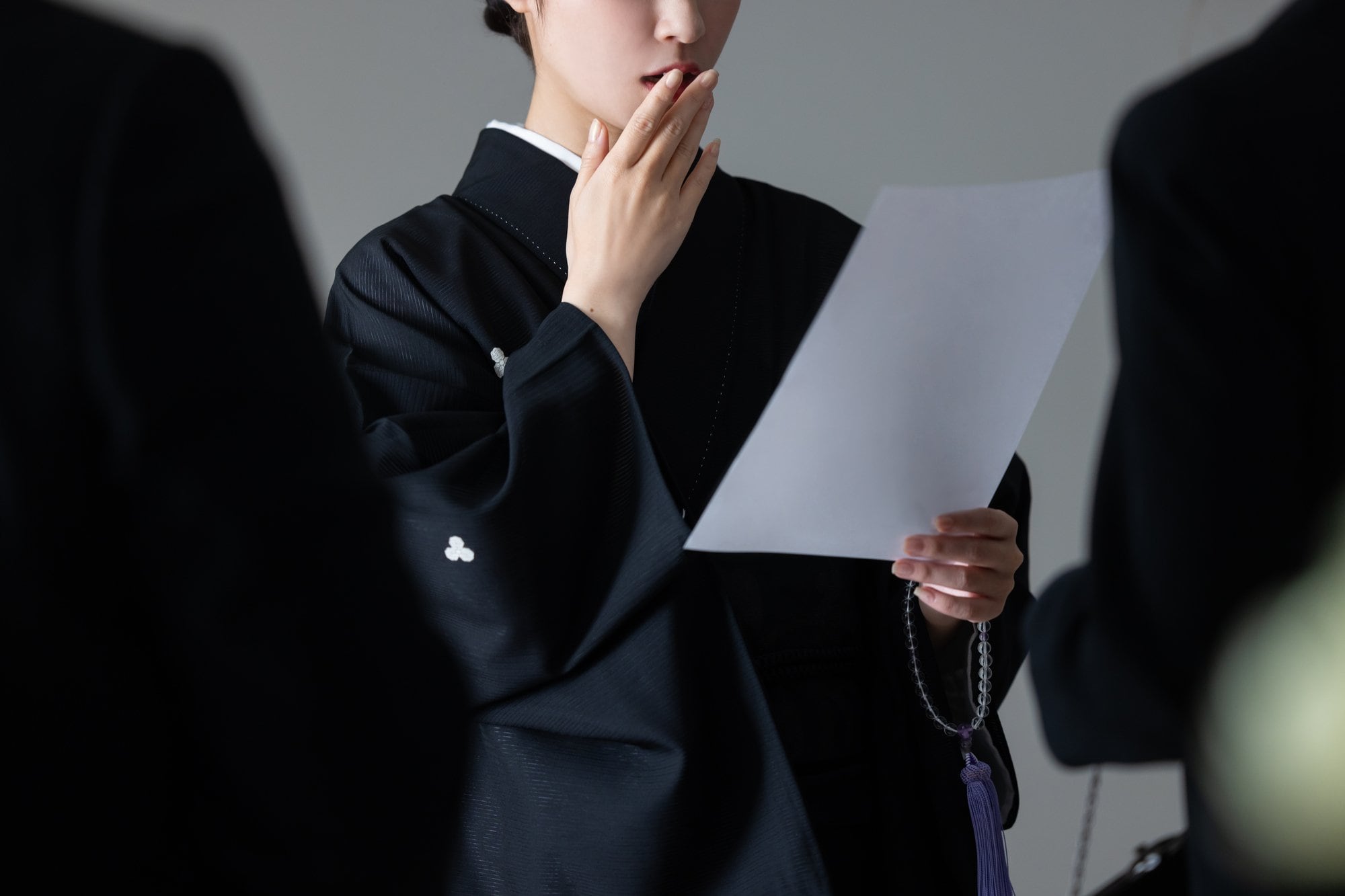取り戻した二人の日々
翌日から、2人の生活は再び大きく変わっていった。
拓郎は日々の撮影の仕事に加えて、以前のスタジオ時代の知り合いに頼み込んでアルバイトを増やした。少しでもお金になるならと、小さな仕事でも断らずに受け、これまで苦手だからと取りくんでこなかったSNSアカウントも使って、営業活動を行った。
一方で、悠里もまた罪悪感に押しつぶされそうになりながらも、できる限りの努力をしていた。今までの派手な付き合いを全て切り、地道に会社での業務に集中した。だが、彼女の心の中に積もった重い感情は、日を追うごとに彼女の表情から輝きを奪っていった。
「なあ、悠里。ちょっと長めの休みを取ろうと思うんだ」
日に日に疲弊していく悠里を見ていられなくなった拓郎はある夜、ふと思いついたように提案した。とはいえ、本当は前々からスケジュールを調整し、まとまった休みが取れるように時間を作っていたのだが。
「どうして急に?」
「お前を連れて、のんびり風景でも撮りに行きたいと思ってな」
拓郎の言葉に悠里は表情を暗くした。
「でも、借金もあるし、そんな余裕は……」
「いや、それでも必要だと思うんだ。俺たち、ずっと頑張ってきただろ? 少しぐらい、息抜きがあってもいいじゃないか」
悠里は迷いの表情を浮かべたが、やがて静かにうなずいた。
「……分かったわ。でも、本当にいいの?」
「もちろん。たまには俺の言うことも信じてくれ」
悠里は微笑み、その目にかすかな光が戻った気がした。
拓郎の胸には、ようやく彼女を救う1歩を踏み出せた安堵感が広がった。
拓郎と悠里が向かったのは、海沿いの小さな町。そこは2人が大学時代、ゼミの合宿で訪れた場所だ。どこか懐かしさを感じさせる景色の中、2人は少しずつ言葉を交わしながら駅から海岸へと続く小道を歩いていった。
やがて冷たい潮風が2人の頬を撫でた。冬の海は荒涼としながらも広大で、拓郎たちが抱える悩みなんてちっぽけなものだと言っているようだった。
「懐かしい。ここで花火とかしたよな」
拓郎は砂浜に埋もれた花火の燃えがらを拾い上げる。拓郎たちがこの浜で遊んでいたのはもう20年も前のことだったが、今も昔も学生のすることというのはそう変わらないのかもしれない。
「覚えてるよ。冬の合宿のとき、あなたが夏の残りとか言って持ってきて、震えながらみんなで海まで来たのに、結局線香花火以外はしけってて使えなかった」
「線香花火も最悪だったよな。みんな震えてるから、すぐに落ちてたし」
「そうそう。帰りにみんなで食べた肉まんだけがいい思い出」
悠里が小さく笑う。拓郎は無意識のうちにカメラを構え、シャッターを切っている。
「なに、不意打ちやめてよ」
悠里が不満そうに頬を膨らめる。久しぶりに見た悠里の表情に、覗き込んだままの
ファインダーがわずかに霞む。
綺麗だったから思わず。
やっぱり悠里は笑っているほうがいいよ。
砂浜の足跡が波打ち際で消えていくように、どの言葉もかたちにはならず、拓郎は代わりにもう1度、微笑む悠里に向けてシャッターを切る。
※複数の事例から着想を得たフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。