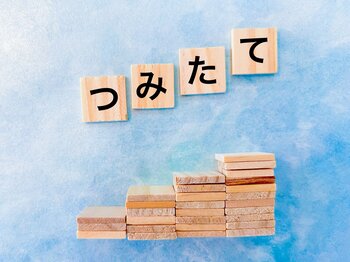ケース4: 「60歳から」のiDeCoはNISA(つみたて投資枠)と比較しながらスタート
・60歳8カ月
・再雇用で働いている会社員
〈受給可能年齢〉66歳(最初のDC拠出から5年経過後から受給可能のため)
〈加入可能期間〉65歳まで(再雇用で厚生年金保険の被保険者として勤務)
〈拠出限度額〉月額2.3万円
このケースでは、60歳退職時に退職金を1500万円受け取っており、NISAでの運用を考えています。
再雇用の給与は高くはありませんが、所得税は課税されている状態です。NISAのつみたて投資枠での運用を予定していた金額のうち、2.3万円はiDeCoの掛金とすることにして所得税・住民税の軽減効果を活用します。
60歳超の方の場合、若年層にとってのiDeCoの最大のデメリット「60歳まで受け取れない」ことは、それほど大きなデメリットとはなりません。ただ、iDeCoで毎月拠出にすると、最低でも年額2,052円の手数料(毎月66円、拠出時に105円)がかかります※。
掛金拠出を年1回にすれば、手数料も897円まで抑えられるので、税の軽減効果に重点を置くのであれば、そうした対応も考慮に入れましょう。
老後資産を取り崩していく場合も、運用の有無で資産の寿命は大きく異なります。公的年金の受給金額を想定しながら、余裕資金はリスクを抑えた運用にしていきます。
iDeCoは年金制度として設定されているため、ターゲットイヤー型の投資信託のなかには、相場の急落時にいったん運用をストップしてくれる安心機能がついたものもあります。NISAつみたて投資枠の運用商品にはない魅力といえます。ただ、60代になってから初めてDC(企業型DC、iDeCoともに)を活用される場合、最初の拠出から5年間は受け取れない、という点は認識が必要です。
※金融機関によって異なる。表記は野村證券の場合。
50代超に限らず、企業型DCのマッチング拠出、iDeCo、NISAなど、どの方法をとるかは、どのメリットに重点を置くかという点から選ぶのがよいでしょう。
具体的には、拠出時の所得税・住民税の軽減効果なのか、運用益非課税なのか、資産寿命を延ばすための運用なのか等です。
いずれにしろ、積立投資にはスタートの時期が遅すぎるということはありません。積立投資は思い立った時にスタートするのが一番です。
※数字に関する部分は手数料を考慮していません。運用結果は簡易計算によるものです。