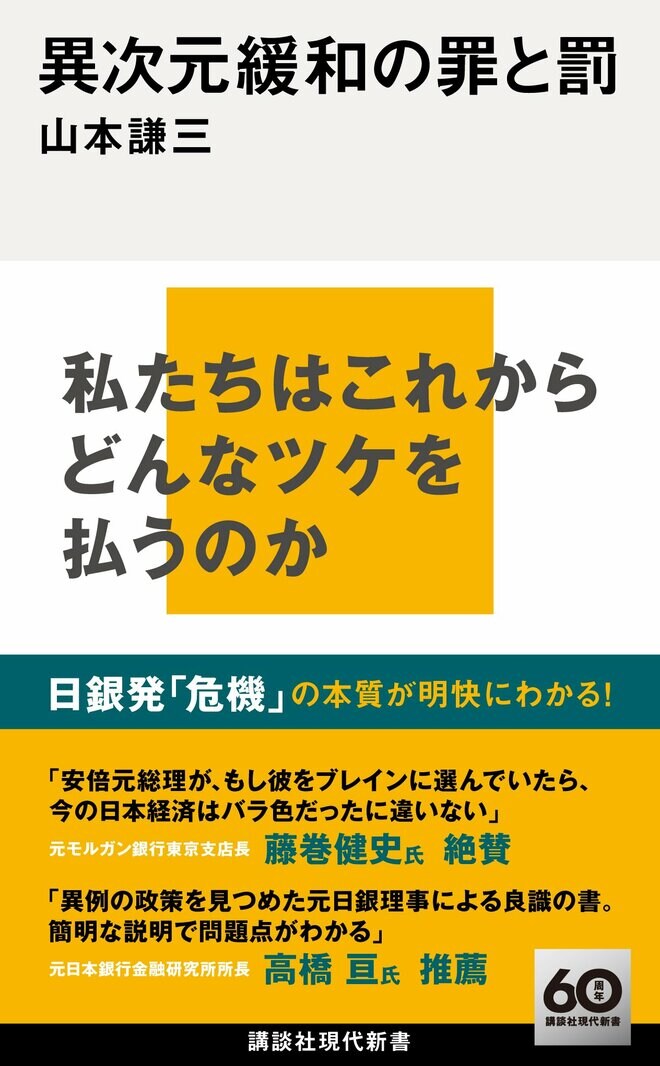確認困難な「物価と賃金の好循環」
植田新総裁は、就任当初から一貫して異次元緩和を否定しない姿勢を維持してきた。その上で、長期金利に限っては、タイミングを計りながらコントロールの緩和に努めてきた。2023年7月、前年(2022年)末に拡大した±0.5%程度の金利変動幅を「目途」と呼び替え、事実上1.0%までの上昇を容認した。さらに同年10月には、名実ともに上限を1.0%に引き上げ、この水準を超える場合も柔軟に運営する姿勢を明らかにした。
植田総裁は、就任以前から、長期金利の抑制が金利機能を低下させることへの懸念を表明しており、そうした理解に立った対応だった。
一方、金融政策の本丸である短期金利のコントロールは、「物価2%を安定的に持続するために必要な時点まで」異次元緩和を継続するとの方針を維持し、総裁就任後もマイナス0.1%を約1年間続けた。その際、日銀が「持続的、安定的な物価目標の達成」を見通すための判定材料としてあげたのは「物価と賃金の好循環」の蓋然性の高まりだった。
この物価目標達成の判定材料は、黒田総裁時代の終盤期に付け加えられたものだった。2022年6月、「値上げ許容度」発言が世間から批判を浴びた日銀は、発言の撤回に追い込まれた。黒田総裁が講演の中で行った「企業の価格設定スタンスが積極化している中で、日本の家計の値上げ許容度も高まってきているのは、持続的な物価上昇の実現を目指す観点からは重要な変化だ」との発言だった(2022年6月6日きさらぎ会での講演)。
それまで、物価が上がらない理由として「適合的期待」の存在を繰り返してきた日銀にしてみれば、家計の値上げ許容度が高まるのは望ましい変化に見えたのだろう。しかし、国民の受け止め方は違った。国民は2022年春以降の生活費の値上がりに苦しんでいた。物価目標2%をかたくなに守ろうとする日銀と、物価上昇率0%を前提に生活設計を行っている家計の間に、大きな認識のギャップがあった。
以後、日銀は、「値上げ許容度」を連想させる発言は控え、「物価と賃金の好循環」への言及を増やした。賃金の上昇を強調することで、国民に寄り添う姿勢を示す狙いもあったのだろう。植田総裁も、持続的、安定的な物価目標達成の判定材料として「物価と賃金の好循環」を確認する姿勢を継続した。
しかし、この判定材料にはいくつかの疑問があった。まず、「物価と賃金の好循環」といえるためには、少なくとも賃金の伸びが物価の上昇率を上回り、プラスの実質賃金がある程度の期間、定着する必要がある。しかし、足元の実質賃金は長期にわたりマイナスが続いていた。
賃金は物価を後追いする傾向の強い指標(遅行指標)なので、物価が上昇する局面で実質賃金がマイナスとなるのはやむを得ない。しかし、大企業の賃上げ動向は春闘の動きで分かるものの、中小・零細企業を含む全体を把握できるのは、例年、秋以降のタイミングとなる。将来の物価見通しを前提に金融政策を判断するにしても、春闘だけで全体を判断するのはリスクがあった。
また、物価と賃金の関係には、好循環も悪循環もある。中央銀行が苦しんできたのは、むしろ物価と賃金の悪循環の方だった。1960年代~80年代の米国、1970年代の日本、1980年代~90年代の南米と、その例は枚挙に暇がない。ならば、好循環であれ悪循環であれ、物価の上昇局面では、金融を引き締める(あるいは金融緩和の程度を弱める)のがオーソドックスな対応だ。悪循環ならば、なおさら早く引き締めに転じなければならない。なぜ、好循環の見極めにそれほど時間をかけなければならないのか、疑問が残った。
●第2回は【なぜ実質賃金は低迷したままなのか? 賃金から日本経済の実相に迫る】です。(11月26日に配信予定)
異次元緩和の罪と罰
著者名 山本 謙三
発行 講談社
価格 1,210円(税込)