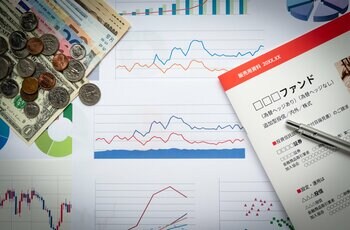ファンドラップの手数料は三重構造
ファンドラップとは、金融機関に運用を一任できるラップ口座のうち、投資信託の運用に特化した商品です。金融機関は顧客のリスク許容度に応じ、顧客の資産を複数の投資信託で運用します。
通常のラップ口座は多くが富裕層向けで、契約は数千万円単位となることが一般的です。一方ファンドラップは比較的少ない金額から契約でき、数百万円の資金も受け入れています。敷居の低さも人気の理由かもしれません。
ただしコストは高めです。ファンドラップは一般に、契約中は「ファンドラップ手数料」と「投資一任報酬」がかかります。前者は口座の管理料に相当し、後者は運用を委託する対価です。投資一任報酬は、固定報酬に加え成功報酬が設定されている場合もあります。
さらに投資信託で運用するファンドラップは、組み入れる投資信託でも信託報酬が発生します。つまりファンドラップは、直接の費用としてファンドラップ手数料と投資一任報酬の負担があり、間接費用として投資信託の信託報酬、合わせて3つの費用が発生するのです。
ファンドラップの高いコストは運用成績を圧迫しています。金融庁がQUICK資産運用研究所に分析を委託して公表する資料によれば、ファンドラップの運用成績は費用(※)控除前ならバランス型ファンドと比べて悪くないものの、費用控除後だと下回るケースが多かったようです。
※ファンドラップ手数料および投資一任報酬などの年間費用で、信託報酬などの運用コストは含まない。
ファンドラップの費用控除後のシャープレシオ(5年)がバランス型ファンド全体の平均値(0.19)を上回った商品は少ない。その一方で、費用控除前のシャープレシオ(5年)では、バランス型ファンド全体の平均値を上回ったファンドラップが目立つ。
引用:金融庁 国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標(KPI)の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析(2022年末)