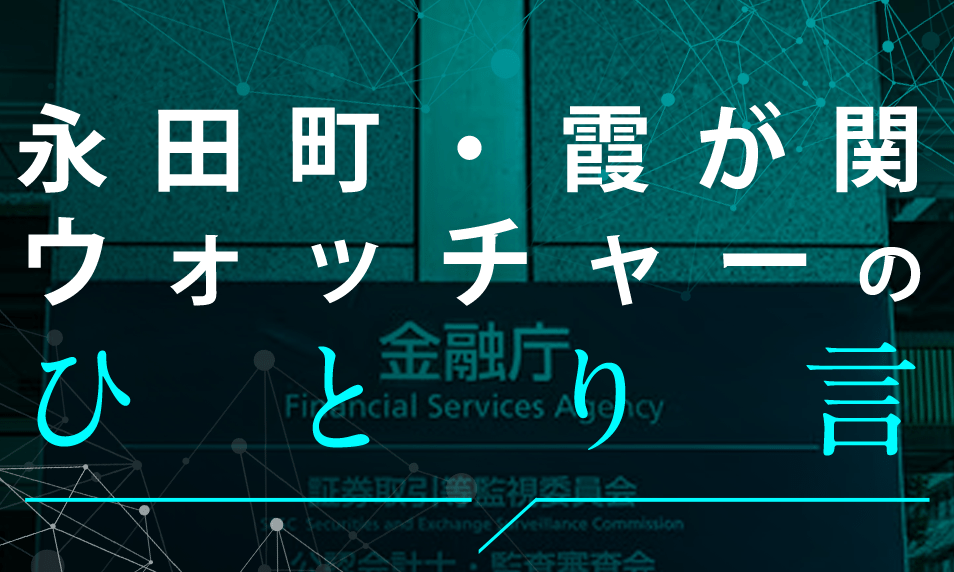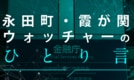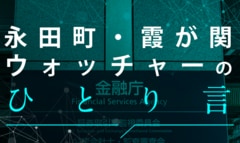高市早苗氏の自民党総裁選出は番狂わせだったが、これは日本経済が長らく停滞し、国やルールに縛られて動きが鈍っていた状態から、自ら成長し、資金が活発に動く経済へと大きく方向転換するきっかけを示す、象徴的な出来事となるのかもしれない。鼻の利く金融市場はこうした変化を察知し、「円安・株高・金利上昇」というトリプルインパクトが日本列島を駆け巡り始めているように見える。以下、高市氏のこれまでの著書や公約、コメントなどを踏まえ、近く発足が見込まれる高市政権が目指す経済の方向性、それが市場に与える影響、そして金融機関に求められる新たな役割について、私見を述べてみたい。
高市氏が描く新しい経済の形
高市氏は、政府資金(財政)、金融機関資金(金融)、そして私たち個人や企業の資金(民間資金)という、これまで別々に動いていた資金の流れを一つに繋ぎ合わせ、日本経済全体を再び力強く動かすための大きな計画と捉えているように思われる。
この計画は、以下の3つの柱で構成される。
①積極財政と戦略的減税の「車の両輪」
将来の成長に繋がる先端技術開発やインフラ整備への大胆な公共投資と、イノベーションを促進する戦略的減税を組み合わせることで、経済活動の土台を強化し、持続的な成長を目指す。
②国主導の資金誘導と民間活力の活用
国が資金誘導の全体像を描き、将来性のある産業や技術革新分野へ意識的に資金を誘導することで、民間資金や活力を引き出し、日本経済全体の底上げを図る。
③個人貯蓄・企業内部留保の投資への転換
低金利で眠っていた個人貯蓄や企業内部留保を投資へと向かわせるインセンティブを強化するとともに、リスクマネーを市場に供給し、新しいビジネスや雇用を創出することで経済全体に活力を生み出す好循環を目指す。
この構想は、「失われた30年」と言われた停滞期にデフレと低金利政策で抑えられてきた日本経済の潜在力を引き出す、まさに「地殻変動」とも言える挑戦だ。
「円安・株高・金利上昇」の波
高市総裁の就任は、すでに市場に明確な変化をもたらしている。
①株高:大胆な公共投資や先端産業への資金投入への期待から、企業の業績改善が見込まれ、株価が上昇。
②金利上昇: 積極的な財政政策による国債増加観測から、金利が上昇。
③円安: 日米金利差拡大や財政拡大による円の供給増への思惑から、円安が進行。
この「円安・株高・金利上昇」は、金融機関にとって複雑な状況をもたらしそうだ。金利上昇は収益改善のチャンスだが、保有債券の価値下落リスクも伴うため、金融機関はリスク管理と投資ポートフォリオの見直しが求められる。
日銀との新しい関係性
高市氏は「日銀の独立性は尊重するが、金融政策は政府の経済戦略と一致すべきだ」と述べ、政府の経済戦略との連携を重視する姿勢を示している。アベノミクス以降の「政府・日銀共同声明」から踏み込んで、日銀の金融政策が政府の経済戦略と「一致すべき」と明言している点で、従来の「連携」よりも強い関与を求めるニュアンスが感じられる。
市場は、この発言を金融政策の政治的影響力増大の兆候と受け止める可能性がある。もし、インフレ抑制よりも経済成長を優先する政府の意向が強く反映された場合、長期的な物価安定目標の達成が困難になる可能性が懸念される。一方で、政府と日銀が一体となって経済成長戦略を推進することで、より効果的な政策運営が期待できるとの見方もある。
高市政権の課題
いずれにせよ、経済再生の道は容易ではない。成長のための投資が本格化すれば、国債の需給バランスが崩れ、金利上昇は避けられないだろう。金利上昇は企業の資金調達コスト増や住宅ローン金利に影響し、経済全体への影響は大きいと考えられる。また、経済の過熱によるインフレ懸念、為替市場の急激な変動、資金調達コストの増加など、政策と市場のタイミングがずれると、経済が不安定になるリスクも抱える。
高市政権にとって、この「成長」と「安定」という、相反する目標をいかにバランスよく達成するかが最大の課題となるだろう。金融政策と財政政策の連携、そして市場との対話を通じて、過度な変動を抑えつつ、持続的な成長を実現できるか、その手腕が問われる。
金融機関の新たな役割
このような環境変化の中で、金融機関に求められる役割は、単に制度や商品を説明するだけでなく、顧客が抱える不安や期待に対して、制度、市場、税制という3つの視点から「意味づけ」をして、分かりやすく説明できる「変化を翻訳する側」になることであると思う。例えば、「この制度変更はあなたの資産設計にどう影響するのか」「この市場の動きはあなたのポートフォリオにどのような意味を持つのか」といった問いに、具体的な言葉で答える力が求められる。
投資の基本的な原則である「長期・積立・分散」はこれからも重要だが、これに加えて、「時間に任せる投資」ではなく、「時間とともに変化を吸収する投資」という考え方を提案する必要がある。積立投資は単なるルーティンではなく、市場の変動を乗りこなし、そのリズムを乱さずに続けることで、ポートフォリオは「変動の平均化」という最大の複利効果を得られる。顧客にそのダイナミックな側面を伝え、納得して継続してもらうことが、これからの金融機関の腕の見せ所となる。
また、金利が上昇する局面では、債券や外貨といった、これまで「安定資産」とされてきたものの価値が再び注目される。金融機関においては、満期を迎えた資産を金利情勢に合わせて賢く「ロールオーバー」して、継続的に安定した金利収入を確保することが長期運用の醍醐味の一つであると顧客に伝える好機となるだろう。
金融庁の組織再編
金融庁が要望している組織再編は、こうした流れを後押しすると思われる。資産運用を専門に担当する新しい監督局が設立されれば、運用ビジネスはより明確に「制度産業」としての性格を強めるだろう。金融商品の登録、販売、情報開示が一体的に管理されるようになり、運用会社も販売会社も「説明力」が競争力の核心となる。
すなわち、政策を正確に理解し、制度を分かりやすい言葉で伝える能力が、これからの金融業界における新しい価値となる。金融機関は、顧客に対して単に情報を伝えるだけでなく、その情報の意味合いや、顧客の資産形成に与える影響を深く掘り下げて解説する能力を磨く必要がある。
一方で、積極的な財政政策の裏側には、財政リスクの膨張という問題が潜む。金利上昇が制御不能になれば、国の借金の利払い費が財政運営を圧迫するだろう。市場が不安定になれば、個人投資家の投資意欲も冷え込む可能性がある。だからこそ、金融機関は顧客に「制度や相場の変動に振り回されない運用設計」を提案する必要がある。顧客のライフプランやリスク許容度に基づいた、堅実なポートフォリオを設計することが、今後の金融アドバイスの本質となるだろう。
予期せぬ総裁選出をきっかけに、日本の資金は活発に動き始めている。その流れを把握し、顧客に分かりやすい言葉で伝えること。それこそが、今まさに、金融機関に求められていることであろう。