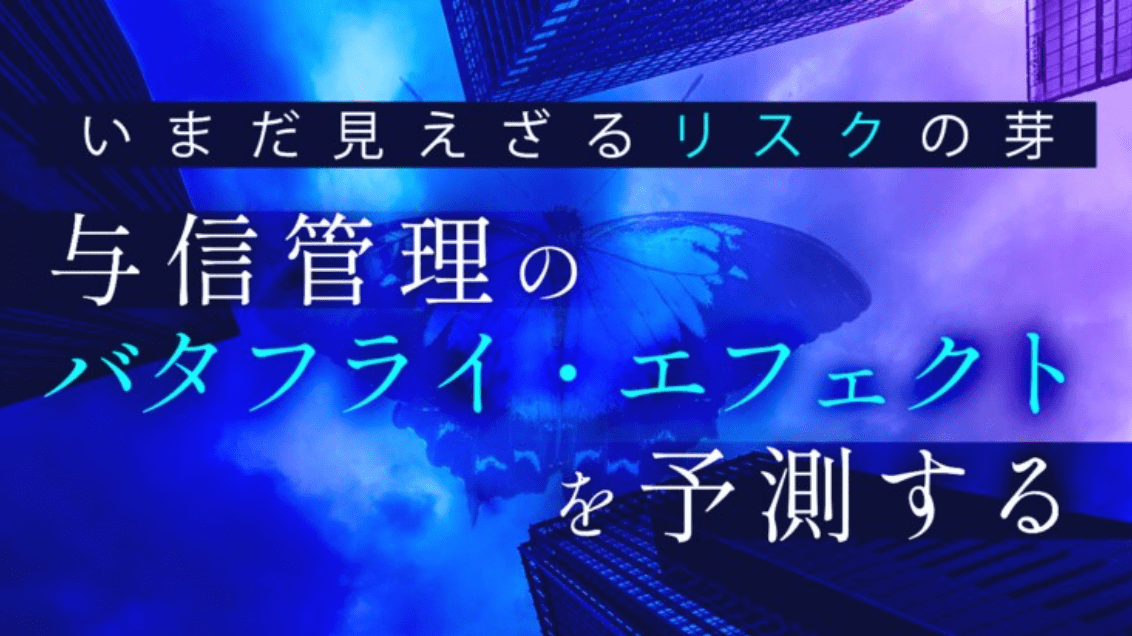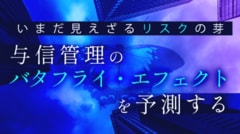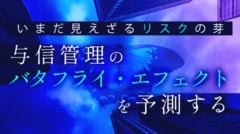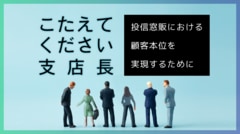「都市の木造化推進法」が昨年10月に施行された。正式名称は「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」という。この法律の成立に伴って建築基準法も改正され、今年の4月1日に施行が予定されている。今回は、これらに伴う各セクターへの中長期的な影響を予想したい。
日本の木材自給率が回復している
近年、国産材の需要を促進する法制等の手当てが順次なされている。
さかのぼること15年前には、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(通称:「公共建築物等の木材利用促進法」)」が施行され、低層の公共建築物は原則として全て木造とする方針を示した。こうした方針もあって、2002年に19%まで落ち込んだ日本の木材自給率が2023年に43%と倍以上になり、1970年代の水準に回復している。
こうした促進法制等が手当てされる背景には、森林の循環が求められる現状がある。日本は国土の3分の2を森林が占め、そのうち4割が人口林であり、その人口林の5割以上が木材として利用可能な50年生(ねんせい)以上となっている。
よって、単純計算で算出される50年生の人口林面積は、国土の8分の一強に及ぶ。
66%[国土の三分の二]×40%[森林に占める人口林割合]×50%[人口林に占める利用可能比率]=13.2%[国土の八分の一強]
改めて言うまでもなく、樹木は大気中の二酸化炭素を吸収し、光合成によって体内に固定して成長する。その吸収量は枯死するまで一律ではなく、おおむね20年生をピークとし、その後は衰退する。よって健全な森林を形成するためには、地表近くまで日光が届くよう立木の密度を調整する間伐整備だけでなく、適切に伐採・植林して若返りを図る入換えも必要となる。国産材の利用増は樹木の伐採を伴うため、第一印象では森林面積が減少し地球温暖化防止に逆行する印象を受けがちだが、全体としてはむしろ高齢木の伐採を迅速に進めなければならない環境だ。
今般の建築基準法の改正箇所は広範囲のため、本稿では、特に影響すると見込まれる代表的な箇所にまつわる予測をできるだけ平易に表記したい。
まず、「階数が3階(建て)以下かつ、高さ16㍍以下」までの木造建築物の構造計算が合理化(=簡略化)された[建築基準法第20条第1項2号]。
改正後は、延べ面積300㎡までの建築物で簡易な構造計算による建築が可能となり、二級建築士でも設計が手掛けられるようになる。専門のソフトウェアの投資と算出まで2~3週間程度を要した構造計算の発注時には、1㎡あたり2,000円~3,500円程度の費用負担をもたらしていた。法改正による簡略化により、建築費用削減が見込まれる。
また、延べ面積3,000㎡超の大規模建築物について、一定の条件の下で、構造部材(いわゆる骨組み)を石膏ボードなどの不燃材料で覆わずに取り扱えるようになるなど、耐火基準が緩和される[建築基準法第21条第2項]。
法改正によって内装木質化のハードルが下がると共に、木目を露出したデザインなど、デザインのレパートリーが広がることも見込まれる。
さらに、5階以上14階建て以下の建築物に最大2時間の耐火性能が求められていたところ、5階以上9階以下の中層建築部については90分の耐火性能に緩和した。木造による耐火設計ニーズが強いと言われる中層建築物に譲歩した形だ。2024年中に建築届が出された47万7766棟のうち、9階以下の建物は40万6431棟と85%を占める。大多数と言って良い占有率だ。
これらの改正に加え、木造建築に助成を行っている自治体も少なくない。例えば東京都では、中・大規模の民間建築物を新築・改築する場合に、多摩産の木材を3割以上使用することなどを条件に、㋐設計費用の二分の一(500~5,000万円まで)、㋑木造木質化経費の二分の一または建築工事費の15%以内(5,000万円~5億円まで)の補助金を支給している。
2022年5月の日本政策投資銀行の調査結果によれば、木質化対応に伴う支払費用は、木質化を図らなかった場合の10%増程度となる模様だ。よって単純計算では、東京都の助成は費用増を補ってあまりあることとなる。
これらの結果、(「木質系材料+鋼材など非木質系材料」の複合による)木質ハイブリッド部材を含め、今後、構造部材などに木質系建材を使用した建物が増加することを見込む。
2021年には、野村不動産が東京都千代田区に日本初の木造ハイブリッド高層分譲マンションとして、14階建て・総戸数36戸の「プラウド神田駿河台」を施工した。このマンションは、国内のグッドデザイン賞のほか、2023年には本部を米国のイリノイ工科大学に置く国際NPO「高層ビル・都市居住協議会(CTBUH、Council on Tall Buildings and Urban Habitat)」の建築賞を受賞している。筆者も現地を訪れて建物を目視したが、入口やベランダの間仕切りなどに木材が使用されていた。今後、高級高層マンションなどで、このような工法が採用されることが増える事態を予想する。
同様の動きは、ビルにも広がるだろう。昨年11月の日本不動産研究所の調査・公表内容によれば、延床面積1,000㎡で賃貸市場に出ている1981年以前に竣工した(旧耐震基準時代の)オフィスビルは、全国でなお2,656万㎡(全体の18%)・4,696棟(同23%)残っている。東京23区内だけでも1,340万㎡・2,603棟に及ぶため、大都市を中心に、年齢の高いビルが建替えや改築がなされていく中、それに伴って木質化が進むことが想像に難くない。
木材が栄え、鉄材がすたれる?
これらを裏返せば、従来、中高層マンションやオフィスビルの構造部材などの中心であった鉄筋の利用が減少することを意味する。その影響も、相応に広がるだろう。
直接的な影響を受けるのは、まずもって鉄スクラップ市場だ。建材で使用される鋼材は、鉄スクラップを電気炉で溶解して再利用する鉄筋が中心だ。大まかには言えば、鉄スクラップリサイクル事業者(以下「リサイクル事業者」とする。)がスクラップを買い取り、有用金属を選別して粉砕などを行った後に、電気炉を持つ製鐵事業者などに持ち込む流れで再生される。
そのスクラップの2021年以降の市況には、低下傾向が認められる[図表1]。鉄スクラップは輸出もされているが、近時の円安ドル高の外国為替相場にも関わらず、昨年の輸出量は前年比5.6%減少した。中国からアジア各国への鉄鋼製品・半製品の高水準の輸出が続いたため、これらアジア各国の鉄スクラップ需要を押し下げた模様だ。
こうした構図は一朝一夕には大きく変動しないため、今後の短期間で、アジア各国の鉄スクラップ需要が急拡大する展開は望み薄だ。よって金属スクラップ市況には、建物の木質化による中長期的な国内需要の減退が、相応に大きなマイナス要因となるだろう。これらの結果、市場価格がリサイクル事業者の仕入(買取)価格を下回れば、リサイクル事業者の保有在庫が不良化する。従って今般の法改正は、金属リサイクルセクターに負の影響を与えよう。近年、リサイクル事業者の倒産などの報道が時折みられるが、市況悪化に意欲を喪失させ、廃業や事業停止などを選ぶ事業者が現れる可能性がある。
また、鉄の密度は高く、比重は水の8倍にも及ぶ。よって重量も重く、回収時などのスクラップの運搬には、(いわゆる「鉄箱トラック」など)特殊車両が多用される。従って、リサイクル事業者が行き詰まって減少すれば、自動車整備・販売セクターのうち、特に特殊車両の製造・整備関連事業者に間接的な負の影響をもたらそう。
順番が逆になったが、リサイクル事業者が買い取ったスクラップは“ヤード”と呼ばれる置場に置かれ、選別・粉砕された後に種類別などで集積されて配送を待つ。重量の重い鉄などの金属ゆえに、置場が窪むことも珍しくなく、一定の頻度で整地を余儀なくされる事業者もみられる。ヤードは雨ざらしのため、囲いや間仕切りなども経年劣化する。こうした中で、設備事業者がヤードに出入りし、設備などのメインテナンスを行っている。よってリサイクル事業者が行き詰まれば、設備工事セクターのうち、こうしたヤード関連事業者に負の影響を与えよう。
「スクラップ=産廃」の印象を与えるため、その置場を貸すことに抵抗を覚える地主や近隣居住者は珍しくない。それゆえに、ヤード用地の確保は、リサイクル事業で最も難解な事項の一つだ。裏返せば、ヤード用地を貸与している地主は、それなりの覚悟と引き換えに相応の賃料を受領していることが多い。
そんな中でもリサイクル事業者が行き詰まれば、不動産(賃貸)セクター、つまりは地主に直接的な負の影響を与えよう。他の事業者に居抜きのヤードとして貸し出せれば良いが、それができずに他の用途で貸し出すことになれば、改良負担を強いられかねない。
影響は、中古自動車販売セクターにも及ぶ。自動車の原材料に占める鉄部分はおよそ4割を占め、毎年相当数の廃車が発生している。このため、配車後の車体は、解体ビルからの建材と並んで鉄スクラップの代表的な拠出元となっている。
鉄スクラップ価格が低迷すれば、その影響は(廃車予定分を含む)中古車相場にも及ぶ。「最後の最後はスクラップ用に(リサイクル事業者に)売れば良い」という選択ができなくなれば、年式の古い自動車の買取りなどに慎重にならざるを得なくなる。
そうした一方、故障しない・燃費が良いことで世界的に有名な国産車は、年式が古くとも諸外国での人気が根強い。このため国内の買取価格の低迷は、「(それほど差益が得られなくとも/修理時のパーツ用としても)輸出に回そう」という意向に拍車を掛ける。現在は、経済制裁として「排気量1.9㍑超の内燃機関(エンジン)車」などの輸出が禁じられているロシアについても、停戦が成立して制裁が解除されれば中古車の輸出が増えることになろう。
それでなくとも、近年の輸出と廃車には対照的な動向がみられる[図表2]。永久抹消登録台数は、解体報告記録がなされた日を記載して陸運局に提出された台数のため、スクラップされた台数と等しくなる。
今後、さらに輸出が増えれば、その分だけ国内の中古車市場に入ってくる台数が減少する。それに伴って、廃車時の解体車両から取り外されて再利用されるパーツも減少するため、使用中の車両の修理や整備にも支障を来すようになる。ユーザー目線で、「(以前に比べて)中古車はいざというときに直せなくなった」という認識が広まれば、中長期的な中古車流通市場の縮小要因になりかねない。
販売する商品数が減れば、売上や収益を獲得する機会も減る。結果として、修理・整備事業者や中古車販売事業者間の生き残り競争が激化し、相対的に経営基盤が脆弱な中小企業・小規模事業者が市場から淘汰される。経済センサス活動調査上では、中古自動車小売業が2014年の1万5,393事業所から2021年の1万1,168事業所に27%減少している。今般の建築基準法改正は、こうした減少傾向をさらに加速させかねない。