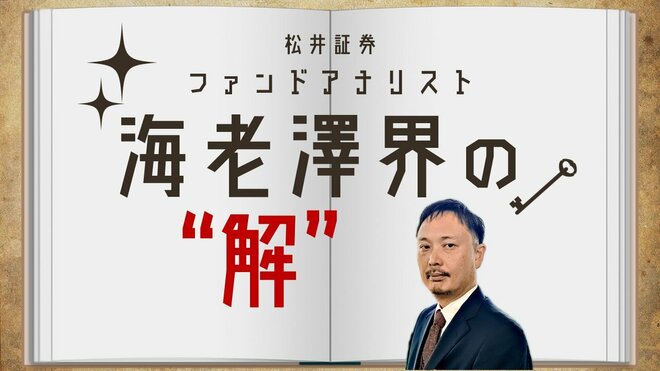投資信託の月次リポートや特設サイトなどで、投信アワードの受賞実績がロゴやバナーと一緒に掲載されているのを目にすることが多い。この手のアワードの受賞実績をどこまで信用していいものか、悩んだ経験がある人も少なくないだろう。長年、投信アワードに携わり、アワードの立ち上げにも関わったこともある筆者の立場から、情報の有効な活用法をお伝えしたい。
アワードの受賞ファンドをみる際のポイントは2つ
結論を最初に言えば、アワードの情報は有益な情報になり得る。ただし、以下の2点はおさえておいた方が良いだろう。
- ①資先選びの決め手にするのではなく、スクリーニング手段の1つとして活用すべき
- ②各アワードの特徴を知っておくことは重要
なお、投信アワードの中には、人気投票やインフルエンサーの選考によるものもあるが、ここではそれらは対象外としたい。過去の運用実績(定量評価)を中心に選定する主要アワードの中から、選考方法が具体的に開示されている以下のアワードについて取り上げたい。
■R&Iファンド大賞
■LSEGリッパー・ファンド・アワード・ジャパン
■モーニングスター・アワード
主に定量評価で選考するという意味では、これらのアワードの受賞ファンドは過去の実績が評価されたものであり、その成果が将来を保証するものではない点は大前提として読み進めていただきたい。
日本の公募投信の数は5000本を超える。どのくらい多いかということを分かりやすく言えば、日本の上場株式の数(4000社弱)よりも多い。NISA(少額投資非課税制度)の普及で投信が個人の資産形成手段として重要視されている中で、何を選んでよいか分からない方は多いだろう。
ネット空間では「○○一択」といった、特定のファンド以外を認めないような根拠の乏しいフレーズが蔓延している。敢えて真面目に取り合えば、世の中の事象は常に複雑であり、「一択」で片付けられることなどほとんどないと思うので、筆者はこの種のフレーズが好きではない。ただ、そうした言葉に助けられなければ選べないほど、選択肢が多いのも事実である。
アワードには「限界」があることを前もって知っておく
だからこそ、1つの情報としてアワードを活用すればよい。中には「なぜこんなファンドが受賞するのか?」「なぜこのファンドは受賞していない?」と思う時もあるだろう。そんな時は選考方法を確認してほしい。その理由が見えてくるはずだ。そして、それを含めてアワードの特徴だと捉えればよいだろう。
例えば「150メートル走では誰にも負けない」という人がいても、陸上競技の公式種目は100メートル走と200メートル走であるから、競技の上で、その人は評価されない。投信のアワードも同じで、基本的に同じような基準で評価するのだから、すべてのファンドの良さを浮き彫りにできるとは限らない。自ずと限界は出てくるのだ。
一方でそれは、恣意性を排除するからこそ生まれてくる結果でもある。いずれにしても、アワードを手がかりに個々の受賞ファンドを深掘りすることはさまざまな気付きを与えてくれる。それぞれのアワードがどんなモノサシを使っているかを把握し、その情報を活用することは、投信選びの立派なアプローチの1つだろう。
「R&I」はシンプルにシャープレシオで評価
それぞれのアワードを見てみよう。まずはどんな指標で選考しているかみてみよう。この点で最も分かりやすいのは「R&Iファンド大賞」(以下、R&I)だろう。代表的なリスク控除後リターン(無リスク資産に対する超過リターン÷価格変動リスク)であるシャープレシオで選考している。ここでは詳しいシャープレシオの話は割愛するが、公募投信の評価に使われる最もポピュラーな指標と言ってよいだろう。
なお、リターンとリスクの両面を考慮するのは他の2アワードも同じだが、「LSEGリッパー・ファンド・アワード・ジャパン」(以下、リッパー)は「収益一貫性」という独自の指標、「モーニングスター・アワード」(以下、MS)はリターンとリスクの双方で「パーセント順位」(イメージとしては最高が100で最低が0)を付け、スコア化している。
「定性評価」をアワードの選考に加えることの是非
多くのアワードは過去の運用実績、つまり数値に表れる「定量評価」で選考する。運用方針や運用哲学など、客観的に数値では評価できない部分の評価、いわゆる「定性評価」をアワードで加味するか否かは時々、議論の対象になる。定性評価は評価する人の主観や恣意性が入り込む余地が多いためだ。
定性評価は「今後、高い実績が期待できる」という未来に対する評価でもある(逆に定量評価は過去に対する評価=バックミラー)。オリンピックの100メートル走で、2位だった選手に「君には伸びしろがある」という理由で金メダルをあげたら1位の選手は絶対に納得しないだろう。基本的には定量評価100%がアワードの選考方法としては分かりやすいと筆者自身は考えている。
もちろん、定性評価をアワードの選考に組み込むことが100%否定されるものとはいえないだろう。例えば、主要アワードの中ではMSが定性評価を選考プロセスに取り入れているが、あくまで、評価が並んだ場合に定性評価を優先する、または、表彰の条件として一定の定性評価の基準をクリアしていることを要するといったものであり、納得できる定性評価の取り入れ方だ。
また、非常に重要なポイントとして、MSの場合、運用戦略・評価の対価として運用会社から手数料を受け取っていない。「対価を得て評価を付けたプロダクトがアワードにおいて表彰される」といった利益相反に絡む問題は発生しないといえる。
一方で、もしも今後、さまざまなアワードが乱立してきた時、それらのアワードにおいて、定性評価がどの程度選考に考慮されていて、妥当な内容かどうか、そして、利益相反に絡む問題はないのか、注意して見定めた方がよい。公平性というアワードの根幹にかかわる部分に直結するためだ。