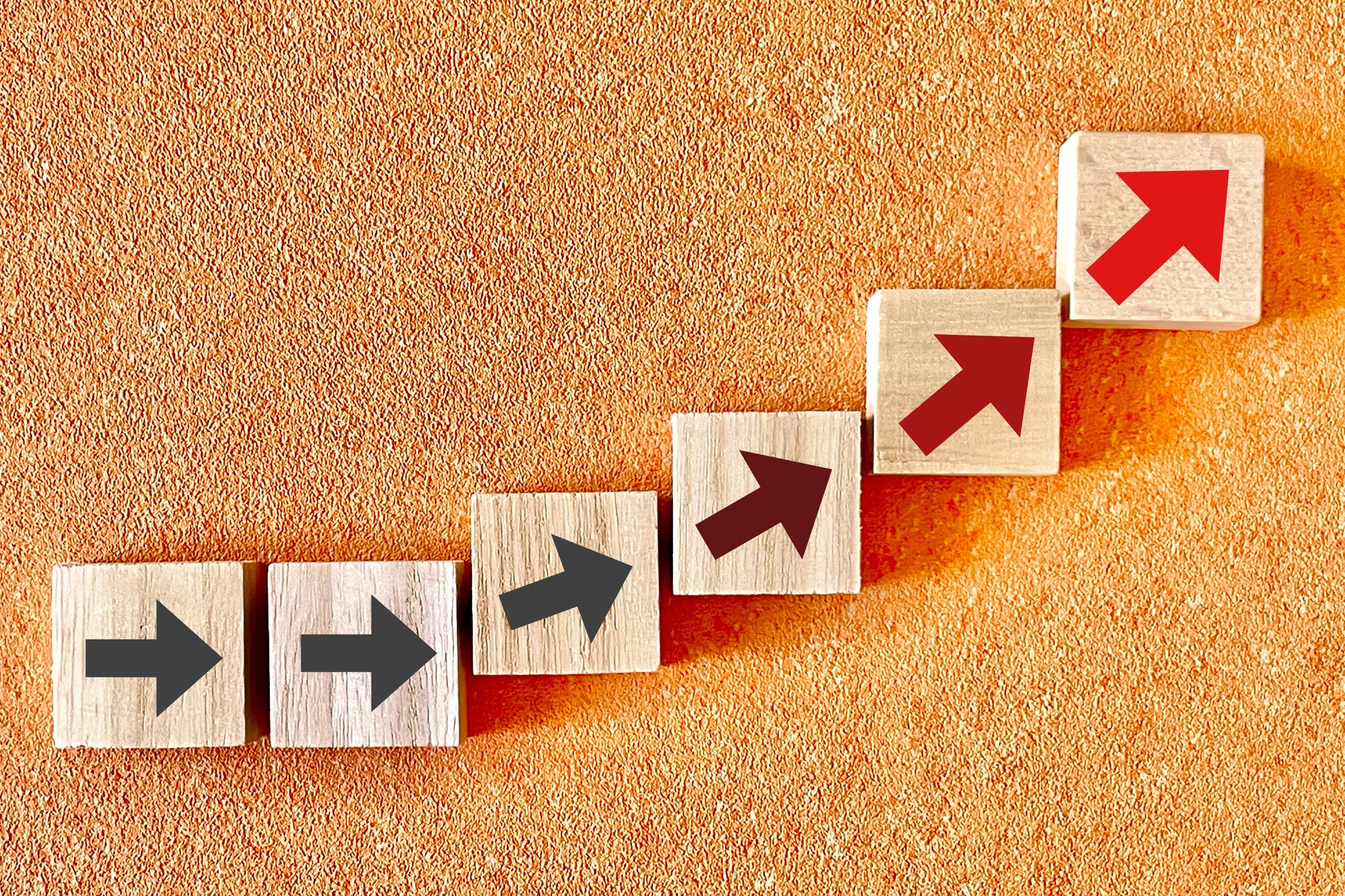「ディープバリュー戦略」の人気は持続する?
三井住友銀行の売れ筋ランキングの第9位にランクインした「ドナルド・スミス グローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド」は、株価の割安度を測る尺度として「株価有形純資産倍率」を活用し、そのランキングで下位10%の銘柄を投資対象にしている。「有形純資産」とは、現金・有価証券や不動産、工場、材料・部品など「実物が存在する資産」のことで、評価(現金化)がしやすい資産のこと。純資産から特許権やのれん、ソフトウエアなど評価が難しい「無形純資産」は除いて資産価値を計算することで、一般的な指標として使われる「株価純資産倍率(PBR)」を使うよりも、計算式における「純資産総額」の金額が小さくなるため、より割安な銘柄にフォーカスできる戦略だ。
実際に、10月14日に発表された「ポートフォリオ構築のお知らせ」によると、ポートフォリオのPBRは0.90倍で、「世界株式(MSCI ACWI)」の3.55倍や「世界バリュー株式」の2.23倍より大幅に低い。PER(株価収益率)でも8.64倍で「世界株式」の22.89倍や「世界バリュー株式」の16.76倍を大きく下回っている。組み入れ上位銘柄もアイルランドの「エアキャップ・ホールディングス」(資本財・サービス)、ブルキナファソの鉱山開発にも携わる「アイアムゴールド」(素材)、カナダの「エクイノックス・ゴールド」(素材)、英国の「OSBグループ」(金融)などで、「S&P500」などで上位に並ぶ「エヌビディア」も「マイクロソフト」も「メタ・プラットフォームズ」などとは無縁にみえるポートフォリオだ。日本の「野村ホールディングス」や「本田技研工業」も組み入れ上位10銘柄に入っている。このポートフォリオの内容であれば、既存の「S&P500」や「全世界株式(オール・カントリー)」を保有している投資家が、分散投資手段の1つとして購入する効果も感じられる。設定から1カ月足らずで純資産総額は約450億円にまで拡大した。この人気が持続するか注目していきたい。
執筆/ライター・記者 徳永 浩