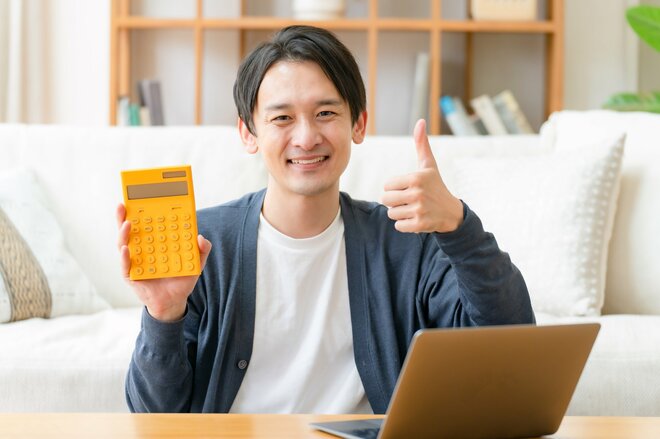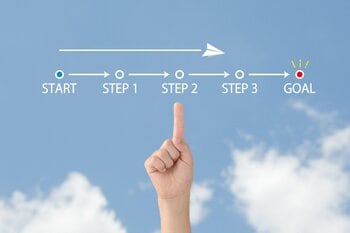老後の資産形成を支援するために作られた制度であるiDeCo(個人型確定拠出年金、イデコ)。
「節税メリットがある」と聞いたことがあるものの、具体的にどんなメリットがあるのか分からないという人もいるのではないだろうか。
そこでこの記事では、iDeCoのメリットについて簡単に解説する。
●前編『20年後に必要な老後資金は3500万円⁉iDeCo(個人型確定拠出年金)は インフレ時代の資産づくりに検討すべき?』
月額5000円から始められ、運用の手間は少ない
資産運用と聞くと「まとまったお金がないと始められないのでは」と敬遠する人もいるかもしれない。しかし、iDeCo(イデコ)ならそのハードルは思いのほか高くないともいえそうだ。例えば積み立てる金額(掛金)は月額5000円から可能で、1000円単位で設定できる。これなら資金に余裕がない人も始められるのではないだろうか。
iDeCoで積み立てできる商品は投資信託や保険、定期預金など。運用する商品と掛金額を最初に決めてしまえば、あとは毎月自動的に積立が継続される。手間がかかるのは最初だけで、あとは基本的に「ほったらかし」という人もいるほど。とはいえ、完全な「ほったらかし」は避けた方がよいだろう。年に一度、例えば誕生日などと日を決めて運用状況の確認をすることは心がけたい。
「所得控除」によって節税が可能
iDeCo最大のメリットと言えるのが、税金が年間で数千〜数万円ほど安くなること。会社員や公務員の方はご存じだろうが、生命保険料等を年末調整することで税金が戻ってきて、数千円から数万円ほど手取りが増えたという経験があるだろう。理屈は同じで、iDeCoでは掛金の全額が「所得控除」の対象となるので節税効果が期待できる。
この「所得控除」とは簡単に言うと一定の金額が所得から差し引かれることで、その分だけその年の所得税と次の年の住民税が安くなるというものだ。具体的にどのくらい安くなるかは条件によって異なるが、一例を挙げよう。
例えば年収500万円の人が会社員のiDeCoの掛金上限額である毎月2万3000円(年間27万6000円)をiDeCoで運用するなら、課税の対象となるのは500万円ではなく、500万円から27万6000円を差し引いた472万4000円となる。そのとき節約できる税金は年間で5万5200円に上る。
預金だと預けた額が多いからといって所得税や住民税が安くなることはない。しかしiDeCoであれば掛金額が多いほど節税効果も大きくなる。しかも掛金を出すのは1年だけではなく、長年にわたって節税効果が期待できる。