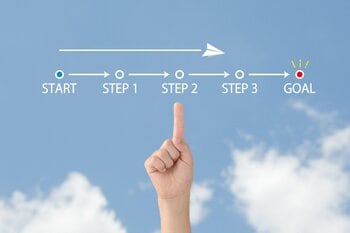みなさんは「老後2000万円」問題を覚えているだろうか。金融庁の金融審議会・市場ワーキング・グループによる試算で、高齢夫婦(無職)が公的年金をもらっていたとしても、毎月約5万円、老後30年で約2000万円もの資産の取り崩しが必要という内容だ。
物価高騰でもはや「老後2000万円」ではない?
老後2000万円問題が話題になったのは2019年のことだが、最近になって再度注目が集まっているのは物価高騰も背景の1つとしてあるかもしれない。実際、2024年11月の消費者物価指数(総合指数)の上昇率は前年同月比で2.9%。物価高騰が続けば、同じ金額で購入できる量が減る。つまりお金の価値が下がってしまう。
仮に2.9%の物価上昇率が20年続けば、現在100万円の資産をもっていても20年後には56万円程度の購買力にしかならない。言い換えると、もし20年後に老後を迎えるならば、豊かな老後生活には2000万円ではなく、約3500万円が必要になるかもしれない。
老後の資産形成のための制度、iDeCo
公的年金だけでは余裕のある老後が難しいならば、足りない分は自分で用意するしかない。しかし老後まで長い時間があるとはいえ、何千万円というお金を準備するのは容易なことではない。老後に向けた資産づくりをしっかりと検討する必要がある。
なかには、資産づくりなら預金でもよいのではと考える人もいるかもしれない。しかし今のような物価高騰時にはどんな金融商品でどう運用するかが重要になってくる。預金で運用するのもいいが、いくら金利が上がったとはいえ、2%を超える物価上昇率には適わない。
もちろん、日々の貯蓄は大切だが、資産を増やせる手段があればさらに心強いだろう。そこで、老後資金の形成を国が支援する制度であるiDeCo(個人型確定拠出年金、イデコ)の活用を検討することも一案だろう。
iDeCoは、毎月積み立てたお金を「預金・保険・投資信託」の中から自分で運用する資産を選択し、老後資金を作っていく私的年金制度。国民年金や厚生年金とは別に、「自分で掛金を払い、自分で年金を作る」ための制度、と言えばイメージしやすいだろうか。
iDeCoを利用して、例えば資産の一部を複数の企業の株式を投資対象とする「株式型」の投資信託(ファンド)などのリスク資産に振り向けることで、物価高騰から資産を守ることができるかもしれない。
iDeCoは20歳以上60歳未満で公的年金の受給要件を満たしている人(第2号被保険者など一部は65歳未満)なら原則加入できる非常にオープンな制度だ。なお、加入時や運用中に一定の手数料がかかるほか、投資信託のような価格が変動する商品に積立する場合は損失が発生するおそれもある。メリットやデメリット等を確認した上で利用を検討すべきだろう。
●「自分で年金を作る制度」iDeCoにはさまざまなメリットが存在する。中編『「節税できる」と聞くけれど…結局、iDeCoってどんなメリットがあるの?』にて詳細をお伝えする。