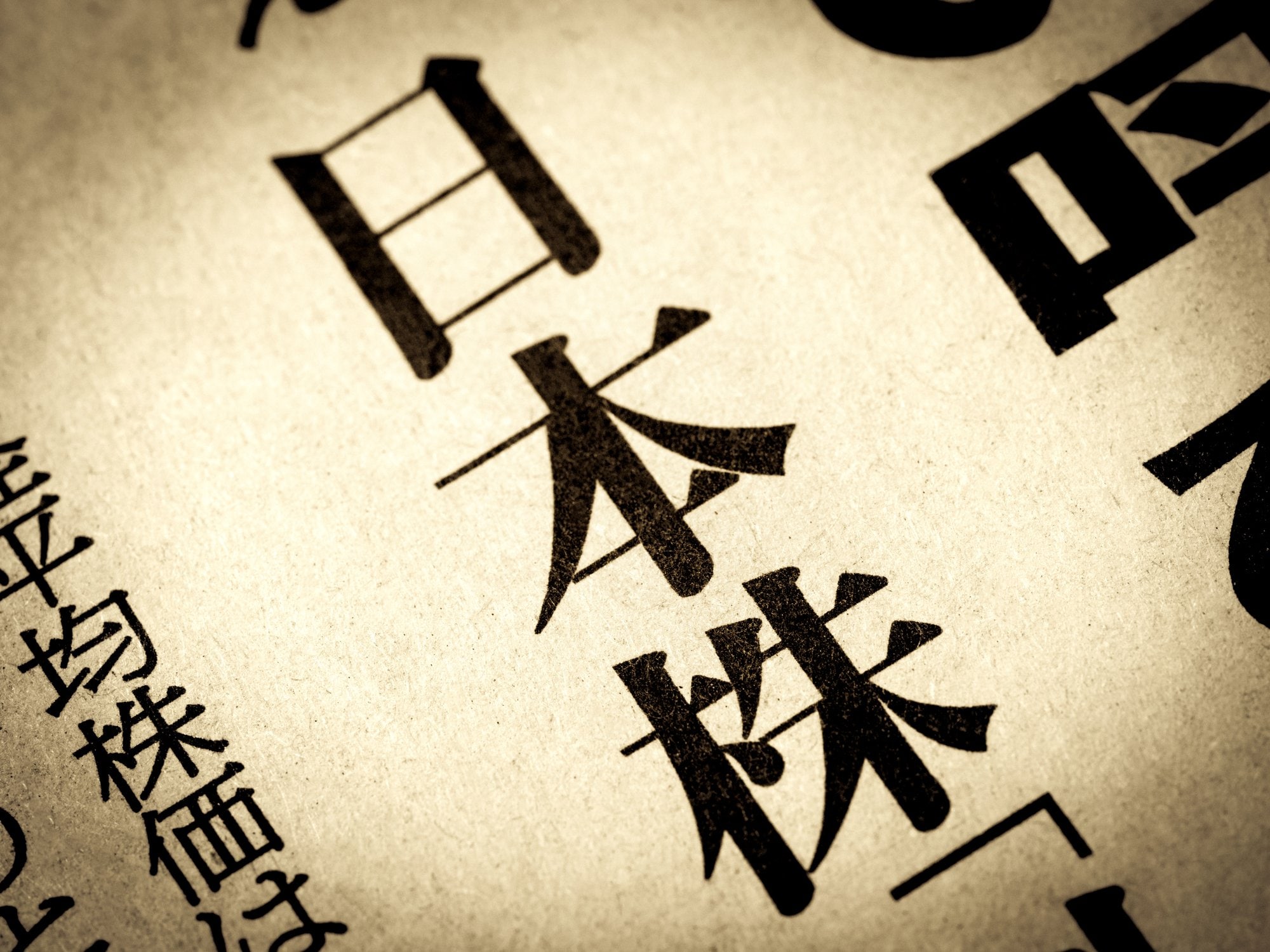※当記事は2025年7月4日(金)に行われた「アセマネOne 商品戦略フォーラム」内のセッション「トランプ政権の関税政策を受けた相場変動の振り返りと今後のマーケット見通し」を採録したものです。
保護主義的政策が揺るがす「米国一強」
投資家たちに地域・通貨を分散させる動き
村松 トランプ政権の誕生を理解する上で、無視できないのが経済のグローバル化の影響でしょう。産業革命や輸送革命に続く1990年代の通信革命に加え、1948年のGATT(関税及び貿易に関する一般協定)の設立や1995年のWTO(世界貿易機関)の発足、そして2001年の中国のWTO加盟を契機にグローバル化は一気に進展しました。この過程で各国のGDPは大きく成長し、特に1990年代から2024年にかけては新興国の経済成長が顕著となりましたが、その副作用として米国では製造業などの衰退が進み国民の不満が蓄積されました。この不満が保護主義的なトランプ政権の誕生、そして足元の関税政策へとつながったと考えられます。
そもそも米国は、バイデン前政権時代から独自の貿易政策を推進する動きを見せていました。WTOの紛争解決制度(※)の利用件数を見てみると2019年以降は大きく減少しているのですが、その背景には米国の反対があるのです。従来のようなグローバル経済の枠組みは通用しなくなってきていると言えるでしょう。
こうした背景もあり、トランプ政権は20世紀前半の保護主義的な経済構造を目指すような施策を打ち出していますが、かえって米国民の購買力の低下を招く可能性があるでしょう。米国の貿易収支は長期的に赤字が続いており、どこかで是正しなければならないものの、急激な関税引き上げという荒療治では従来の「米国一強」の経済構造が崩れドル安圧力が高まる懸念があります。すでに投資家の間でも他の地域や通貨への分散投資が進みつつあります。

このような環境下では、国や地域ごとの特性に応じた投資アプローチが重要になります。グローバル化による経済成長は今後も各国で緩やかに続くと考えられますが、投資家はリスク分散を意識し、特定の通貨や地域に依存しないポートフォリオを構築することが求められます。資産運用においては、多様な資産クラスを活用し、インフレヘッジや長期的なリターンを追求することが肝要です。
※編集部注:貿易紛争を解決するための手続きを定めた国際的なルールのこと。当事者である二国間の協議による解決が前提とされるが、それがかなわなかった場合にWTOが関与し、必要に応じて対抗措置を取ることなどが認められる。紛争解決制度はWTO加盟国間の貿易体制を支える柱の1つとなっている。
混乱乗り越え上昇局面続く
国内外の株式に刮目
酒井 今後のマーケット環境における有力な投資対象のひとつとしては、株式が挙げられるでしょう。関税問題による市場の混乱は見られましたが、すでに株価は大きく回復しています。特に、ナスダック市場を中心とするグロース銘柄など、当初最も下落したセクターが力強く戻している点は象徴的です。またバリュエーションの面でも、ナスダックこそやや割高感があるものの、他の市場では過熱感はなく、企業の財務体力も十分であるため、市場全体への影響は限定的と考えられるでしょう。さらに世界の株式市場の時価総額とEPS(1株当たり利益)の成長を示すデータでは、EPSの上昇に伴い時価総額も増加しており、市場は健全な上昇局面にあるといえます。

日本市場に目を向けても、本決算で増益を発表する企業が圧倒的に多くなっている点は印象的です。また企業による自社株買いが活発化していることも市場を支えていますし、TOB(株式公開買い付け)やMBO(経営陣が参加する買収)の増加も株価や指数を押し上げる要因となっています。基幹産業である自動車セクターは苦戦を強いられていますが、株式市場全体への影響は限定的と考えられます。
日本もインフレ国家の仲間入りした今
欧米投資家並みのリターン目線が必要に
村松 国内がインフレ環境に転じた今、インフレヘッジの概念が重要になってきています。過去20年間の金融資産のリターンを見ると、日本は平均1%(年率、以下同)、欧州は3%、米国は5%程度です。日本が米国のような高インフレ国家になるとは考えにくいものの、日銀が目標とする2%のインフレ環境下では、従来のような1%のリターンでは資産保全が不十分です。今後は欧州並みのリターンを目指す資産運用が求められるでしょう。
3%程度のリターンを目指すのであれば、投資先の国や地域は時期に応じて選択する必要はありますが、相対的に期待リターンの高い株式を中心に据えた運用が有力です。また国内株式・債券、外国株式・債券の伝統4資産の組み合わせは、初心者から年金基金まで活用できる基本的なポートフォリオの考え方として今後も通用するでしょう。個人投資家であれば国内債券の代替として定期預金を活用することも選択肢となります。
より積極的に3%超のリターンを目指すのであれば、さらに多様な資産クラスへ投資することも検討に値するでしょう。例えば米国では、未公開株式や不動産といったプライベート資産が個人投資家のポートフォリオの15%程度を占める例も見られます。日本でも市場の発達により投資対象が広がりつつありますので、こうした選択肢を積極的に検討することが重要です。
ここまで述べてきたとおり、米国以外の地域にも投資先を分散させる必要性が高まるという変化が生じる一方、今後も変わらない点として資本主義経済の恩恵を受けられる株式投資の有用性が挙げられることを最後に強調しておきたいと思います。もちろん金利上昇を受けて30年物日本国債利回りが3%前後になるなど債券投資も有力な選択肢となりますが、インフレヘッジの観点を踏まえて3%以上のリターンを目指すのであれば、株式はポートフォリオを支える重要なパーツとなるでしょう。