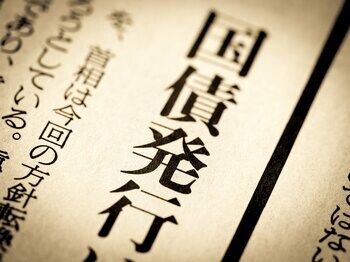日本の生産性が低くなった原因
こうした低成長は、企業の生産性が上がらなかったということでも説明できる。
たとえばコロナ禍のゼロゼロ融資などはその典型例だろう。ゼロゼロ融資とは、コロナ禍の影響を受けた法人および個人事業主に対して実質無利子・無担保で融資する制度のことだ。民間金融機関は2021年3月まで政府系金融機関は2022年9月まで新規の貸付を実行していたので、1年から1年半の間、貸出が継続されていた。3年間は実質無利子であったことに加え、返済が遅れた場合でも元本の8割以上、場合によっては全額が信用保証協会によって保証される仕組みも付与されていた。そのため中小企業庁によると、2022年6月末時点での同融資総額は42兆円にも上った。
これだけの融資額をどう返済するか。返済が滞りがちになることは十分に想像できた事態である。信用保証協会からの代位弁済が増えることに加え、民間金融機関から見れば信用保証協会の保証でカバーされないプロパー貸出分が貸倒れになるリスクもある。
ゼロゼロ融資は、まさにその場しのぎにすぎず、コロナ前から事業の継続性に問題があった企業まで、混ぜこぜにして生き長らえさせてしまった点において悪手だった。いわゆるゾンビ企業が、そのまま残ってしまったのだ。
ゾンビ企業の存在は、日本の生産性を低くした原因の一つだ。そもそも生産性の低い企業は収益が上がらない。収益が上がらなければ社員の給料を増やすことができず、そこで働く従業員はカツカツの生活を強いられる。それでもクビになるよりはマシという選択がされ続ければ、「賃金が上がらない→消費を手控える→物価が上がらない→企業の売上・利益も変わらない→賃金が上がらない」という悪循環に陥る。これが構造的な低成長の遠因になっていることは間違いないのではないか。
このように考えると、低成長を脱するための処方箋として指摘できるのは、価格転嫁の仕組みをしっかり構築しながら、生産性の低い企業には退出してもらうことである。日本がしっかりした成長軌道を確保できれば、為替レートが円安一辺倒になることはない。経済の成長に応じて賃金と物価の好循環が起こり、金利も今以上に上げられる基礎ができる。