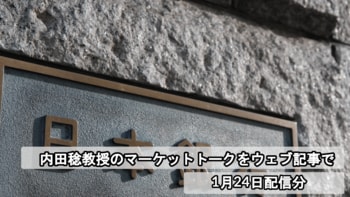通年で見ると、日本人の海外旅行敬遠ムードは続いている…円安と「高い海外」が原因か
とはいえ、通年で見ると、日本人の海外旅行者数は、まだまだ回復の途上にあります。
JTBが今年1月に公表した「2025年(1月~12月)の旅行動向見通し」によると、海外旅行の旅行者数は1410万人で前年比8.5%増という予想が出ています。
観光庁のデータによると、2024年中における日本人の出国者数は1301万人でした。2023年の962万人から見て35%増であり、また2025年中が予想通りに1410万人であれば、8%増になりますが、仮に1410万人に到達したとしても、過去の数字からすれば、回復の途上であるとしか言いようがありません。
ちなみにコロナ禍になる前の2019年における出国日本人数は2008万人でした。つまり1410万人を達成したとしても、2019年比で見れば約30%も少ないのです。コロナ禍前をさらにさかのぼって、出国日本人数が1410万人よりも少ない年は、2003年の1330万人です。
コロナ禍が終わってからも、日本人の海外旅行が今ひとつ盛り上がっていないのは、やはりこの数年で加速した円安の影響が大きいと考えられます。
それと同時に、「安い日本」が定着していたことも、日本人による海外旅行が盛り上がりに欠ける、もう一つの要因といっても良いでしょう。
かつては、日本から海外に出かけると、「海外の物価は安い」という印象だったのが、バブル崩壊後、長年にわたってデフレ経済が続く一方、経済が順調に拡大した海外諸国では緩やかなインフレが続いたこともあり、日本との物価の差が大きく拡大しました。それは冒頭で説明したように、ニューヨークの大戸屋と、銀座の大戸屋の価格差にも現れています。
三井信託銀行が発行している「DC通信(2024年11月28日)」の「日米の物価格差を考える」というレポートによると、1999年12月を100として日米の消費者物価指数を比較すると、2024年9月時点で日本が111.7であるのに対し、米国は187.3です。
加えて、ここ数年の円安による影響を加味して、米国の消費者物価指数を円ベースで計算し直した数字もありますが、それは何と261.3にもなっています。これでは日本人の海外旅行熱がなかなか高まらないのも当然でしょう。
ところで、米ドルベースの米国の消費者物価指数と、日本の消費者物価指数との差は、2024年9月時点で1.67倍です。一方、大戸屋のしまほっけ定食の値段を比較すると、1米ドル=140円で換算したとしても、ニューヨークが3640円で、日本が1130円ですから、3.2倍もの差があります。
消費者物価指数の日米差が1.67倍であるのに対し、円ベースに換算した、しまほっけ定食の価格差が3.2倍というのは、やはり物価か為替レートのいずれかがゆがんでいるからであり、そうである以上、そのひずみは米国の物価下落か、もしくは円高進行のいずれかによって修正されるものと考えられます。