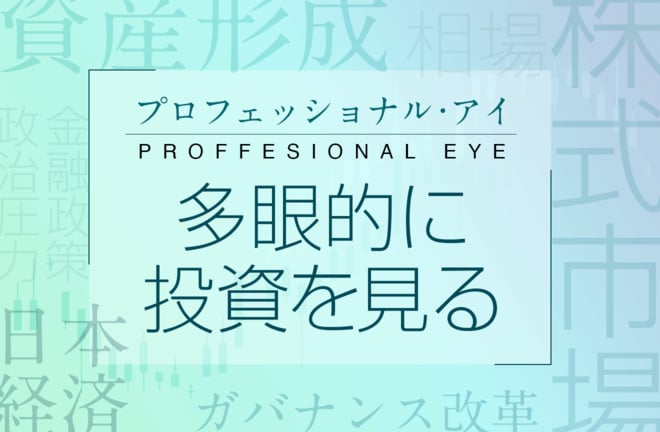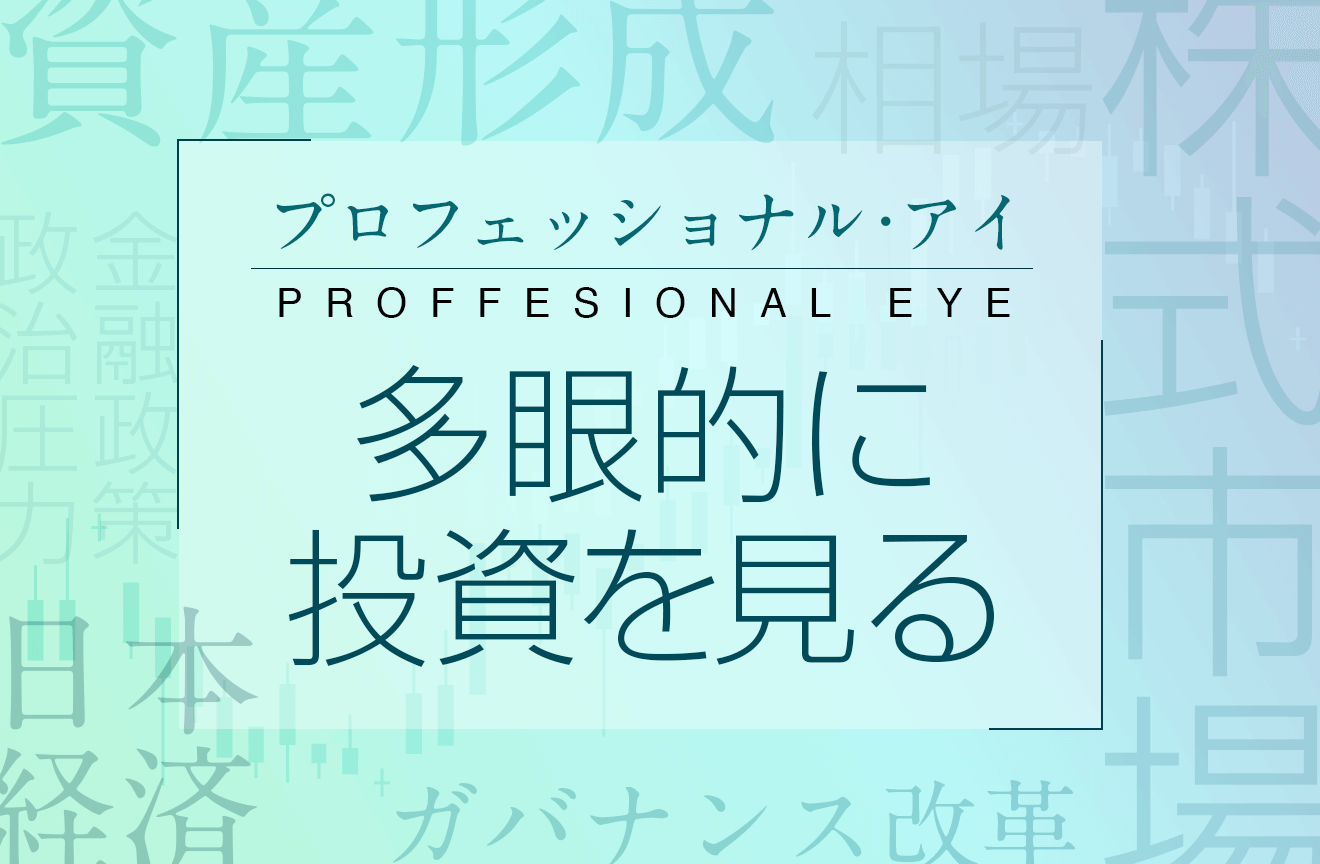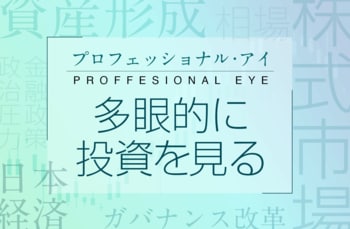「自称・交渉の達人」トランプ大統領の誤算、今後の米国経済に注目
法外に高い相互関税は悪手
4月2日に米国は、ショッキングなほど高い相互関税を発表した。同盟国である日本は24%、中国は145%、ロシアは0%だった。
この手口は悪手だった可能性が高い。理由は大きく分けて2つある。
1つは、同盟国を敵に回したことだ。相互関税の目的が中国封じ込めではなく、モンロー主義*の伝統に基づく孤立主義への回帰ではないかという疑念を抱かせた。となれば、同盟国との防衛費負担にしても、いざ本当に戦争になれば米軍は戦わずに真っ先に逃げるのではないか、という疑念を抱かせた。
もう1つは、最初に高関税を吹っ掛ければ、相手が折れると過信した。これから各国は米国と交渉に入るが、関税は下がるのが確実視されている。問題は145%の関税が発効した中国だ。米国の輸入業者は、関税が下がるまで輸入を止めて待つだろう。2週間後には米国内の小売りの現場で品薄となり、物価押し上げ要因になり始めると見られている。
交渉の達人を自認するトランプ大統領にしては、初歩的なミスをしたと言える。この過程で関税に関するトランプ政権内の力関係は、強硬派のラトニック商務長官や関税率の計算式で出鱈目な結果を出したナバロ大統領顧問から、穏健派のベッセント財務長官らにシフトした。強硬派のラトニック商務長官は辞任のタイミングを見計らっているとみられている。
*モンロー主義:1823年にアメリカ第五代大統領ジェイムズ・モンローが連邦議会での演説で発表した外交政策の原理。アメリカ合衆国がヨーロッパ諸国に対して、アメリカ大陸とヨーロッパ大陸間の相互不干渉を提唱した。
グローバル・リバランス路線への回帰
米国からみて相互関税で押して無理なら、他の手段で引くのが得策だ。
4月23日に穏健派のベッセント財務長官は、国際金融関係者の集まりで「米国ファーストは米国の孤立を意味しない」、「米政権は中国とのリバランスを支援したい」と発言して、悪手の火消しを始めた。リバランスとは、昨年に訪中したイエレン前財務長官が中国に持ち掛けたグローバル・リバランス路線への回帰だ。中国経済は過剰投資で外需に頼る一方、米国経済は過剰消費で輸入に頼る構造になっている。米中の貿易不均衡はその結果であり、根本的な原因を改善しようというのがグローバル・リバランス論だ。しかし、これは口実だろう。単なる関税「引き下げ」合戦では格好がつかないため、先に米国から折れることを糊塗して現実路線への回帰を呼びかけたと理解できる。もしグローバル・リバランス論が本当なら、中国だけでなく日本やベトナムも対象となる。
これはある意味でトランプ政権には屈辱だ。前バイデン政権を否定して法外に高い関税で攻めたのに、このままでは自国経済が苦境に陥るのが明白になったため、攻め手を切り替えた。しかも、その中身は悪く言えば前政権の「パクリ」なのだ。
米国に弱み
相互関税によって、米国の物価は上がることが確実視されている。中国は輸入シェア第1位で関税率145%だ。物価に与える影響度は圧倒的に大きい。中国は、待てば待つほど交渉で優位な立場になると見られる。さらにウクライナ支援に必要な武器弾薬の製造には、中国から輸入するレアアースが必要不可欠だが、現時点では実質的に差し止められている。ウクライナ和平で、ロシアはじらし戦術を採用することで交渉において優位に立っているが、同じことが関税交渉で中国に当てはまる。
他方、輸出が停滞する中国も苦しい立場にあることに変わりはない。米国での輸入品の品薄とは正反対に、モノが余っている。関税引き下げの合意に向け、協議に入るのは時間の問題だろう。
景気と株価への影響
景気後退の最終局面では、底が深ければ深いほど、景気対策が大きくなる期待から株価は大きく反発する傾向がある。今後の米国経済の行く末は、中国をはじめ各国と関税でどう折り合いを付けるかで決まる。米国経済の落ち込みが早くて深いほど、米国は関税で大きな譲歩をすることになるだろう。結果的にこれは景気対策と同等の効果を持つことになると見込まれる。
■関連リンク:
りそなアセットマネジメント マーケットレポート内「黒瀬レポート」https://www.resona-am.co.jp/market/report/#tabSwitchC03
〈当記事に関するご留意事項〉
·当記事は、投資環境や投資に関する一般的事項についてお伝えすることを目的にりそなアセットマネジメント株式会社が作成したものです。
·当記事は、投資勧誘に使用することを想定して作成したものではありません。
·当記事は、当社が信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
·運用実績および市場環境の分析等の記載内容は過去の実績および将来の予測であり、将来の運用成果および市場環境等を示唆・保証するものではありません。
·りそなアセットマネジメント株式会社が設定・運用するファンドにおける投資判断がこれらの見解にもとづくものとは限りません。
·当記事に指数・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権、その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
·当記事の記載内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。