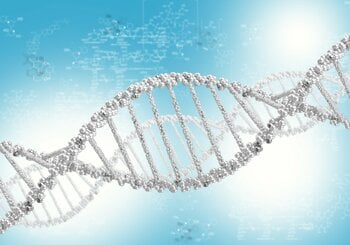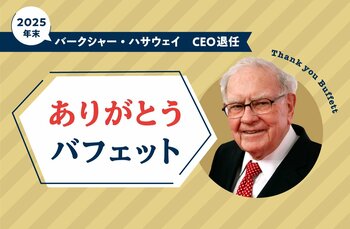「90日間延期」に対して、株価は大幅反発で反応
まさに朝令暮改ですが、これをマーケットはどのように受け止めたのでしょうか。
株価は大幅反発しました。発表された9日のS&P500は、前日比9.52%の上昇。10日の日経平均株価も前日比で9.13%の上昇でした。
関税が大幅に引き上げられた時、まずその影響を受けるのは、海外から高い原材料・製品を輸入しなければならない米国企業です。
米国商務省が2024年6月に発表した2023年の貿易統計から、輸入額の比率が高い順に並べると、
資本財・・・・・・27.9%
消費財・・・・・・24.6%
工業用原材料・・・・・・21.9%
自動車・同部品・・・・・・14.9%
食料品・・・・・・6.5%
その他・・・・・・4.2%
となっています。
もう少し具体的に言うと、資本財にはコンピューターおよびアクセサリー、半導体、民間航空機エンジン、電気機器、医療機器、通信機器が含まれます。
消費財は医薬品、携帯電話・その他日用品、繊維衣料品・日用品、玩具・ゲーム・スポーツ用品、家具・家庭用品が、そして工業用原材料には原油、燃料油、プラスチック、天然ガスが含まれます。
相互関税が課せられると、それらを輸入して製品・サービスを生み出している米国企業にとってはコスト高要因になるため、企業収益が圧迫されます。もちろんコストを全額、消費者に転嫁できれば、企業収益への影響も軽微で済みますが、今度は米国国内でインフレ懸念が浮上します。それらは米国経済にとって、必ずしもプラスではありません。トランプ大統領が就任した直後から、米国10年国債の利回りが低下傾向をたどったのは、相互関税の発動が、米国経済の成長率低下につながることへの懸念の現れでした。
ちなみにトランプ大統領が誕生したのは1月20日の就任式でしたが、米国10年国債の利回りは、1月14日の4.792%をピークに下がり続け、4月4日には3.999%まで低下しています。
これは景気のスローダウンを織り込む動きです。だとすると、9日に発表された相互関税の90日間停止と個別交渉による関税率の見直しは、先行き不透明でリスクオフ状態になっていたマーケットからすれば明るいニュースであり、だからこそ株価が急騰したと考えられます。