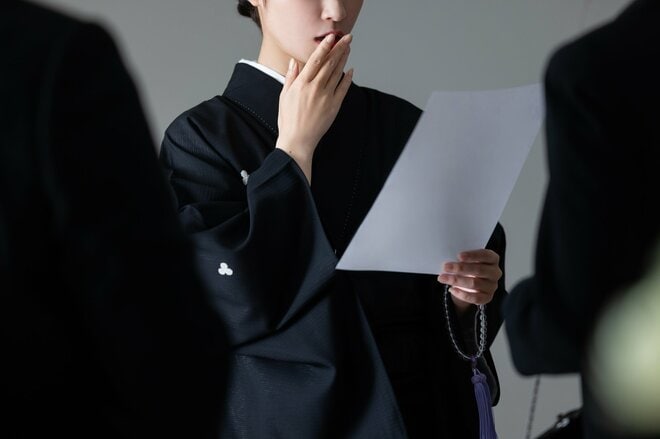薄明かりの差し込むリビングには、拓郎の衣擦れの音だけが漂っていた。
壁際に置かれたデジタル時計は午前4時。そろそろ出発の時間だ。
拓郎は使い慣れたバックパックに機材を詰め込み、肩に背負うとそっと寝室を覗いた。ベッドの上で規則正しい寝息を立てている妻の悠里。拓郎はふっと微笑むと小声でささやいた。
「行ってくるよ」
当然返事はない。拓郎はそれ以上何も言わず、静かに寝室のドアを閉めて玄関へ向かう。愛用の一眼レフなどの機材が入ったキャリーケースの重量感を確かめ、やはり静かに家を出る。
今年42歳になった拓郎は、いわゆるフリーカメラマンだ。細々ではあるが、夫婦2人、十分に食べていけるだけの仕事を得ながらなんとかやっている。
「まだ暗いな……」
ふと青く染まった早朝の街を眺めてつぶやく。毎日見ているはずの光景も、時間が違えば新鮮な刺激を拓郎の感性に与えてくれた。
拓郎は白い息を吐き、鞄から取り出したカメラを構える。朝の澄んだ空気の隙間に、軽やかなシャッター音が差し込まれる。