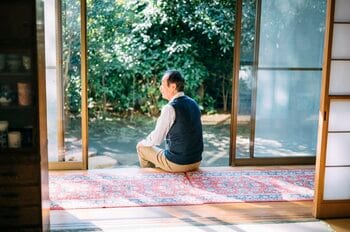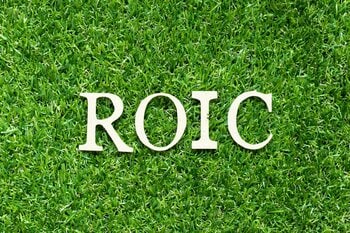すでに、金融資産から得られた所得を含めての保険料を算定されている人はいる
今回、「医療・介護保険における金融所得の勘案に関するプロジェクトチーム(PT)」の初会合で、厚生労働省が示した検討案で騒ぎになったのは、公的医療保険や介護保険の保険料を計算する際の基準となる所得に、働いて稼いだ給料などの所得だけでなく、保有している金融資産から得られる運用収益(=金融所得)も含めるべきだという意見が浮上してきたからです。
要するに、株式の取引などによって得られた値上がり益や配当金を、医療保険や介護保険の保険料を算定する際の基準となる所得に反映させようという話です。これを額面通りに受け止めると、それこそ冒頭のコメントではありませんが、「せっかくNISAで得た利益にまで課税するつもりか」的な批判を引き起こすことになります。
ただ、ここは少し冷静に考えてみる必要がありそうです。
実は現時点においても、金融資産から得られた所得を含めて医療保険や介護保険の保険料を算定されている人もいます。具体的には、株式投資で得た利益を確定申告している人たちです。対して、特定口座によって株式投資で得た利益を源泉徴収にしている人は、その利益は保険料に反映されていません。つまり同じ株式に投資しているのに、確定申告しているか、していないかによって、保険料に差が生じてくるのです。
当然、確定申告している人たちには、それをする理由があるのですが、医療保険や介護保険の保険料を多く負担しているという事実があり、そこにはどうしても不公平感を拭い去ることができません。その不公平感を正すのが、今回のプロジェクトチームに課せられたミッションになります。
2028年をめどにしてその改正作業が行われる予定ですが、実際に保険料算定にあたって金融所得が勘案されるようになると、特に源泉分離課税を選択して株式などに投資している人たちの医療保険、介護保険の保険料は値上げされる可能性が高まります。