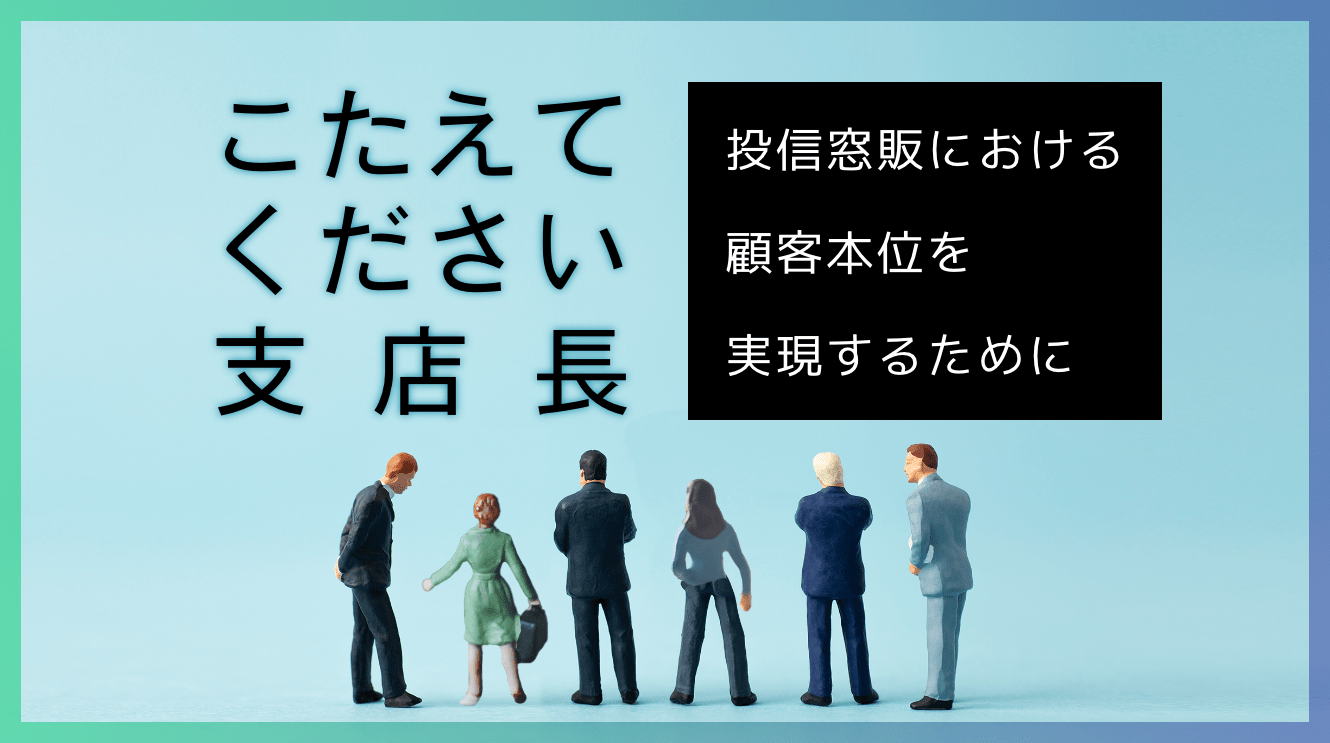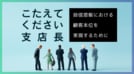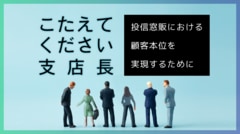Q:職員「支店長! 業績を上げるためにFP資格は必要ですか」
A: 支店長「昇進昇格の条件にもなっていますから、ぜひ資格を取得してください」
森脇's Answer:
FP資格を取得したほうが良いかと問われたら、筆者は「勉強は何でもしたほうがいい。よってFP資格を取得するのも良い」とお答えします。金融機関の役職員は常に学習し続けることが必要です。業務の範囲は広く、また時代の流れに合わせた対応が求められるので、学習しつづけなければ良い仕事ができないと考えています。もちろん、それは資格取得に限った学習を意味しません。資格取得のために学習することは良いとは言っても、ただ取得するだけでは意味がないわけです。
しかし実際には、資格を取得している職員は多くいるものの、残念なことにそれを現場で生かしている人は少数であるようです。
その理由は二つです。一つは、資格取得そのものが目的化していることです。上記の支店長の回答にもある通り、多くの金融機関で資格取得が昇進昇格のための必須要件になっており、そのために学習するという姿勢が強く、実務に生かすという本来の学習の意義が見失われがちです。
もう一つは、業績評価が自身の担当業務内の限定された範囲で行われるため、学習したことを生かして仕事の幅を広げていく意欲が湧きにくいことです。担当業務以外で成果が上がったとしても、その評価が低いかあるいは全くされない、ということがあると、他に適した提案が考えられるにもかかわらず自分の評価としてカウントされる契約を受託することに専念し、それ以外の顧客ニーズを切り捨てることが少なくないのです。
このように資格やそれに伴って習得した知識を生かす態勢が整っていない状況において、資格取得の意義について問われれば、「資格取得は意味がないですよね」と答えざるを得ません。しかし本来ならば、自分のスキルアップを図りたい、提案の幅を広げたいという動機があるはずで、そのための知識習得・学習であり、資格取得はその手段の一つです。そうであれば、FPをはじめとする資格取得のための学習には意義があります。
お客さま対応の幅を広げるのに有効
FP試験は6分野(ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継)の学習が必要です。金融機関で扱う金融に関する提案は幅広いものですが、自分の担当業務の範囲を超えるもの、また自金融機関の取り扱い範囲を超える内容も含まれます。
学習が実際の業務に生きてくるのは、お客さまのご要望や抱えている問題について、お客さまが発した言葉に表面的に対応するだけではなく、あらゆる情報を踏まえて背景にある潜在ニーズにアプローチする場合です。また、自分の専門分野外の対応が必要な場合には、他の担当部署につなぐことができます。自金融機関では取り扱いがない業務であれば、どこに相談すれば適切なのかといった案内もできます。
例えば、遺族年金や障害年金の計算方法が頭に入っていれば、お客さまの相続や事故などが発生した瞬間に概算で計算して、今後のキャッシュフローの状態を想定して話を進めることができます。“いざという時”に備えたいとおっしゃるお客さまには適切な保険が検討されるでしょう。個人名義でアパートを所有する大家さんとの会話でお子さまへの相続対策についての話になったら、相続や贈与、不動産等々の知識をフル稼動させます。法人格を持つ中小企業の社長が相続対策をしたいとおっしゃる場合には、会社の株式の保有状況やその評価方法などが学習した知識として引き出され、考慮すべき点、自金融機関でお手伝いできる業務の範囲などが想像できるでしょう。
お客さまの言葉や状況を踏まえてより深く推量し、自分や自金融機関以外の手段もご案内できるようになれば、プロとして信頼されるようになります。そうなれば、お客さまは実にさまざまな事柄について相談してくるようになります。お客さまの自己開示による精度の高い情報が多く取得できれば、その情報を活用してよりよい提案、付加価値の提供につながります。結果として、金融機関で取り扱う金融商品であればその全てを自金融機関にお任せいただけるようになり、さらには家族取引も依頼され、契約が次から次へと舞い込むようになるでしょう。
資格とその活用について、いかに評価するか
資格とその知識がお客さま対応に役に立つことを確認しました。ではその上で、支店長など管理者は、資格取得を現場職員に促すべきなのでしょうか、促すとしてそれをどのように評価すべきなのでしょうか。
資格取得を促すのであれば、資格とその知識を生かして、幅広いお客さま対応を実践したことをしっかり評価する仕組みが求められます。金融機関は定量評価に偏りがちだと思いますが、資格をどのように活用して日々の業務に生かしているか、その仕事ぶりを定性評価することにもそれなりの重きを置いた評価体系を検討してほしいと思います。他部署といかに連携しているかを測ることで、お客さまへの総合的な提案を行なっているかを見ることも可能でしょう。
このように評価方法を工夫することで、資格取得と結びつくお客さま対応力の向上や、それに向けた職員の動機付けを期待することができるでしょう。昇進昇格の条件の一つになっている、といった形式的な評価だけでは、前述の通り資格取得が単なる目的化してしまいます。
部下の資格取得状況が支店長の評価に影響を及ぼす金融機関もありますが、支店長が自身の評価を気にして資格取得を促していれば、そのような姿勢は部下には見透かされるものです。知識を習得する結果、お客さまにより良い提案をする可能性が高まるという本来の資格の意義について確信していてこそ、部下に資格取得を促すことができると思いますし、支店長自身が広い知識を身につけていてこそ、部下の仕事ぶりを正当に評価できるのではないでしょうか。
評価体系は組織全体の課題であり、支店長がすぐに変えられない面もあるでしょう。それでも、支店長には現場職員に声をかけるという、とても意味のある働きかけができます。評価とは、必ずしもシステマティックに実施されるものだけではありません。日々声をかけつつ現場の取り組みを見て、経営者として評価し、感謝の気持ちを伝えてみてください。そのような支店長の思いやりを、現場の職員は好意的に受け止め、強力なモチベーションへとつながるでしょう。