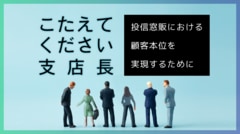学校教育からみる学びの要素
学びの基本をシンプルに考えるとき、例えば、子どもの教育を振り返ってみて欲しい。6歳の小学校1年生が高等学校を18歳で卒業するとき、「学びを得て、成長できた」度合いの内訳は、学校での「実習的な授業(OJT)」と「座学の授業・宿題(OFF-JT)」だけであっただろうか?違うはずである。家庭で両親と世の中の様々なできごとや将来の夢を語り合う中で「勉強しなくては」という意欲が生まれていただろう(=目標設定)。学校においては、一定のサイクルで必ずテストや成績の通知があり、その結果、教師に褒められる(クラスメイトと競い合ったり、家庭ではおこづかいをもらえたり、もあったかもしれない)ことで自己承認を高めていただろう(=評価・報酬)。
将来のゴールが決まっていない子供は、潜在性を広く伸ばす“成長”の基本サイクル(①目標設定、②OJT・OFF-JT、③評価・報酬)の中で、当然のように育ってきた。これが企業組織に入ると、突然②のOJT・OFF-JTを押し付けられる。そして往々にして、①目標や③評価が伴っていないのである。キャリアに入った社会人は再生産が中心になりがちだが、実際は子どもと同様、やはりゴールがきまっていない。学ぶ=お客様として学習機会を享受する、ではなく、スキルアップを自己投資として昇華させつつ、それを社内でどう発揮するかで対価を得てキャリアアップをしていくことで適正な還元が行われるといった組織・個人双方の意識変革が必要である。
社会人の学びは、子ども時代のように「家庭」がサポートしてくれるものでもない。「教わり・学ぶ」以前に、「稼ぐ」ことにフォーカスするのも当然だ。だからこそ、企業は育成の基本サイクルを連続的にカバーできるように仕組みを用意してあげる必要がある。
新時代の育成における”個の活用”
今日、ビジネスの成長という点では、日本はかつてに比べ他の先進諸国に先を譲っている感はあるが、スポーツ界における日本人選手の活躍は目覚ましい。ここに育成転換のもう一つのヒントがありそうだ。
ひと昔前は、共通的に高負荷なトレーニング、一律な方法論でパフォーマンスを上げることにより、持久力の高い選手をつくろうとしていた。しかし画一的な技術の追求では限界があり、世界に通用する水準の個人を作れないことがみえてきた。さらには上意下達・徒弟的な指導関係の成れの果てとして、暴力やハラスメントといった問題も顕在化したように思う。
その後、現代のスポーツ業界では、個性を活かしたチーミングと自発的なトレーニングを促すコーチングが推進されているようだ。「プレイヤーズセンタード」いった考え方で、スポーツの主役はプレーヤーであり、スポーツ指導者自身の考えを一方的にプレーヤーに伝えるのではなく、気づきを促し、成長に導いていくコーチングを目指すというものである。コーチは俯瞰的な視野で、スポーツの価値やスポーツの未来への責任を理解した上で、常に自らも学び続けながらプレーヤーの成長を支援する。
ここで、成長の基本サイクル(①目標設定 ②OJT・OFF-JT ③評価・報酬にもう一要素を付け加えたい。④アスピレーションの活用である。上司が部下に一方的に指導する詰め込み型の教育ではなく、一人ひとりが意思をもってスキル向上に取り組めるよう、周囲が働きかけるようなやり方が現代のビジネス界においても求められているのではないだろうか。
【落とし穴】そもそも育つ気がない社員たち
では、①~④のサイクルを順当に回せば社員は育ってくれるのか?残念ながらここには日本特有の大きな落とし穴がある。前回の(臨時特集)においても少し触れたが、諸外国と比べ日本の社会人は学びへの意欲・関心が極めて低く、実際の行動結果も伴っていない。例えば、勤務先以外での自己研鑽について、日本は「とくに何も行っていない」割合が極めて高く52.6%(各国平均は18%)にものぼる上、自己投資意欲も最下位という調査結果が興味深い(※2)。総務省の「社会生活基本調査」によると、雇用されている人の週あたり自己研鑽(学習・自己啓発・訓練)時間は、わずか7分という驚きの結果である(※3)。
なぜこんなにも、日本人は企業の外で学ばないのか。厚労省の「能力開発基本調査」によると、正社員が自己研鑽を行っていない理由として「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」が突出している(※4)ものの、労働時間についてはここ10年で1割近く減少している上、諸外国と比べて日本の労働時間はむしろ短いともいえる(※6)現状を鑑みると、必ずしも「日本人は仕事が忙しい」が真の事由ではないように見受けられる。
この問題を紐解くだけでも相応の考察が必要であるが、組織・個人双方にリスキリングの習慣がなかった(「育成しない」ことの習慣化)が根深いように思われる。組織側は、古くから続く新卒一括採用・ジェネラリスト育成・終身雇用の中で、「入社した右も左も分からない社員こそが、育成の対象」「現場で上司の背中を見て経験を積み、色々覚えてもらえば良い」「その経験値をもって年功序列で登用していく(シニア層に学びを押し付けるのは失礼)」といった価値観や仕組みが確立し、抜け出せなくなっていたことが考えられる。この仕組みの中では、欧米のように「社会に出てから大学に入り直す」といった、一時的にでもキャリアのルートから外れることを許容しづらかった。
社員側は、この価値観が蔓延する組織の中で「仕事で必要なことは教えてもらっているし、よほどのことがないと解雇もされない。だから、他に何もしなくて良いといった意識が慢性化し、デジタル技術の発展を横目に見ても専ら娯楽として消費するばかりで、自らビジネスへ活かすための努力をしようというモチベーションにつながらないのであろう。
ここでは、日本特有の「組織・個人双方が育成にコミットしづらい」状態から脱却し、成長の基本サイクルを効果的に回すポイントを解説する。
①目標設定 「いま(もう一度)、変わることの必要性を実感する」
トップダウンで目標を押し付けるのではなく、対象者や関係者の内発的な動機付けを促すという考え方だ。特に中高年層は過去に(紙からシステムへの移行など)“分かりやすい”転換を経験しているからこそ、足許の変化を認識しづらいかもしれない。時代の変化に伴う企業・個人の変化の必要性について、企業の方から説いた上で、個人の目標意識にまで落とし込むことが必要だ。
②OJT・OFF-JT「コーチ任せの授業に頼るだけでなく、専門家も活用する」
変化と多様性の時代において、徒弟的な現場教育も、紋切的なカリキュラム運営も、過去のものとなりつつある。にもかかわらず、かつての習慣を引きずり、現場のエース社員を指導者(コーチ)としてすべてを丸投げしたり、人事部にあらゆるOFF-JT計画を設計させたり、といったことは荷が重すぎる。機能ごとに役割を分化させ、自社で難しいことは外部も頼るべきだ。
③評価・報酬「しがらみに捉われず、新しい枠組みを導入する」
ゴールが明確でない(決まったモノを作れば良い、が終焉した)産業の世界で、「親方・先輩に認められれば(あるいは、テストが満点ならば)及第・昇進」といった従来の枠組みでは個人の成長を図ることは難しい。新しい価値観を取り入れた柔軟な評価の仕組みをつくることが肝要だ。ハレーションが大きく移行が難しい場合には、DX領域を切り出して特別な認定や報酬を過渡的に設けるのも良いだろう。
④アスピレーションの活用「“従業員中心”を周囲がサポートする」
人的資本の重視や個の尊重が謳われる中、「従業員“第一”」という名目で実質「従業員へ“一任”」しがちだが、複雑・難解なDXの世界において、独りで成し遂げられることはほぼないといえる。あくまで「従業員“中心”」に据えながら、チームとして相互学習ができる仕組み・風土や未発現の個の関心を引き出す働きかけといった(かつて親や学校がやっていたようなことを)企業が用意してあげることが肝要である。