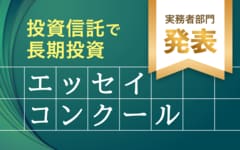解決のカギ その1 求める人材像の「解像度」を上げる
課題解決のカギは、求める人材を正しく定義し直すことだ。必要な「DX人材」は企業にとって千差万別である。人材像の解像度が低いまま、「何となくデジタルも変革もできるスーパーマン」を探している経営者は多いが、そのようなタレントはめったに存在しない。やみくもに(従来の枠組みで)優秀と評価されていた人材を選抜したり、漠然と「DX」のお題を掲げて現業と関連のない研修を導入したり、「デジタルラボ」と称して閉塞的な環境のみでトライさせたりといった手法でうまくいっている例は極めて少ない。
まずはシステムアーキテクチャーの刷新やクラウドサービスへの移行を進めるべきだ。そのためにも、仕事をするうえで必要な投資と配置に沿った組織のなかで、持つべきカルチャーと価値観に合致するデジタル人材の姿を定義し、その人材と仕事とを結びつける試みが必要になる。その際は、「ジョブ型」への移行は不可欠となる。高いスキルを持つ多様な人材を確保するためには、漠としたお題目に留まらず、求めるケイパビリティ(遂行するためのスキル・前提となる知識、経験)を細分化して社内外に打ち出していく取り組みが必須だ。
人材像の解像度を上げるべきだという意味でいえば、DX人材とグローバル人材はよく似ている。1990年代半ばにグローバル資本主義の進展・インターネットの普及によってグローバリゼーションが一般化し始めた。しかし日本社会が「グローバル人材」の必要性に気づき、それを提唱し始めたのはおよそ10年以上が経過した2010年ごろであった。
当時も各社こぞって「グローバル人材の獲得」に力を注いだが、「そもそも語学教育が不十分」「とりあえず海外に送り込んだが、パフォーマンスできず帰国」といった初期のつまずきから、何とか語学力の底上げをしても「グローバル展開の戦略・案件がそもそも不足」「英語堪能な人材を増やしたが、ビジネスにコミットしてくれない」といった具合であった。
今となっては、「グローバル人材」という曖昧なレッテルを使い続けている企業はほぼ存在しない。「企画力」「変革力」といった本来ビジネスに必要な行動指針やコンピテンシーに立ち返っていることが多い。そもそもハードスキルである「語学力」は短期間で習得できるものではないため、より若年期からの必修が義務化されたことは記憶に新しい。
解決のカギ その2 役割の明確化を
時代の潮流に乗ろうとして足りない人材をやみくもに追いかける「負のループ」から脱却するためのカギは、スキルの不足に注目するのではなく、そのスキルで何をさせたいのかを明確にすることである。十分な勉強の時間が取れなかったり、年齢的に多くを吸収できなかったりする中堅・ベテラン層に、本業の片手間で新技術を学ばせ、それを全く新しい形でビジネスに活用せよ!と外野が指示したところで、目の前の業務との乖離が激しく学ぶ意欲にはつながらない。
いかに本業の戦略と紐づく需要を個々人の「役割」にブレイクダウンできるか。アクセンチュアでは2022年に、”Work to Learn. Learn to Work.”(学ぶために働く。働くために学ぶ)という最新のラーニングセオリーを打ち出した。「足もとの仕事のための学習」「学ぶことが目的」という一方通行の思考から脱却し、 「業務を通じて学習を最大化」「将来の仕事に必要なスキルを習得」すべきだという意味だ。学びと仕事の両輪を回して、組織と社員が一体となって中長期の両者の成長を目指すアプローチである。ラーニングに納得感を持たせ、恒常的にサイクル化できるかが肝要となる。
実際にDX人材を定義するプロセス
DX人材の定義では、以下に掲げる①~⑧のステップを踏む必要がある。連載初回である今回は下記の①~④までを説明する。
①事業戦略・成長戦略の分解
②人材タイプの定義
③現状把握、課題分析
④人材ポートフォリオへの落とし込み
⑤スキルの定義
⑥ロールとのひも付け
⑦レベル、キャリアパスの設計
⑧従業員価値の定義
②でいう「人材タイプ」とは、その人材が自身の「ジョブ・ロール」を果たすために、どのようなケイパビリティを保持する必要があるかを定めたものである。新規事業の創出に寄与するタレントが欲しいのなら、必要な人材タイプは「ストラテジスト」である。「革新をもたらすアイデアを創出、社会課題を解決する事業を追求する」ために、必要なスキルは「変革シナリオ立案力」「サービス企画力」「CXO(=CEOやCTOといった責任者)との対話力」であり、知識は「財務・会計」「業界トレンド」「戦略フレームワーク」になる——といった具合だ。
ここでのポイントは、必ず自社のビジネスニーズを出発点に考えることだ。経営計画・事業計画を分解して、一般的なデジタル標準定義とロジカルにひもづけていく。世の中にあるスキル標準は参考にしながらも、自社がどこを目指すのか、できれば事業計画や成長戦略とセットで検討することが望ましい。もし基本的な戦略がなければ、現場で上がっている課題や数年先でのニーズから一旦定義しておいてもいい。
人材タイプの定義自体は、細分化しすぎてはいけない。最初はビジネス人材、テクノロジー人材、データ人材の3つを大別したうえで、人材タイプごとに何をさせたいのかを具体化する。
この際、「DX人材」に少なからず求められる「変革(DXの“X”)」力は、単なる技術力だけでなく、行動的な側面も強化する必要がある。例えば、チーム内外のメンバーとの意思疎通を通じてパフォーマンスを最大化する「コラボレーション力」、学習した技術知識を組み合わせ新たなソリューションを考案する「テクノロジー融合力」といったところだ。特に従来の金融機関では、「協調性」「内部調整力」のような対極の行動様式が重んじられていたこともあり、新たに評価されていくべき行動水準はしっかりと明文化して打ち出す必要がある。
そして④の「人材ポートフォリオへの落とし込み」だ。経営計画・要員計画と人材タイプとをリンクさせ、どのタイプが何人必要なのかを定量化する。これを目標値として、足元の要員数と目標値とのギャップを測定し、そこを埋めていくことになる。このステップは次回以降に解説していきたい。
一連の流れを通じてのポイントは、躍起になって「DX人材」を探しに行く前に、「自社が真に達成すべきことは何か?」「そのためにどのような人材が必要か?」を徹底的に自問することだ。そんなの当たり前のことだ、と思われるかもしれない。しかし、ここを見落としたまま五里霧中で「DX人材育成」に走ってしまうケースがいかに多いことか。
あるデジタル技術のスペシャリストが欲しいと考え、自社内で資格を取得させるなど育成投資をした結果、一定の水準に達した人材が増えた…しかし社内には、そもそもスペシャリストが活躍できる案件も、必要とされる現場もなかった。結局デジタル人材の使い道がなく、持て余している——そのようなたぐいの実話は尽きない。DXというある種のバズワードに踊らされず、まずは自社に必要な人材像を見つめ直さなくては、本末転倒である。
DXとは資格があればできる仕事ではない。そのためアマチュアと専門家の境目がわかりづらい。スキルは技術の進展とともに日々陳腐化していくし、実務家として実際に起きる問題を解決しながら、プロジェクトを成功に導いていくことができるかが問われる能力である。研修を受講し、資格を取得したことをもってDX人材の人数を達成することは終わりではなく、始まりである。すなわちこの人数に対して継続して学ぶ機会を提供し、機会を預けて、成果を出すためのサポートをしていく必要がある。「現在活躍しているDX人材の人数」こそ、注視すべき指標となる。
金融機関A社の例
それでは今回の最後に、国内金融機関の実例を見てみよう。A社は1年以上にわたって「DX人材」を採用してきたが、ジュニアクラスは採れてもリーダークラスの獲得に苦戦していた。採用した人材の見極めができずに要件を満たしていないこともあった。
まず人材の定義に着手することにしたが、A社本体の人材要件や制度設計にまで手をつけてしまうと、合意形成などに時間がかかることが見込まれた。そのためデジタル子会社の人材に対象を限定した。はじめに標準的な人材要件をたたき台として議論を始めたが、A社本体におけるビジネス・システム開発の進め方との違いが大きすぎて、検討に加わるメンバーからは「イメージがつかない」と困惑する声が多かった。
そこでA社本体の事業、開発プロセスをベースに整理しなおすことにした。精緻な制度を整える前に現状の人材にあてはめてアセスメントをしたことで、誰がどの人材タイプに該当するのか、具体的なイメージを持って精査を進めることができた。
ただしDX人材に欠かせないデザイナーだけは、これまでA社内に存在しなかった。アクセンチュアに在籍するデザイナーを招いて人材像や仕事のイメージを共有したところ、今のプロセスにおける創発レベルを上げることが想定できたため、デザイナーをA社に加えることになった。
あるべき理想像やビジネスの方向性に関しては、検討段階だと十分に詰められていないことも多い。一方でこれまで自社にいなかった人材については外部の人材を取り入れることができる。人事部門や検討メンバーがプロパー社員だけの場合、新たな人材の採用や必要な制度への観点が不足することがあり、金融以外からの人材確保を想定しているなら、そうした人材運用の経験者を獲得することも有効である。
A社の事例から言えることは、社内での納得感を十分醸成させて、今後運用していくことができる人材を定義することの大切さであり、DX人材の採用を「チェンジマネジメント」(組織変革を促す経営管理)の一環として捉える重要性である。