超低金利による収益力の悪化や地方経済の低迷で、特に地域銀行の経営環境は厳しい状況が続いている。最近は「どこが生き残るのか」といったネガティブな報道をされる機会も多い。しかし大原氏は、地域銀行がその強みに集中さえすれば、必ず輝きを取り戻せると強調する。
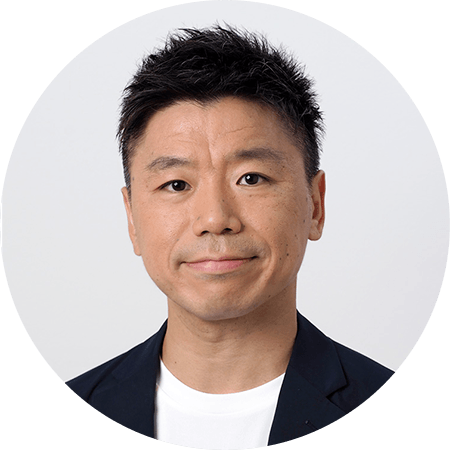
2003年東京大学法学部卒。2010年ロンドンビジネススクール金融学修士課程修了。野村資本市場研究所を経て、2004年に興銀第一ライフ・アセットマネジメント(現アセットマネジメントOne)に入社。日本・英国で主に事業・商品開発業務に従事。同社退職後、マネックスグループ等から出資を受け、2015年8月にマネックス・セゾン・バンガード投資顧問を創業。2016年1月から2017年9月まで同社代表取締役社長。2018年5月に日本資産運用基盤を創業し、代表取締役社長に就任。
「地域銀行の皆さまは、地域に根ざしながら、長年にわたって地元のお客さまとの信頼関係を築いてきました。地域の個人・法人の継続的なサポートは、地域銀行にしかできない役割だとさえ言えるかもしれません。だからこそ、例えば個人のお客さまに投資信託を『売って終わり』ではなく、保有中は定期的にサポートし続ける。販売に対して手数料を取るのではなく、そうしたサポートそのものに対価をもらうビジネスモデルに変えるべきだと私は考えています」。
「商品を売る」だけで終わらないビジネスモデルが必要
投資信託をはじめとする金融商品の販売で言えば、近年はゴールベース・アプローチと呼ばれる手法が注目されている。具体的には、顧客のライフイベントに基づいた目標を設定し、そこから逆算して資産運用のやり方を徐々に変えていく手法のこと。金融機関には、顧客のライフプランを随時確認しながら、資産形成の伴走者として寄り添う姿勢が求められる。
ただ、ゴールベース・アプローチも、あくまでもひとつの手法に過ぎないと大原氏は話す。「最近の金融業界では、顧客本位の姿勢のうたい文句として『商品売りからゴールベース・アプローチへ』と言われたりもします。もっともこれは、金融商品は売って終わりではなくそこからがスタートだということを別の表現に言い換えているだけ。お客さまからしても、ゴールベース・アプローチを行っていようがいまいが、自分の大切な資産を預けているという点に変わりはありません」。
とはいえ、従来の金融機関が「商品を売る」ことで完結していたのも否めない。なぜなら投資信託などの金融商品は、販売した時点で手数料が発生するからだ。それでも投資信託であれば、信託報酬という運用期間中の手数料もあるため継続的にお金が入ってくるのも事実だが、近年の低コスト競争を受けてその額は減少の一途をたどっている。そのため売買を繰り返さないと、金融機関としてもビジネスが成り立たない仕組みになってしまっていると言っても過言ではない。
近年は金融庁の主導で「顧客本位の業務運営」という言葉が掲げられ、金融機関に営業スタイルの変革を迫ってきた。しかし大原氏によれば、もっと顧客のためになるビジネスに変えていかないといけないという意識自体は、多くの地域銀行が以前から持っていた。それでも販売手数料を得る以外のビジネスモデルが見いだせなかった以上、そうした意識を実践できなくても仕方がなかった面もあるという。
「そこで私たちは、顧客と丁寧に接し、付加価値を提供することで、預かっている金額に応じてきちんと報酬を得られる仕組みを作りましょう、と提案しているわけです。その仕組みづくりのサポートを行うことこそが、私たちのビジネスなのです」。


























