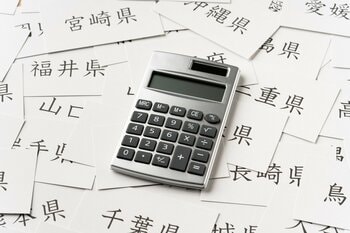金融リテラシーとデジタルリテラシーは表裏一体
――若い世代は、働いてちゃんとキャッシュフローを得る基盤を作ることが大事ということですね。そのうえで資産運用と向き合う際に、どんなことに気を付けるべきですか。
デフレからインフレへと移行しつつある以上、個人にとって資産運用はこれまで以上に重要になった、という事実は変わりありません。これまで、ネガティブなことばかり述べてきましたが、投資環境は随分と良くなったと思います。税制優遇制度も充実しましたし、インターネット証券を使えば取引手数料はほとんどかからなくなりました。投資信託の信託報酬も、以前と比較してかなり引き下げられています。
ただし、ここでも注意すべき点があります。インターネットが不可欠の世界となったことで、胡散臭いものも身近に溢れてしまいました。たしかに良質な金融商品へのアクセスは格段に向上しましたが、同時に、詐欺まがいの悪質な金融商品にも簡単にアクセスできるようになってしまったのです。
――インターネット社会の光と闇ですね。
これは金融だけに限らず、あらゆるネット上の情報は玉石混交だということは、私たちの世代は分かっていますし、若い世代の人もある程度理解はしていると思います。しかし、日常的にそうした悪質な情報に囲まれてしまうと、胡散臭いものに対する心理的なハードルが下がってしまうんですよね。これが大きな問題です。
私が学生にいろいろと注意喚起をしても、SNS上のインフルエンサーみたいな人の意見を持ち出して、反論してきたりするんですよ。私の意見とインフルエンサーの意見を同列で比べるなよ、と思ったりするんですが、若い世代は偏見がなく物事をフラットに見るんですよね。向こうからすれば、私の方が胡散臭いだろと(笑)。「じゃあ、先生、どうやって情報を見分ければいいんですか」って聞かれたりしますけど、そういった類の情報を実際に目の前に出してくれれば、「これは胡散臭いぞ」とか言うことは可能ですが、一般論としてはなかなか難しい部分がある。そこに持ってきて、「インフレが大変だ、自分も資産運用しなくちゃ」っていう切迫感が重なると、判断が狂って、身を切るような資産運用になりかねません。
――その部分にはどんな対処をされているのですか?
私は、これからの金融リテラシー教育は、インターネット社会といかに付き合うかというデジタルリテラシー教育とセットで取り組む必要があると痛感しています。金融と非金融の境界線は、普通の人はあまり区別していないんです。例えば、学生で生活費が足りなくなってきたけど、これ以上親には仕送りしてもらえないとなったとき、バイトをしようとすると、投資詐欺や闇バイトといった案件がネット上に溢れているわけです。闇バイトに手を染めないことは金融リテラシー教育の中では語られることではないですが、お金で困っているという金融的な原因があり、それが現実の行動にも影響してしまう。そこにトータルで対処するためには、もう金融リテラシーの半分は、デジタルリテラシーとリンクさせないとダメだと考えています。学生の例を出しましたが、これは現役世代やシニア世代にも十分通用する話ではないでしょうか。
――金融リテラシーとデジタルリテラシーの両方を高めていくことが必要ということですね。本日はどうも、ありがとうございました。
渡邊隆彦氏・専修大学商学部教授

三菱UFJ銀行(現)にて主に市場業務、投資銀行業務を担当後、三菱UFJフィナンシャル・グループ コンプライアンス統括部長、国際企画部部長を歴任。2013年4月より現職。日本郵政アドバイザリーボードメンバー等も務める。東京大学工学部卒、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院修了。