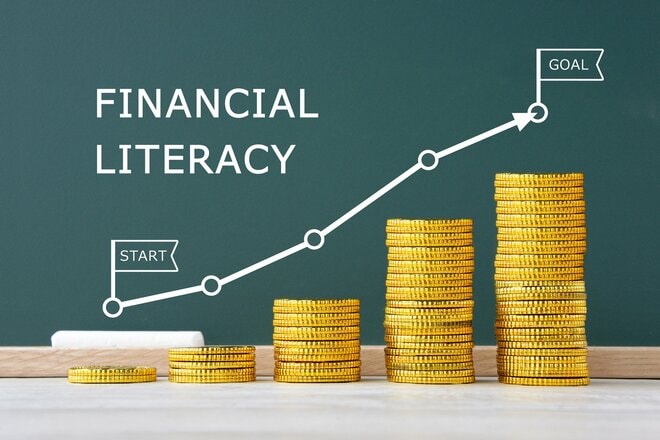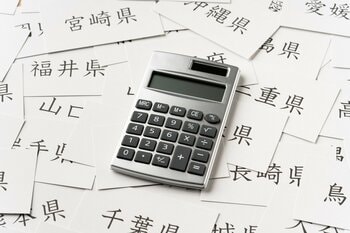日銀が2024年3月に17年ぶりに利上げに転じて以降、日本も「金利のある世界」となり、約30年ぶりの本格的な金利上昇・インフレ局面に移行しつつある。それに伴い、個人の資産運用には劇的な変化が訪れている。
今の現役世代の多くが過ごしてきたデフレ環境下では、預金による資産形成も正当化されてきた。しかし、金利のある世界では、投資をしなければ資産が実質的に目減りしてしまう。この大転換の中、個人の資産形成や金融リテラシーはどうあるべきか。
1990年代の「金利のある時代」に銀行実務を経験し、現在は金融リテラシー教育の最前線で教壇に立つ専修大学商学部の渡邊隆彦教授に、現在の課題や今後の展望について聞いた。
デフレ時代よりも深刻化する将来不安
――大まかに2000年から24年までをデフレ下のマイナス金利の時期とすると、今は1990年代以来の金利のある世界になります。90年代と現在との最も大きな違いは何でしょうか。
インフレ要因ということで言えば、現在は強烈な人手不足があります。国内の人手不足が供給制約となり、インフレが加速している部分が大きい。90年代には供給制約はありませんでした。加えて、今は実質賃金の低下が顕著です。これが、個人の景況感というか、心理面に大きな影響を与えています。本来、インフレのときは、物価と賃金は同じペースで上昇し、豊かさも実感できるはずですが、今はインフレが先行してしまっているので実質賃金は大幅に低下しています。すべての世代にわたって、将来不安がどんどん高まっている状態です。
――90年代はバブル崩壊の過程にあったわけですが、将来への不安などはなかったのですか。
当時は、どちらかというと、まだバブルの再来があるんじゃないかと思っている人も多く、将来への不安はそれほどなかったですね。あと、デフレの時期も、景気の悪さを漠然と感じている人は多かったと思います。ですが、賃金こそ上がらないものの、それに輪をかけて物価が下落していたので、豊かさの実感はないながらも預貯金による資産防衛はできていました。それが、いまは物価上昇が凄まじく、人々に不安感が広がっています。これは、いままでの日本にはなかったことではないでしょうか。
日本は、個人金融資産などマクロの数字には豊かさが表れていますが、よく言われているように二極化が急速に進行中です。すでに住宅などの不動産や株式などを持っている人は含み益も膨らんで、非常に有利な状況でしょう。他方、例えば、若い一般生活者は“居住不安”を強く感じているようです。「居住」は、衣食住のうち、もっともコストがかかる部分で生活への影響も大きい。よく話題になるように、都心の不動産価格、住居費の上昇は強烈なので、若い世代の居住不安は強く、それが将来不安にもつながっています。生活に余裕がある中間層が減少傾向にあることも、90年代との大きな違いではないでしょうか。
――金利のある世界になったけれど、資産運用の手前の段階でハードルが上がってしまったということですか。
近年、新NISAの拡充など「貯蓄から投資」を促進するさまざまな政策が打ち出されてきましたが、その恩恵を受けられている人は限定的です。それどころか、資産のない一般庶民の間に将来不安が蔓延している状況で、「人生100年時代に、あなたの資産寿命は大丈夫ですか?」と、一層不安を煽られるような事態になっています。また、インフレによる生活苦によって、節約志向に走る人もいる一方で、インフレ対策には資産運用が必要だと感じる人も増えます。すると、「身を切るような資産運用」をする人が出てくる恐れもあるのです。