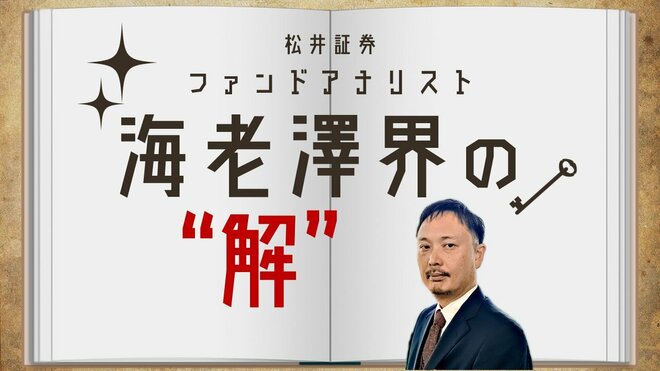NISA(少額投資非課税制度)を通じた個人の投資拡大とともに、指数への連動を目指すインデックスファンドの存在感が増している。特に根強い人気を持つ「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」(愛称:オルカン)と「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の純資産総額の合計は2025年6月末時点で13兆7746億円となっており、ETF(上場投信)を除く国内全公募投信の1割に迫る規模となっている。もっとも、ここ数年で投資を始めた初心者の中には、インデックスファンドの種類や運用手法について、知らないことが多い方もいるのではないか。じっくりと解説したい。
インデックスファンドとは?
インデックスファンドは特定の「指数」への連動を目指す運用戦略全般を指す言葉だ。指数自体は株式以外にも債券やREIT(不動産投信)などを対象とするものもあり、これを組み合わせたバランス型のインデックスファンドもある。とりあえずここでは「株価指数」に着目してみよう。
身近な株価指数として「日経平均株価」と「東証株価指数(TOPIX)」を思い浮かべる人が多いだろう。どちらの指数にも連動を目指すインデックスファンドがあり、どちらに投資すべきか迷う人もいるかもしれない。それぞれの特徴を言えば、日経平均は株価そのものに注目して銘柄の構成比率を決める「株価平均型」であり、TOPIXは時価総額(株価×発行済株式数)に応じて銘柄の構成比率を決める「時価総額加重平均型」だ(※1)。
【関連リンク】TOPIXとは?日経平均株価との違い|計算方法や構成銘柄、活用する方法
米国の株価指数にそれぞれを当てはめれば、日経平均の「株価平均型」に該当するのが「NYダウ」(ダウ工業株30種平均)であり、TOPIXの「時価総額加重平均型」に当てはまるのがS&P500だ。なお、オルカンが連動を目指す「MSCIオール・カントリー・ワールド指数」も時価総額加重平均型だ。単刀直入に言えば、インデックスファンドの連動対象として一般的であり、ふさわしいとされているのは「時価総額加重平均型」である。
【関連リンク】NYダウとは?構成銘柄の特徴や日本から投資をする方法
【関連リンク】S&P500とは?NYダウとの違いや構成銘柄、買い方など基本をわかりやすく解説
なぜNYダウよりS&P500がインデックスファンド向きなのか?
なぜ、日経平均やNYダウの「株価平均型」よりも、TOPIXやS&P500の「時価総額加重平均型」の方が、インデックスファンドの連動対象として一般的で、なおかつふさわしいと言えるのか。過去のコラムでは、学術的な視点から解説したこともあるが、投資初心者には分かりづらかったかもしれない。
【関連リンク】S&P500が連日の最高値更新! 「株価指数」を深堀り
単純にこのように考えれば良い。時価総額加重平均型の株価指数は「株式市場そのものの形」に近い。市場は、多くの参加者が知恵を出し合って売買し、それぞれの銘柄の時価総額がそれぞれのファンダメンタルズを反映していくことで形作られるとしよう。だとすれば、「市場そのものの形は概ね正しいものだ」とも受け止められるし、そこに乗っかるのが最も合理的ともいえる。
「人のふんどしで相撲をとる」というのはインデックスファンドを表す言葉として、しばしば使われるが、その表現が最も当てはまるのが、時価総額加重平均型のインデックスファンドといえるだろう。なお、日経平均やNYダウといった株価平均型はインデックスファンドが生まれる前からあるもので、「市場全体の株価のおおよその動向を知らせる」といった株価指数の原始的な機能を果たす役割が大きかった。もちろん、これらのインデックスファンドがダメなわけではないが、特に機関投資家などのプロの投資家が、株価平均型のインデックスファンドに投資することはほとんどない(※2)。