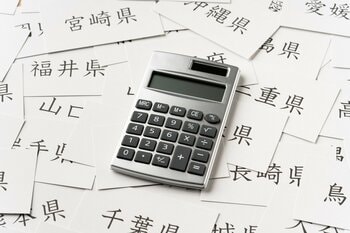税制優遇が受けられるNISAとiDeCoの2つの制度があります。
NISAは運用益が非課税で、自由度が高いのが特徴です。一方、iDeCoは掛金が所得控除の対象になりますが、60歳まで引き出せません。
では、それぞれの制度をどう活用すれば、効率的に資産を増やせるのでしょうか。ファイナンシャルプランナーの藤川太氏が、NISAとiDeCoの違いと使い分けのポイントを解説します。(全3回の2回目)
●第1回:iDeCoとNISAの税制メリットを徹底比較! 所得控除の対象になるのはどっち
※本稿は、藤川太著『2025年度最新制度対応版 世界一かんたんなNISAとiDeCoの得する教科書』(宝島社)の一部を抜粋・再編集したものです。
iDeCoでは掛金の限度額を考慮
NISAとiDeCoは併用することができます。それぞれの特徴を活かして上手に併用できると、より一層効率的に資産形成することが可能です。
これらの制度は税制メリットがあるだけに、それぞれ積立できる金額に制限があります。制限枠内での積立では必要な金額を貯め切れないかもしれません。
iDeCoは公的年金の種類や勤め先の企業年金の違いなどによって、掛金の限度額が異なります。たとえば自営業者であれば、上限額は月6.8万円(年81.6万円)。上限いっぱい活用して20年積み立てれば、元金だけで1632万円にもなります。運用が上手くいけば2000万円以上の老後資金を作ることができる水準です。
一方、公務員であれば上限額は月2万円(年24万円)です。20年積み立てたとしても元金は480万円にしかなりません。運用益を考慮しても、十分に老後資金を貯めることはできないでしょう。
自営業者は公的年金が少ない分、できるだけ老後資金は貯めたいところです。会社員であればiDeCoの上限額が低く、力不足であることは否めません。とはいえ、iDeCoは60歳までお金を引き出すことができない「積み立てすぎ注意」の制度です。教育資金や住宅資金など大きな資金需要の大きさと時期を確認し、やりくりできる範囲で積み立てる必要があります。