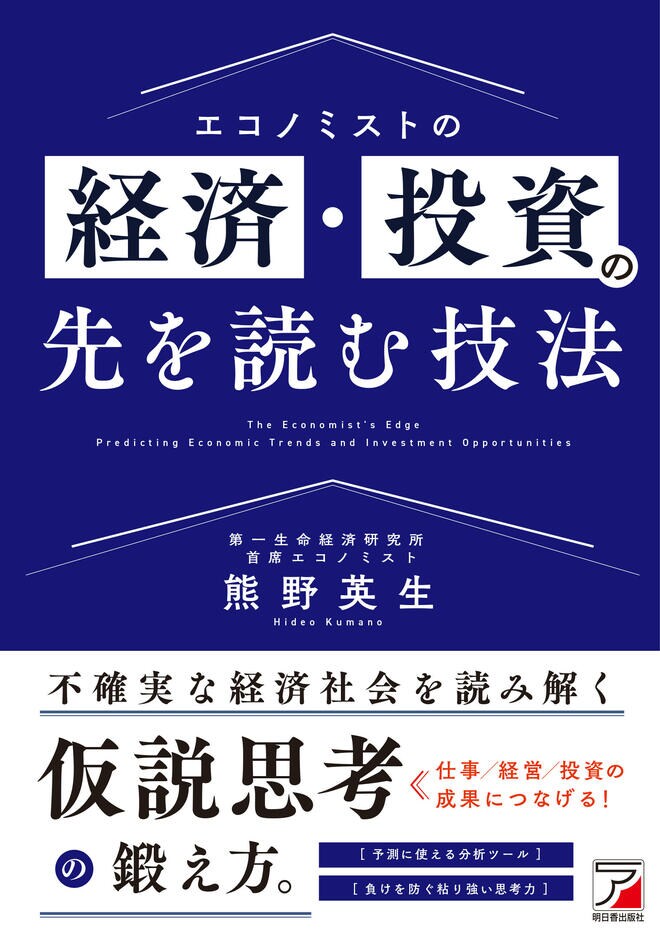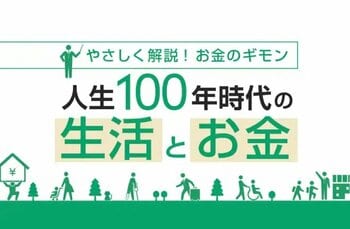株価は景気を映す鏡
では、具体的に景気循環と株価の関係について考察してみましょう。
ここでは景気循環の話に入る前に、「株価は本当に波のように変動しているのか?」という根本的な疑問を考えてみたいと思います。たとえば日経平均株価の長期チャートを見ると、2012年頃を底として2025年まで全体としては上昇傾向にあります。つまり、長期的に見れば株価は一時的な上下動を繰り返しながらも、結局は上昇トレンドを描いているのです。
これは株価が「トレンド」と「サイクル(波)」の2つの要素で構成されていることを示しています。そのため、株価の変動は単純な波ではなく、もっと複雑な動きをしているのです。日経平均株価が225種類の銘柄によって構成されていることを考えると、この点は理解しやすいでしょう。個々の銘柄の値動きが合成された結果として、日経平均株価という指標が形成されているからです。
次に、計量分析の手法を用いると、「トレンド」と「サイクル」の関係に分解できます。2012年の底値から2024年までの株価上昇のトレンド成分を抽出し、このトレンド成分を実際の株価データから差し引くことで、景気循環に起因するサイクル成分をより明確に浮かび上がらせることができます。
では、このサイクル成分は一体何を反映しているのでしょうか。私は、一定期間ごとに株価を押し上げたり押し下げたりする要因、すなわち景気変動を反映していると考えています。なぜなら、株式とは本来「定期的に配当を受け取るための権利書」だからです。
企業の配当金額は景気の良し悪しによって大きく変わります。これは企業収益が景気動向によって変動するのと同じです。景気が良くなれば企業収益が増加し、配当金額も増える可能性が高まります。逆に景気が悪化すれば企業収益が減少し、配当金額も減る可能性が高まります。こうした仕組みによって、景気変動が企業の収益と配当金額に影響を与え、結果として株価の上下動を生み出すのです。
●第2回は【“教科書”的な4つの経済サイクルは鵜呑みにできない? 技術革新が生み出しつつある新たな景気循環のパターン】です。(3月29日に配信予定)
エコノミストの経済・投資の先を読む技法
著者名 熊野 英生
発行元 明日香出版社
価格 2,145円(税込)