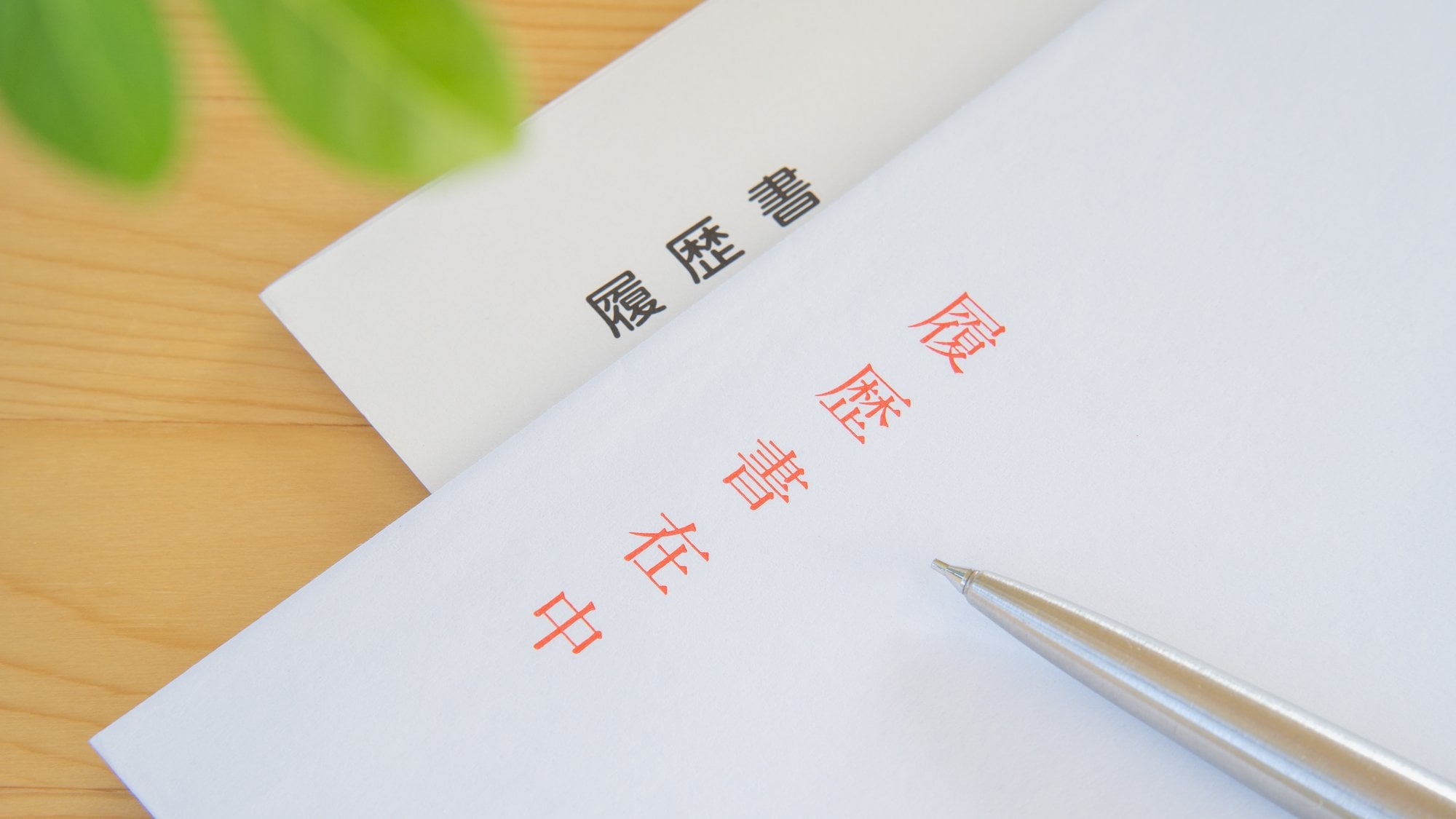多くの人員削減で、なぜ「中高年」が対象になるのか
この手の人員削減は、中高年をターゲットにしたものが大半を占めています。これは、企業として中高年社員に辞めてもらいたいと思っているからに他なりません。
独立行政法人労働政策研究・研修機構の「各年齢階級における正規、非正規の内訳」というデータを見てみましょう。
ここでは正規社員の人数を参考にします。1988年と2023年の年齢階級別従業員数を比較してみましょう。
25~34歳・・・878万人→818万人(▲6.8%)
35~44歳・・・927万人→843万人(▲9.1%)
45~54歳・・・717万人→984万人(+37.2%)
55~64歳・・・307万人→571万人(+86.0%)
65歳以上・・・36万人→126万人(+250.0%)
1988年から2023年までの35年間で、日本企業が超高齢社会になっていることが分かる数字です。
そして、組織の高齢化が何をもたらすのかを考えてみて下さい。一番の問題点は、特に年功序列的な色合いの濃い日本企業の場合、年齢が上がるほど給与が増えていきますから、企業側からすればコストがアップすることになります。
国税庁の「年齢階層別の給与額」を見てみましょう。あくまでも平均値ですが、従業員が5000人以上の大企業の場合、年収ベースでは以下のようになります。
20~24歳・・・233万1000円
25~29歳・・・414万2000円
30~34歳・・・488万円
35~39歳・・・540万5000円
40~44歳・・・587万5000円
45~49歳・・・606万円
50~54歳・・・610万円
55~59歳・・・633万3000円
60~64歳・・・387万5000円
65~69歳・・・265万3000円
70歳以上・・・233万円
このように、平均給与のボリュームゾーンを見ると、45歳から59歳までの年齢階層が最も高額になっています。高給なうえに社員数も多いため、企業にとってはこの層のコスト負担が非常に重くなっているのです。
そのうえ、今は65歳定年が当たり前になり、ゆくゆくは70歳定年も視野に入りつつあります。
企業としては、これだけの人数を占めている中高年社員を、さらに65歳、70歳まで雇い続けていけるだけの余裕が無くなっているとも言えます。そのため、少しでも早い段階で、中高年社員の人員削減に着手し始めているのです。黒字であるにも関わらず人員削減を行っている企業が多いのは、これから先の人件費負担増を出来るだけ軽減したいと考えているからです。
1980年代半ばから1990年代にかけて社会人になった人たちが、まさに人員削減のターゲットになっています。この年齢層の人たちはかつて、「大企業に入れたら一生安泰」などと言われたものですが、30余年という時間の流れは、この程度に当時の常識を覆すだけの力があるということです。