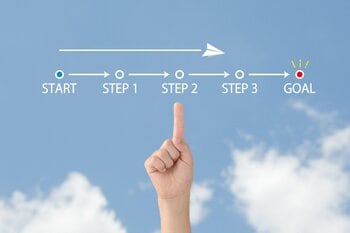公的年金制度の改正から見える確定拠出年金の役割
しかしこの20年で、確定拠出年金は企業年金という位置づけから、公的年金を補完する自分年金制度としての大きな役割を担うまでに成長してきました。
公的年金は、夫婦二人の高齢期の収入を夫の現役時代の収入のおよそ6割程度とすることを目安に設計されてきました。年金制度は昭和36年にできていますから「サザエさん」のように夫が働き妻は家庭を守ることをモデルケースとしました。子育ても終わった老後の生活費は現役時代よりは随分減るだろうから、年金はそれに応じた金額で構わないだろうと考えたのでしょう。
しかし日本は急激に少子高齢化社会に突き進みました。保険料を納める人が少なくなり、年金を受け取る期間が劇的に伸びたことで年金財政が圧迫されてきます。それでも現役世代に負荷をかけ「保険料を上げる」ことでなんとか収支を維持してきましたが、いよいよ難しい局面となってきました。
そこで2004年の改正では、国民年金、厚生年金共に保険料の上限が設定されました。また、すべての国民が受給する国民年金の財源に対しては国庫負担金という税金投入がなされていましたが、それをそれまでの3分の1から2分の1に引き上げました。さらに年金を受けとる側にも、購買力を維持するための仕組みにマクロ経済スライドが導入され、支給額が抑制されるようになりました。そしてそれらの対策がうまく回っているのかどうかを、5年に1回の財政検証で年金の健康診断をしながら、持続可能なものにしようとしたのです。
しかし、その年金改正が「100年安心プラン」と呼ばれることになったことをきっかけに、「日本の年金制度は安心じゃないのか!?」と、声高に騒ぎ出した方が少なくなかったことは記憶に残っているでしょう。老後の暮らしは国や会社がなんとかしてくれるものと思っている人が多かった時代、自らが主体的に運用をしなければならない確定拠出年金は、不人気でした。個人型は自営業者と一部の会社員のみが加入対象者でしたし、企業型に至っては、導入当初の危機感は薄れて無関心層が増え、問題となっていました。