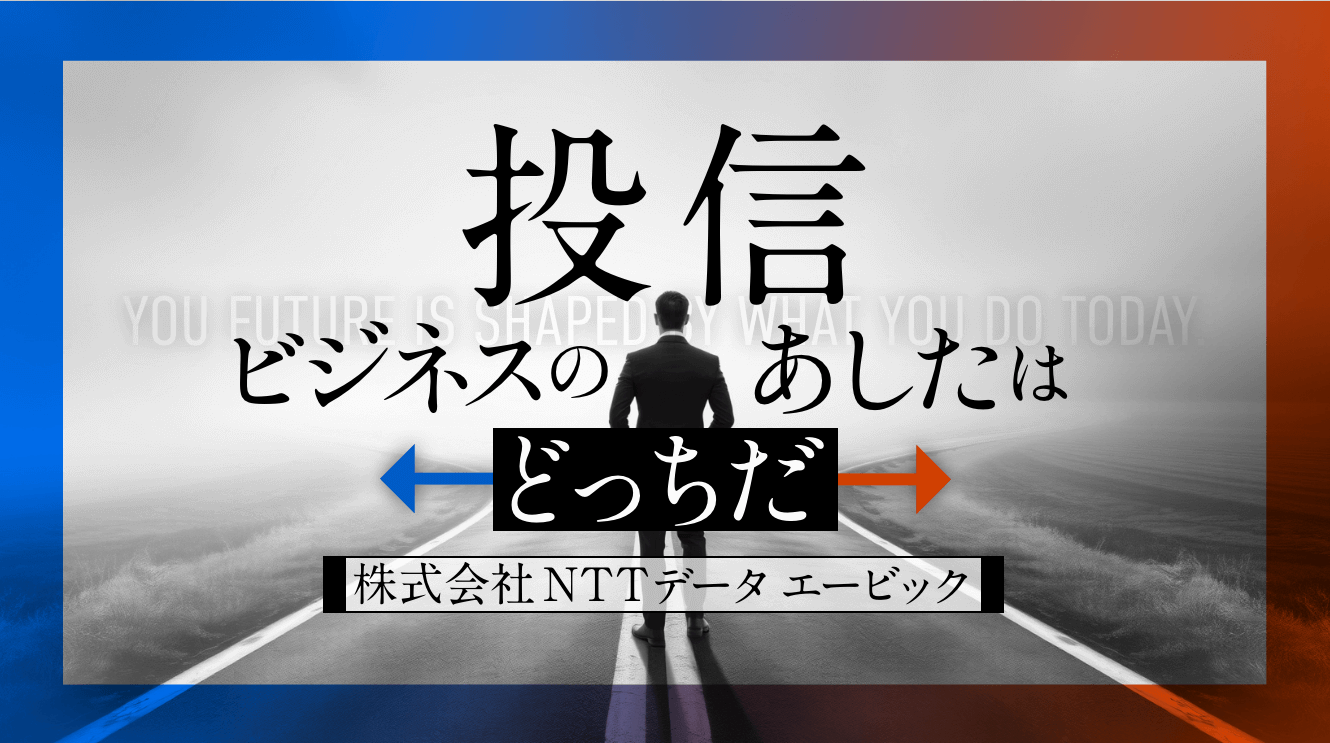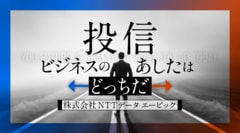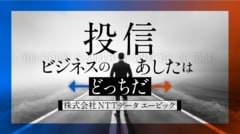今や、買い物をする場合、ネットから情報収集をすることは当たり前の時代になりました。投資信託の場合も、ネットで様々な情報を得ることができます。
来店されたお客さまがファンドを指定して購入の意向を示された場合、その情報源を確認する必要があります。ネットからあらかじめどんな情報を仕入れているのか、これについて見ていきたいと思います。
1. 金融機関のホームページから得られる情報
多くの金融機関はホームページに取扱い投信の情報を掲載しています。この場合、勧誘を目的とした広告と見なされますので、恣意的な見解や根拠のない情報は掲載されていません。基本的には目論見書に記載されている内容と基準価額、収益率、標準偏差等のデータとなります。併せて目論見書(交付、請求)、運用報告書、販売用資料などを見ることができます。
基本的に一覧表形式のサイトとなりますので、自らの投資目的やリスク許容度といったパーソナルな要素との紐づけは限定的なものになります。設問に回答してファンドを選定する検索機能を用意している場合もありますので、お客さまが事前にご利用されていることも考慮しておく必要があるでしょう。
2. 第三者機関の提供する情報サイトから得られる情報
投信協会の「投信総合ライブラリ」、ミンカブ・ジ・インフォノイドの「みんかぶ投信」、Yahoo Japanの「Yahooファイナンス」、ウエルスアドバイザーなどがあります。金融機関のサイトと異なり、公募投資信託全ファンドが対象となります。内容は金融機関同様、目論見書の記載内容の他、独自レーティングを掲載しているものもあります。
レーティングについてはシャープレシオの相対比較など簡単なものが多いので、これを頼りにファンドを選んできたお客さまには注意を促す必要があります。あくまでも過去実績を基にした一指標に過ぎません。お客さまの投資目的、リスク許容度などとは無関係で格付けされていますから「レーティングが高い=お客さまに適したファンド」とは言えません。最近は視聴頻度も増加し、月間800万PVに上るサイトもあります。
3. 投信会社のサイトから得られる情報
最初から投信会社のホームページを訪れるお客さまは少数と思われますが、検索サイトでファンド名を指定して検索すると投信会社のページに行き着くことがあります。投信会社はその商品を組成した会社ですから、力を入れているファンドは特設サイトを作り、投資先の有望性、運用手法の効用などをかなり細かくアピールしています。
当然、読むとどれも素晴らしいファンドに思えてきます。
この場合もお客さまの事情、要望とは無関係に主に期待リターンを中心に構成されていますので、販売する場合はマイナス面も併せてご案内することが必要です。
投信会社のサイトまでご覧になっているお客さまはそのファンドについて知識が豊富です。しかし値上がり期待が先行している場合も考えられますので、1、2と同様にお客さまの事情を踏まえてリスクの部分を冷静にご判断頂くことが重要です。
4. YouTubeで学習
かなりの数のアクセスがありますので、YouTubeで投資を学習されてきたお客さまも多くいらっしゃると思われます。
内容は幅広く、投資、資産形成の基本から推奨ファンドまでチャンネルによって特色があります。登録者数の多いチャンネルから配信されている内容を見てみます。
多くは資産形成の必要性と積立による資産形成を説いています。インフレなどを絡めた一般的な解説でお客さまの理解には大いに役立つ部分と思われます。もう一つの面でかなり偏った見方をしているチャンネルもあります。「金融機関窓口は手数料収入を考えて顧客本位ではない」「複雑なファンドを売りつけられる」「ネット証券で購入すべき」といった内容も散見されます。
多くのチャンネルでは最終的にS&P500のインデックスファンドを推奨しており、金融庁のいう「顧客に応じたリスク・リターン」という観点が無視されています。長期積立投資をこれから行う若年層に限れば大きく間違った話ではないかもしれませんが、見た人は誰もがS&P500インデックスが最適と思わせる内容となっています。こういった記事が10万回以上再生されています。
昨今のS&P500インデックスやオルカンといった集中的に資金流入が続く傾向と無関係ではないでしょう。また窓口を叩くという論調も閲覧者数を稼ぐ定番の記事となっています。こういった記事を読む方は窓口に来ることも少ないかと思いますが、来店された方が記事を鵜呑みにしていた場合、丁寧な対応が必要となります。S&P500インデックスは数ある株式投信の1類型に過ぎず、誰に対しても、どの局面でも最適とは限りません。
ネット上の情報を基にして購入するファンドを選定するお客さまは、投資を前向きに取り組みお考えの方でしょう。それに対してあくまでもネットは一般的な情報に限定され「お客さまに適した」という観点は望めません。
YouTubeでの窓口営業の批判的な記事もリスクの高すぎるファンド、複雑で運用内容が理解しがたいファンドもネット証券では普通に購入できてしまう側面があることを認識すべきでしょう。
来店されたお客さまには店頭でしかできない顧客本位の業務運営が可能となります。その部分での付加価値を高めてゆくことがお客さまの資産形成、資産管理の成功につながります。お客さまご自身で情報を収集する行動を支援するために、データの見方をお伝えすることも長いお付き合いをする中では重要ではないでしょうか。