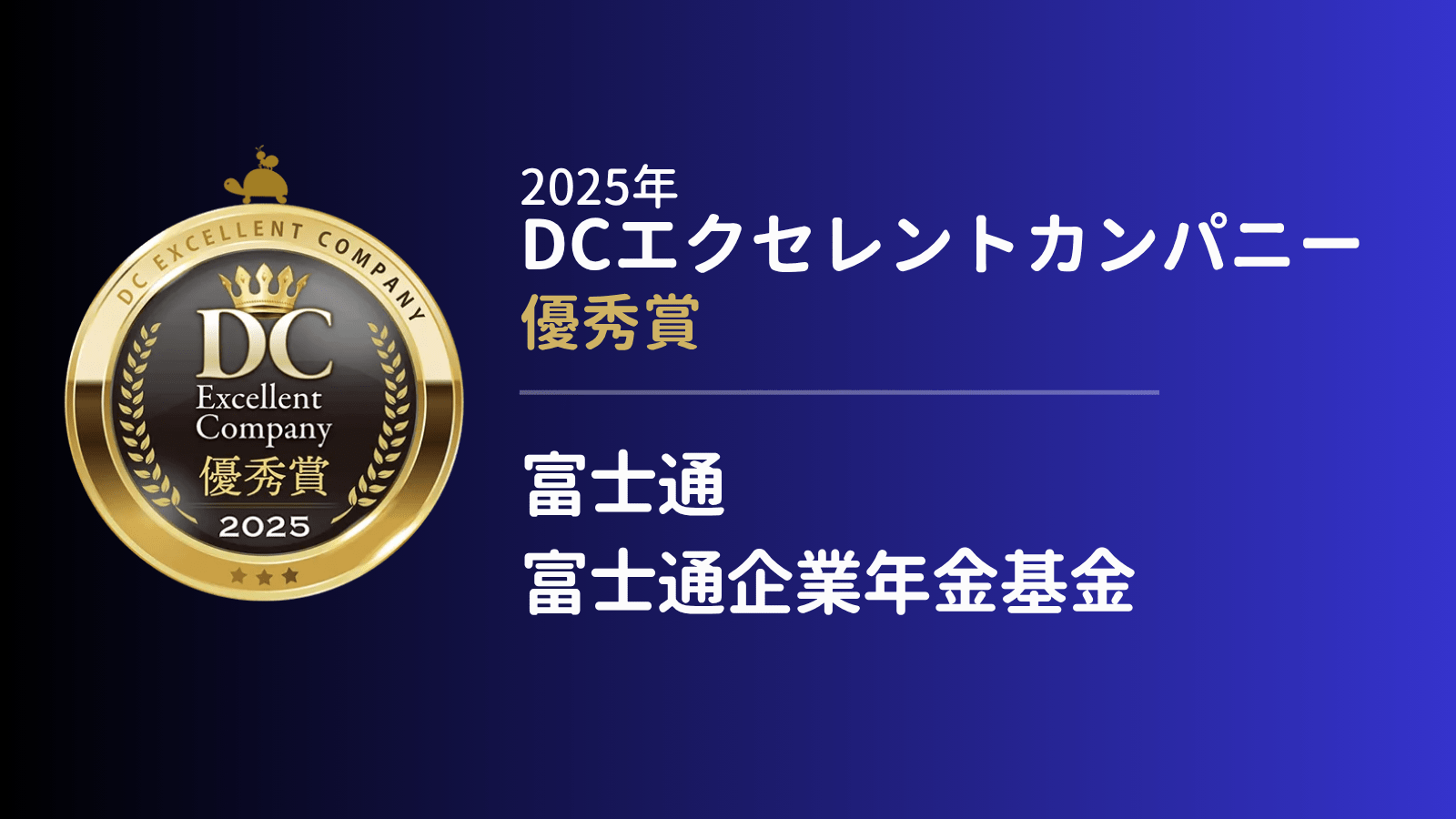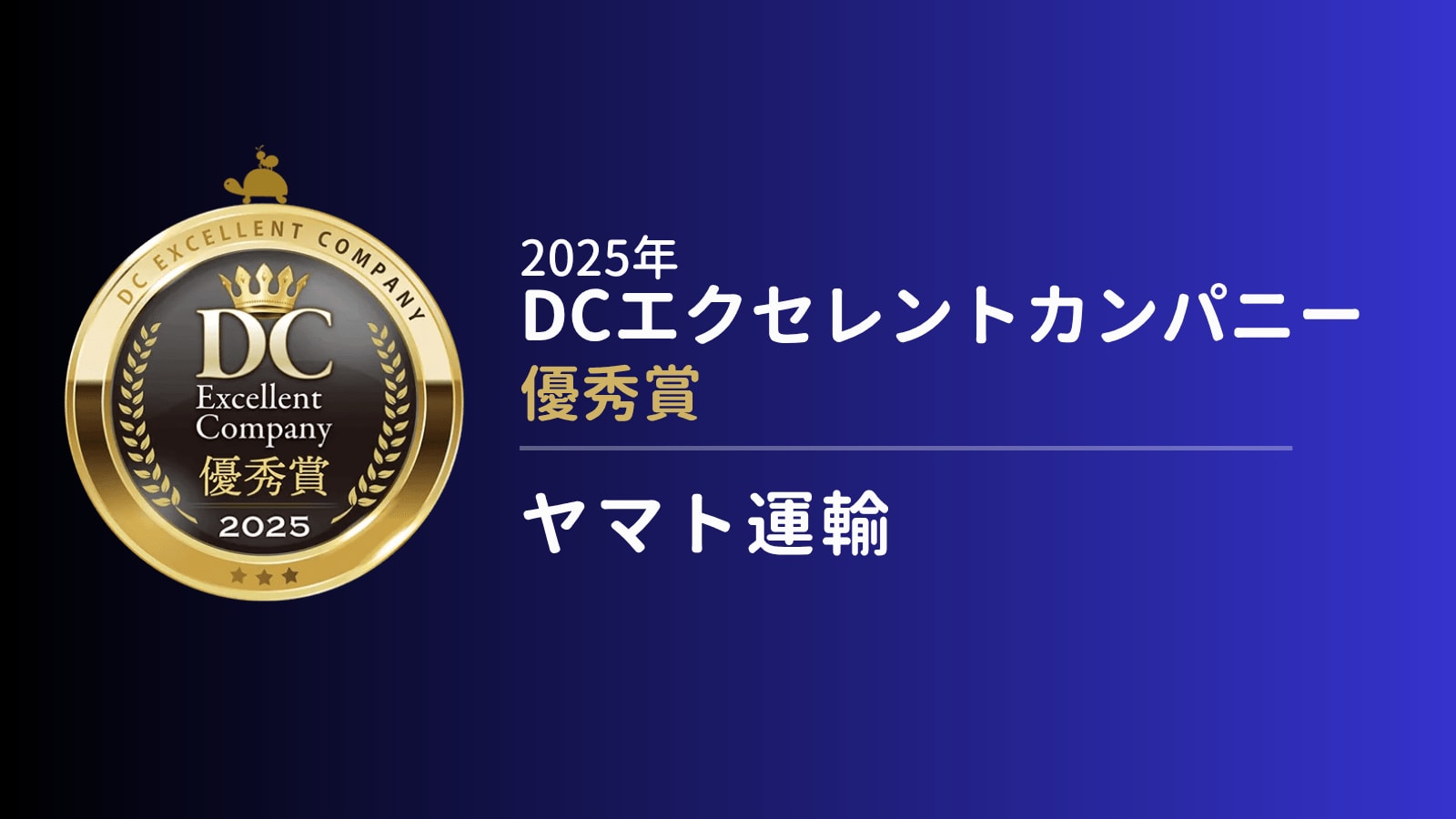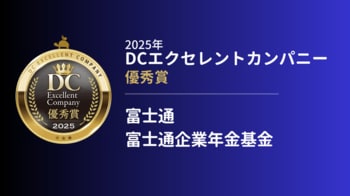運管とのコミュニケーションがガバナンス評価の第一歩
ガバナンスのもう一つの要諦に運営管理機関の評価があります。難しい問題ですが、今から取り組めることの一例として普段からの運営管理機関とのやりとりを記録しておくことが挙げられます。運営管理機関ときちんとコミュニケーションをしている実績を加入者に示すことの証左となるからです。
一方で、当社もガバナンスは道半ばと心得ており、まだまだ課題もあります。
今後の制度運営における最大の課題はDCに対する加入者の理解と関心のレベルを上げること。Web上で自身のDC残高を確認したことがある加入者は全体の50%程度、さらに直近1年以内に確認した人は30%程度にとどまります。
加入者全体の理解レベルを底上げしていくことが先決です。加入者の理解が深まれば、おのずとガバナンスに求められるレベルも上がってきます。特に今の20代は投資に対する理解が40代、50代よりも高い傾向にあり、彼らが中堅となる10年後、20年後に求められるレベルは変わってくるはずです。
ガバナンスについて「何から手をつけたらよいか分からない」という声をよく聞きます。基本的には「あるべき姿」を考え、できるところから着実に進めていくしかありません。当社も制度導入時に60%だった投資信託比率が現在80%にまで上がってきましたが、特別なことを行ったわけではありません。
毎月のメールマガジン配信など地道な活動の積み重ねの結果です。小さなことからコツコツと、担当者があきらめずに続けていけば、必ず何年後かに成果は出てきます。

会社概要 本社:大阪府大阪市 業種:建設業 加入者数:36,177名