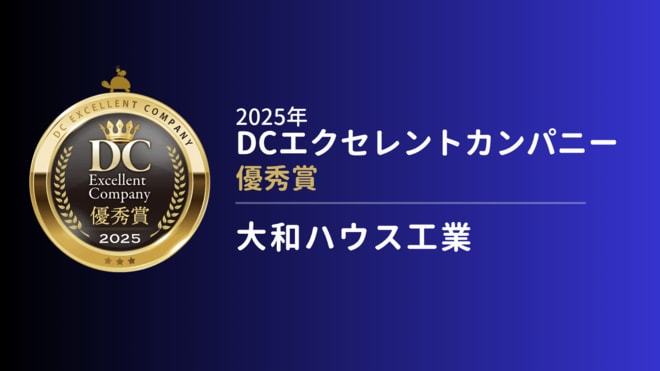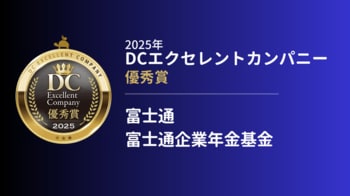近年、人材を資本として捉え、その価値を最大限に引き出す人的資本経営が注目されている。その観点からも企業年金の一つである企業型確定拠出年金(DC)制度の充実は、従業員の活躍やエンゲージメントを高める一因として企業価値の向上に資することが期待されている。企業型DC制度運営に熱心な企業はどのような取り組みを行い、そしてどんな成果を実現しているのか。DC制度運営に秀でた企業に贈られる「2025年DCエクセレントカンパニー」ガバナンス部門において優秀賞に輝いた大和ハウス工業の取り組みを紹介する。
企業型確定拠出年金(DC)制度を効果的に運営するためのガバナンス体制の強化は各社にとって避けて通れない課題の一つだ。グループ会社間の心理的距離を縮め、加入者目線での制度改善に取り組む大和ハウス工業では、DC運営委員会を中心に商品や制度運営に関するモニタリングを継続的に実施、グループ間の有機的な連携によるガバナンス体制を実現している。その要諦を大和ハウス工業 本社 経営戦略本部 人事部 担当部長 臼井 一博氏に聞いた。
多様な業種が集まるグループ各社の課題をヒアリングで深掘り
2011年4月のDC導入から14年以上がたち、現在はグループ32社(うち同一規約24社、独自設計8社)の規模となりました。退職給付制度は、同一規約の24社の場合、退職一時金、確定給付企業年金(DB)、DCの三本立てとなっています。
DC制度の運営は導入当初に発足したDC管理室が中心となり担ってきましたが、2025年4月の組織改編により現在は当社人事部に統合されています。
以前から研修会等を通じて各社の取り組みをディスカッションするなど横のつながりを重視してきました。
グループ全体のDC制度運営をより一層強化するためにDC運営委員会を設置したのが2024年4月になります。メンバーは当社人事部、財務部、企業年金基金とグループ会社7社(同一規約4社、独自設計3社)の各担当者。現場の実態に即した議論とするため参加者の役職は指定せず、実務担当者にも参加してもらっています。また、オプザーバーとして運営管理機関などにも参加いただいています。
制度運営の効果を上げるにはグループ会社との連携強化が不可欠です。DC運営委員会の発足に際して事前に各社から日ごろ感じている課題や困りごとなどをアンケートで収集しました。
当社グループは建設業だけでなく、ホテルや小売業など多様な業種・業態から成り立っています。各社で働く従業員は多様性に富んでおり、その特徴はDCの運用商品の選択傾向にも表れています。具体的には、元本確保型商品への投資比率が極端に高い会社、逆に投資信託比率が非常に高い会社など、顕著な違いがあるのです。
このような特性も見えてきたため、グループ各社の課題をさらに深掘りするべく、若手担当者を派遣してヒアリングを実施しました。親会社と子会社の関係では、どうしても子会社側に親会社に対する遠慮が生まれがち。私自身もグループ会社勤務が長かったのでその気持ちが分かります。
実際に顔を見てヒアリングすることが重要で、顔を見たことがある人とそうでない人とでは相談のしやすさが全く違います。グループ会社の担当者に「こういう人が担当してくれているなら聞きやすい」と思ってもらえる関係づくりを目指しました。